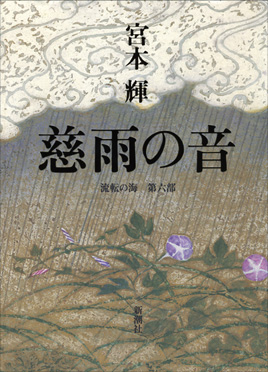野の春―流転の海 第九部―
2,310円(税込)
発売日:2018/10/31
- 書籍
執筆37年、シリーズ累計230万部の大作
「流転の海」、第九部でついに完結。
自らの父をモデルにした松坂熊吾の波瀾の人生を、戦後日本を背景に描く自伝的大河小説「流転の海」。昭和四十二年、熊吾が五十歳で授かった息子・伸仁は二十歳の誕生日を迎える。しかし熊吾の人生の最期には、何が待ち受けていたのか。妻の房江は、伸仁はどう生きていくのか。幸せとは、宿命とは何だろうか──。感動の最終幕へ。
書誌情報
| 読み仮名 | ノノハルルテンノウミダイキュウブ |
|---|---|
| 装幀 | 榎俊幸/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 408ページ |
| ISBN | 978-4-10-332519-2 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文学賞受賞作家 |
| 定価 | 2,310円 |
書評
「流転の海」を数えてみた。
すごい。
ひたすらすごい。
そういう小説だ。
9冊読了後の感想として、そういう言葉しか出ない。
ある男の後半生が描かれている。
いろんな人生と交錯し、じつに深く広く、鋭く、人間が描かれている。
なにせ、長い。長いけれど、読みやすい。読みやすいけれど、深い。
1巻からしっかり読めばいい。9巻だけ読んでもおもしろいとおもうが、1巻から読んだほうが味わい深い。3巻からどうしても読みたいと泣きながら訴えられたら止めはしないが、2巻を飛ばすのはもったいないとおもう。2巻は胸に響くぜ。
文庫本の8巻までで4021ページ、最終巻の単行本402ページである。まあ、ざっくり4500ページくらいだ。見開き2ページを1分で読めば38時間くらいで読み終える。1日13時間読めば3日で読破だ。がんばれ。
この物語では、多くの生と死が描かれている。読んでいると、いくつもの死に出逢う。「生きている姿」に馴染んでいると、ときに突然、または徐々に、その人が死んでいく。死ぬのは人だけではない。馴染んだ犬や牛や馬や鶏や金魚や鮎や蚊も死んでいく。いくつかは馴染みじゃないけど。
物語が進んでいくなか、ああ、死んじゃった、と胸揺さぶられた「死」が35回あった。けっこう多い。死ぬとは知らずに読んでいたら死んじゃった人が35人(33人と2頭)いたのだ。回想シーンの死は入れていない(回想シーンまでいれれば、胸揺さぶられる死は52人になってしまう)。
南宇和にいたとき、主人公は「人が死にすぎる」と呟いたことがあったが、その後もそれは止まらない。
人は死ぬんである。
荷車を引いて有馬温泉に向かう途中で警察に捕まる。直腸ガンが見つかる。二階の窓から転落する。猟銃で頭を吹き飛ばす。船が燃える。山中の切り株に座ったままになる。部屋に鍵をかけてその鍵を捨てるよう頼んで睡眠薬を飲む。姉の帰りを待って暑い部屋で横たわる。乳癌の転移が見つかる。温泉宿で首を吊る。仕事場で準備しているときに脳溢血で倒れる。女の子を乗せたクルマで大型ダンプカーに正面衝突してしまう。
人は死ぬんである。
生きていると、人と関わる。
主人公の人との関わりが実に多彩である。
こっちからどんどん深く関わっていってやろう、という性根があるからだろう。
たとえば、主人公の熊吾は、いろんな会社を経営するが、いつも金を持ち逃げされる。笑っちゃうくらいに横領されるのだ。信頼している男に何度も金を持っていかれる。
伝聞の形で5回(上海時代に2回、戦前に2回、戦中に1回)。
そして戦後には3回ある。1巻と4巻と7巻で出てくる。
戦後の3回はそれぞれ違う会社である。通算8回。
なかなかすごい。
どれだけ持ち逃げする男を雇うんだという意味ですごく、どんだけ次々と「ここは持ち逃げできそう」とおもわせる会社を作ってるんだろうというところがすごい。そういう関わりを作ってしまう男なのだ。
会社にあった金を根こそぎ横領されても、この男はへこたれない。また次の事業に取りかかる。神の試練に耐える選ばれた民のようだ。昭和の元気は、熊吾たちが背負っていたのだろう。
お節介でもある。
困ってる人は助ける。困ってなくても助言する。どんどん関わる。
1巻から9巻まで、熊吾はどれぐらい人と関わったのか、ちょっと数えてみた。
だいたい947人である。だいたいのわりに端数だが、気にするな。妻の房江や息子の伸仁だけと関わりのある人物でも、熊吾とも関係があるかどうかを推察するしかないので「だいたい」になるのだ。気にするほどの誤差はない。ちなみに物語全体で出てきた人物数は私の数え方によるとだいたい1252人である(確定数ではない。以下の数字も含め、これからもう一度確認しておく)。
物語の進展にまで関わる中心メンバーが55人、それに準ずる忘れがたきメンバーが38人、熊吾との親交が深かった人だけで203人、ここまではみんな名前が出ている。昭和22年以前にだけ親交があった人が98人、名前がわからないけれどとにかく何かしら魂の交錯があった人が181人。名前が列挙されただけでどんな人かよくわからない人が41人。
とてもたくさんだ。有名人が出てこない小説としては日本文学史上、屈指の登場人物数ではないかとおもうが、日本の小説を全部読んだわけではないので、歴代何位かはわからない。私が登場人物数を数えたことがある小説では断然一位である(ほかの小説を数えたことがないので、当たり前なんだけど)。
名前はわからないけど魂が交錯した人とは、たとえば、ニセ医者をやっていたとき、見立て違いで少女を死なせてしまったが、その両親は熊吾が逃げ出すときに見送りに来てくれたとか、長崎に行く夜行で一緒になった若い勤め人は「長崎で被爆した上司が一年後に川にめだかが泳いでいるのを見て涙が止まらなかった、めだかになりたいとおもった、と言っていた」と教えてくれたとか、戦争で耳が聞こえなくなった店主がやっている玉川町の飲み屋では品書きを棒で指して注文するのだが、熊吾がやくざと関わっているのをみると、やめておいたほうがいいと目顔で知らせてくれたとか、そういう人たちである。
ときに数行しか描かれてない。それでもしっかり生きている姿が伝わり、いくつもの人生がそのまま埋め込まれている。すごい小説である。
魅力はそれだけではない。昭和の光景、それぞれの土地の風景(特に「大阪の巷」)が生き生きと描かれ、胸に迫ってくる。
平成屈指の大作である。

より詳しい分析が「webでも考える人」でお読みいただけます。
(ほりい・けんいちろう コラムニスト)
波 2018年10月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
宮本輝「流転の海」完結記念インタビュー
大きな人間の、大きなドラマを書きたかった。

聞き手/堀本裕樹
自らの父をモデルにした松坂熊吾とその家族の波瀾万丈の人生を、戦後の時代を背景に描く自伝的大河小説「流転の海」。執筆開始から三十七年、第九部『野の春』の刊行で、ついに完結を迎えます。三十七年間を振り返っての感慨、そして作品に込められた想いを、長年宮本作品を愛読してきた俳人の堀本裕樹氏が伺いました。
──三十七年もの間、「流転の海」という大長編を書き続けられて、このたび完結を迎えられました。読者の一人として、本当にありがとうございました。そして、本当にお疲れ様でした。僕は最終巻を読み終えて、しばらく放心した状態でした。今風に言うと「流転の海ロス」みたいな状態で、充足感と共に、終わってしまったんだなあ、という喪失感が自分の中に渦巻いています。今はどのような心境でしょうか?
人生何が起こるかわかりませんから、途中で私が倒れたりしたら、どうにもなりません。最後の数行は頭の中に出来ていましたけど、ノートにも付けてないし、とにかく未完で終わらせられないという思いでしたので、今は責任を果たせたという感じです。第一部の単行本が出た時に八十代の読者から、生きているうちに最後まで読みたいというお手紙を頂いたのですが、あれから三十五年ですから……。なんとかもう少し早く書けなかったか、申し訳なかったなあ、という気持ちもあります。
ロスという言い方をするなら、私の中で一番ロスが起きなきゃいけないですが、三十七年間僕の中に住み続けた松坂一家とやっと別れられた、ちょっとつき合いも疲れたかな、というのもあります。
しかし最後まで書けたのは、第一に自分が健康であり続けられたからですから、そのことに感謝したい。何か守られたなあ、という気持ちの後に、だんだん自分を褒め称える気持ちが湧いて高揚してきました。お前はえらい、よくやった、と。その時期が過ぎると、長い小説くらい誰でも書く、問題は中味だ、それはどうかな、と少し内省的になっているのが今の時期です。
──大長編だからこそ、作者の心境も波のように変わっていったんですね。
書いている途中も常にそういう状態がありました。
「親父、仇を討ったで」
──『ひとたびはポプラに臥す』の中で、印象に残っているくだりがあります。【「お父ちゃん、俺が仇を討ったるで」父が死んだとき、二十一歳の私が胸のなかでつぶやいた言葉】ですけれど、僕は『野の春』を滂沱の涙で読み終えた時、「ああ、宮本先生はこの小説を完結させて、父君の仇を見事に討ちはった」と思いました。
最後の三巻くらいは、親父の仇を討つという気持ちはなくなっていました。書いている間に自分も年齢を経て、内面的に変わったのを感じましたし、この小説に登場する全ての登場人物の、戦後の時代を懸命に生きてきた、それぞれの宿命というものをねぎらいたい、という気持ちに変わってきました。そして僕が生きてこうして小説家になり、この小説を完結させたということが、つまり父の仇を討ったということになりますよね。だから最後には、「親父、仇を討ったで」という心境になりましたね。
──いま「流転の海」を完結させて、父君に伝えたい言葉はありますか?
伸仁のことを、「うまくいけば、偉大な芸術家になる」と言った易者の言葉がありましたが、「うまくいったやろ? 小説家になって、松坂熊吾という名前に託して、宮本熊市という男を俺は顕彰したぞ、これ以上の親孝行があろうか」と親父に言いたいです。親父には書かれたくないこともあるだろうから、いや、あそこが気に入らん、とか言われるかもしれませんが(笑)。
──お母様にお伝えしたい言葉はありますか。
「流転の海」は前半は熊吾の物語ですが、『花の回廊』あたりからだんだんと房江の物語になっていきました。物陰で寂しそうに泣いていた母親が、自殺未遂事件を契機に一気に変わります。奇跡的に命を取り留め、人生の不思議というのを強く感じ、自分は生きなければならない人間なのだ、という考え方になったんだと思います。
──父君のたくさんの言葉や教えてくれた箴言などで、「流転の海」を書くにあたって、また人生において、励みになった言葉はございますか?
それはもう、「なにがどうなろうと、たいしたことはありゃあせん」という言葉です。小説にはあえて書かなかったんですが、僕が、「でもお父ちゃん、明日死ぬって言われたら、それはたいしたことやろ?」と聞いたら、「それは死ぬだけじゃ」と答えたんです。死もたいしたことじゃない、と。死は永遠の終わりではなく、もう少し違うような気がすると言うんですね。「それは何で?」と聞いたら、「お前も戦場に行ったらわかる」と答えました。

──『野の春』の最後の方で熊吾が戦争の場面を妄想するところもありますね。そして房江が熊吾の最期にやはり、「なにがどうなろうと、たいしたことはありゃあせん」と熊吾に語りかけられている気がした、という一文にも僕はぐっと涙を堪えました。
もう一つはやはり、「自尊心よりも大切なものを持って生きにゃあいけん」ですね。だけどある時、「わしほど、自尊心のために生きてきた人間はおらん」と言ってました(笑)、書きませんでしたけどね。でもやっぱり一番忘れられないのは、『野の春』で書いた、寒い夜に屋台で言われた言葉ですね。あの言葉はこたえて、五十歳位になるまで消えなかったです。父への憎しみというより、申し訳なさです。あの時の寒さと、早く父から去りたいという気持ちも覚えています。だから絶対、小説に書こうと決めていました。
──たとえば第一部で柳田元雄の未来を見通す熊吾の言葉があります。「やがて巨大な城の主となるかもしれない。そのとき、自分はどうなっているだろう」。また海老原に対しても、「お前の臨終の顔は、目ェそむけるくらいに、歪んで汚ならしいことじゃろう」と。九部からなる大長編にもかかわらず、その第一部で既にこんな布石を打っている宮本先生の手腕に改めて驚きました。そもそもこの「流転の海」全体の構想は、どのように組み立てていかれたのですか?
まったく組み立てずに書き始めました、こんなに長くなると思いませんでしたから。最初は長くて五年、全三巻と考えていましたけど、三巻書いても終わらない。全五巻に延ばさなければしょうがない、と思ったのに五巻でも終わらず、次は七巻にしようと決めたんですが、ついに九巻まで来てしまいました。しかし柳田と海老原、この二人は小説の終わり頃には必ず出てくるだろうな、という予感はあったんです。でも、これは小説ですから、実際に起こったことは三分の一くらい、あとは僕の創作です。虚実混じり抜いた全九巻です。
──『野の春』を読み終えたあと、すぐに第一部に帰って読み始めて感じたことは、この物語は永遠に終わらないのだということでした。永久に循環している。第九部で死んだ熊吾が、第一部に戻ると、バッと立ち上がって生き生きと闇市の中を歩いて、蘇っているんですね。これはすごい小説やぞ、と改めて思いました。
いち早く読み終えた人からもそういう感想をいただきました。第一部「流転の海」の冒頭の大阪駅のシーンへと、また続いているようだというんですね。
──終わったけれど終わっていない、ずっと続いていて、まさに物語全体が流転している。こんな小説を読んだことはないなあ、と思いました。この小説の凄みを改めて感じたのですが、例えば『五千回の生死』でも、「死んでも死んでも生まれてくる」ことを一つのテーマに書かれていますが、それはなぜですか?
生死というものほど、人間にとって大問題はない。それが僕の小説の大きなテーマなんです。生という一文字の中に生老病死ということが含まれていて、生きるということは楽しいことでもあるし、苦しくもあるし、様々なことが起きて、長い人生では病と戦う時期もある。僕自身、作家になった頃に結核で倒れましたし、その前のサラリーマンの時代にはパニック障害で会社へ行けなくなるし、子供の頃は体が弱くて二十歳まで生きられないだろう、と言われ、常に死というものが自分の中に大きな恐怖としてあったんです。でもある時から、死はそんなに怖いものではないんじゃないか、と思えるようになった。太平洋のど真ん中に万年筆のインクの一滴をポトンと落としたら、その色は一瞬で広がって元の海の色になるけれど、インクは消滅したわけじゃない。大海原の中に溶け込んでいった。死というものはそういうものだ、とその話を聞いた時、腑に落ちたんです。
──それは「流転の海」の「海」にもその意味合いはかかっているんでしょうか。
そうです。「流転の海」という全体のタイトルをつけた時に、そういう大きな構想はあったんです。つけてしまってから、エライことになったな、そんなことをどう小説として表現していくんだ、と思いましたけどね。

星廻りと喧嘩していた頃
──「流転の海」を読み終えていろんな感慨に浸りましたが、一つの感慨として、「人間」というものは全く一筋縄ではいかない、生きるということは甘いものではない、ということでした。例えば最終巻でも、愚かな関係があったり、長年の約束を反故にしたりという裏切りを、読者として突きつけられて、改めて人間の複雑さ、恐ろしさを感じました。「流転の海」で人間の明るい部分だけではなく、暗部を痛烈にお書きになる理由は何でしょうか?
人間というのは千変万化に心のありようが変わり続けている、そういう生き物であり、命というのは刻々と変わっていくものなんです。だから絶対に裏切らない男だと見極めるには、どうしたら良いのか、僕もいまだにわかりません。
昔ある方から、「機を知れば心自ずから閑たり」という言葉を聞いたことがあります。人生において何が最も大切かということをわかってさえいれば、色んな悩みや厄介な問題があろうとも、心は
──第一部で熊吾が辻堂に、「星廻りとケンカをしてこそ、ほんまの人生やとは言えんかのお」と言う場面がありますが、ご自身は星廻りとケンカしたことはございますか?
やはり重症の結核とパニック障害との戦いですね。これらは自分の中に持って生まれたものですし、勝負つけてしまわなければ早死にしてしまうと思ったから、命懸けで療養しました。病気に勝とうという闘魂の気持ちを養っていくことを数年間経験したことが、自然に自己鍛錬になっていたと思います。
医者がもう薬を飲まなくていい、と言ったのが三十四歳の時でした。やった、宿命を乗り越えた、と思ったらパニック障害が悪化しました。白いものと先が尖ったものがイヤで、原稿が書けなくなった。しかし良い医者と出会い、「これは天才がかかる病気です」なんて励ましてくれまして、何とか病と付き合いながら、取りかかっていた『錦繍』を書き終えました。その後『ドナウの旅人』のための海外取材にも行って、体力的にも精神的にも自信が出来てきた頃、「流転の海」に取り掛かったんです。ですから、自分の星廻りと喧嘩していたのは、「流転の海」を書き始めた三十四歳の頃です。
──熊吾は「人間はしあわせになるために生まれて来たんじゃ」と言っていますが、「流転の海」では「しあわせ」を、房江始め、何人かの登場人物が感じる場面があります。宮本先生にとって、または宮本文学にとって「幸せ」とは何でしょうか?
まあそこそこ食べていけるだけのものがあって、家族がいて、ちょっと夜更かしして一杯飲んで、布団に入って、「ああ、幸せだなあ」と思う時もあります。人によってみんな違う、それぞれですね。何なんでしょうね、幸せって。言葉にできるなら、文学なんて必要ないですね。
──読むたび自分にとって幸せとは何か、と考えさせられる小説ですよね。

宇宙の闇と秩序とはいったい何か
──芭蕉の言葉に「高くこころをさとりて俗に帰るべし」というのがありますが、「流転の海」を読み終え、宮本先生はその言葉を体現されていると思いました。平易な言葉を以て俗世間を描きながら、宇宙のような壮大で深遠な物語を完成させられているのを読んで、この言葉が浮かびました。僕もこの言葉のような俳句を作りたいんですが、なかなかそうはいかない。「流転の海」はまさにこの言葉を表しています。
それは僕のものすごく好きな言葉で、実に至言だと思っています。作家としてそういうふうにありたい、と思っているので、今、図らずも堀本さんの口からお聞きして、本当にうれしいです。
──かつて福武書店版の『流転の海』の「あとがき」に、「自分の父を
宇宙の闇と秩序って一体何なのだ、ということを考えてきて、『野の春』の「あとがき」で、「ひとりひとりの無名の人間のなかの壮大な生老病死の劇」であると書きました。だから最初に書いたあとがきを、僕はきちんと自分への誓いとして守ったということですね。
──僕も一読者として、最後に本当にそう思いました。
自分でこんなこと言うと傲慢に聞こえるでしょうけれど、今は自分でどんなに褒めても褒めたりないので(笑)。
──僕のように、松坂家を自分の親戚のように見守りながら、読み続けてきた読者がたくさんいると思います。最後に読者へのメッセージをお願いいたします。
長い間、松坂熊吾一家に寄り添って生きてきた読者がたくさんいらっしゃると思います。いつまでたっても終わらないので、宮本輝はちゃんと仕事しているんかいな、とお叱りのお手紙もいただきましたが、こうやって無事に書き終えることが出来ました。こんなに長く、まあ地味な小説ですが、そんな小説を三十七年間待ち続けて読み続けて下さり、本当にありがとうございました。おかげで、書き終えることが出来ました。どんなに御礼を言っても言い足りない、そんな心境です。
(2018年8月21日、軽井沢にて)
波 2018年10月号より
単行本刊行時掲載
「流転の海」と私
竹増貞信

いつか息子たちにも読んでもらいたい。
『流転の海』を読むたび、「宿命」というものの重さ、凄まじさ、それをコントロールする「理性」の儚さのことを、くり返し考えます。また熊吾の「自分の自尊心よりも大切なものを持って生きにゃあいけん」という言葉は、仕事に誇りとプライドを持ちながらも、それをいつでもかなぐり捨てる覚悟はあるか、と自らに問うものとなりました。『流転の海』には人生を切り開く上で大切なことが書かれています。いつか息子たちにも読んでもらいたい本です。
小川洋子

宇宙で光を放つ星座に導かれて。
全人生をかけて息子を愛し抜く情の深さと、闘牛を撃ち殺す荒々しさ。熊吾の中でその両方は矛盾なくつながり合い、一つの宇宙を成している。闇は濃く、底知れないが、同時に、すべてを抱き留める度量を持っている。彼に引き寄せられた人々の放つ光が、壮大な星座となる。その星座をたどっているうちやがて、時間も生死も超越した宇宙の摂理に導かれている自分に気づく。何と深遠な小説だろう。
中村義洋

人として父として、かくありたい。
視点の切替、伏線の置き方、邂逅の必然、妬みの怖さ、父とは母とは……物語の在り方はすべて『流転の海』から学んできたように思います。
二十代で読み始めて二十数年。間もなく自分は第一巻の熊吾の年齢に達します。それに近づくにつれ熊吾の気持ちが痛切に沁み入り始めた頃、第六巻のタイトルに「慈雨」の文字。これだけで泣いてしまいました。人として父として、かくありたいです。
壇蜜

愛とは何か、考えさせてくれる小説。
『流転の海』に出会って以来、この大きな物語の深い海に浸っています。圧倒的に強い父の熊吾、繊細で気丈な母・房江、愛情を注がれて育つ賢い伸仁の三人からは、何が起きても決して絆を失わない家族の深い愛を教えてもらいました。特に、熊吾の破天荒さに翻弄されながらも、しっかりと自分を保つ房江にとても刺激を受けました。
私にとって幸福とは愛とは何か、何のために生まれたのか、などを考えさせてくれる大切な本です。
北上次郎

ここには私たちの人生のすべてがある。
『流転の海 第二部 地の星』が上梓されたとき、未読の第一部を取り出して読んだときの興奮は忘れない。それまでもこの作家の全作品を読むほどの愛読者であったが、いま読んでいるものは、この作家のベストであるだけでなく、おそらく永遠に残り続ける作品だろうと深い確信を抱いた。
父と子がいて、男と女がいる。経済があり、政治があり、社会がある。ここには私たちの人生のすべてがある。
波 2018年10月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
宮本輝
ミヤモト・テル
1947(昭和22)年、兵庫県神戸市生れ。追手門学院大学文学部卒業。広告代理店勤務等を経て、1977年「泥の河」で太宰治賞を、翌年「螢川」で芥川賞を受賞。その後、結核のため2年ほどの療養生活を送るが、回復後、旺盛な執筆活動をすすめる。『道頓堀川』『錦繍』『青が散る』『流転の海』『優駿』(吉川英治文学賞)『約束の冬』(芸術選奨文部科学大臣賞)『にぎやかな天地』『骸骨ビルの庭』(司馬遼太郎賞)『水のかたち』『田園発 港行き自転車』等著書多数。2010 (平成22)年、紫綬褒章受章。2018年、37年の時を経て「流転の海」シリーズ全九部(毎日芸術賞)を完結させた。