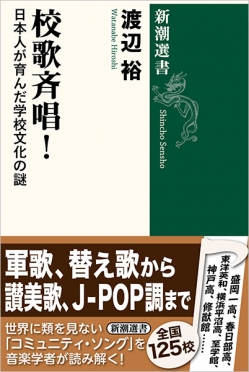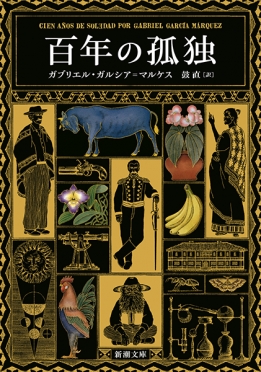オルタネート
1,815円(税込)
発売日:2020/11/19
- 書籍
私は、私を育てていく――。誰しもが恋い焦がれた青春の普遍を真っ向から描き切る、加藤シゲアキ、これが新たな代表作。
高校生限定のマッチングアプリが必須となった現代。東京のとある高校を舞台に、3人の若者の運命が、鮮やかに加速していく――。恋とは、友情とは、家族とは、人と“繋がる”とは何か。悩み、傷つきながら、〈私たち〉が「世界との距離をつかむまで」を端正かつエモーショナルに描く。著者3年ぶり、渾身の新作長編。
2 代理
3 再会
4 別離
5 摂理
6 相反
7 局面
8 起源
9 衝動
10 予感
11 執着
12 門出
13 約束
14 確執
15 結集
16 軋轢
17 共生
18 焦燥
19 対抗
20 同調
21 不信
22 祝祭
23 胸中
24 出発
書誌情報
| 読み仮名 | オルタネート |
|---|---|
| 装幀 | 久野遥子/装画、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 384ページ |
| ISBN | 978-4-10-353731-1 |
| C-CODE | 0093 |
| ジャンル | 文芸作品 |
| 定価 | 1,815円 |
インタビュー/対談/エッセイ
結局、描きたいのは「人間」でした。
司会・構成:吉田大助
3年ぶりの新作小説を刊行した加藤シゲアキさんと、現役大学生で三島由紀夫賞を受賞した宇佐見りんさん。SNSとアイドル、双方の関係性を手がかりに、奇しくも第164回芥川賞(宇佐見さん)・直木賞(加藤さん)で候補となったご両人が、創作の深淵に迫ります。
――「高校生限定」という架空のSNSを題材に描かれる青春群像劇『オルタネート』と、男性アイドルの推し活動をSNSで行う女子高生が主人公の『推し、燃ゆ』。この二作、この二人の並びを考えて、今回の対談を企画した人は天才だなと思っていたんですが、待合室で聞いたら、加藤さんの発案だったそうですね。
加藤 『オルタネート』の刊行記念で対談をという話になった時に、宇佐見さんのお名前を挙げさせてもらいました。まだその時は『かか』も『推し、燃ゆ』も読んでいなかったんですが、いい作品だという噂はいろんな人から聞いていたんですよ。『オルタネート』は高校生を描いているので、なるべく若い方の感想を聞いてみたいなという思いもありました。その後、三島賞を取られた『かか』を読ませていただいたんですが、面白すぎて絶望するぐらい良かった。「もう俺、小説書くのやめようかな!」ってなりました。
一同 (笑)
加藤 『推し、燃ゆ』も素晴らしかったです。
宇佐見 ありがとうございます。私は、自分が小説家になるずっと前から、本屋さんで加藤シゲアキさんのお名前はお見かけしていました。大先輩である加藤さんにそんなふうに言っていただけるなんて、信じられないです。私は今回『オルタネート』を読ませていただいたんですが、発想力に驚きました。東京の高校が主な舞台で、「オルタネート」という架空のSNSの存在が、三人の主人公のパートを繋いでいく。そのSNS自体のオリジナリティがすごいんです。小説の中で、「自分だけのオルタネートを育てる」という話が出てくるじゃないですか。
加藤 オルタネートに自分のスマホの中の情報を全部提供すると、どんどん自分のことを理解していって、高い精度で自分に合った恋人や友達をマッチングして紹介してくれるようになる。お話の途中からは、遺伝子検査した結果をオルタネートに提供すると、「遺伝子レベルの相性」もわかるようになっていきます。その辺りのことを、オルタネートが「育つ」という言葉で表現しました。
宇佐見 SNSは道具というイメージが私の中ではあったんですけど、まるで生き物のように捉えている。いろいろな人間関係だけではなく、「自分対オルタネート」の関係も描かれているのがすごく面白かったです。
加藤 宇佐見さんの小説も、「自分対SNS」の部分が書かれていますね。二作の主人公は、SNSを通じて社会と繋がっているのと同時に、自分を見つめている。SNSの中に現れる自分が、自分というものの合わせ鏡になっている。自分そのもの、ではないんですけどね。『オルタネート』の中では、ある女の子に、自分の言葉を「吐き捨てるために」SNSを使っていると言わせたんですが……。
宇佐見 あのシーン、良かったです。
加藤 ネットに流す言葉には、誰かに届けたい言葉と、吐き捨てたい言葉がある。そうした言葉の裏には、別々の自分がいる。SNSは、そのどっちもが入っている「容器」という感じがします。そういうモノと自分との関係を描くことは、これまでの小説ではできなかったことだと思うんです。
自分なりの神を「信じる」
その姿が、個の表現になる
――宇佐見さんの第二作『推し、燃ゆ』は、主人公の「推し」がファンを殴り、炎上してしまったことから始まる物語です。そのニュースを受けて、主人公はブログやSNSで擁護していく。デビュー作の『かか』も、メインは娘と母の関係なんですが、娘はSNSの裏垢で「推し」のファンたちと常時繋がっていました。二作とも、SNSが重要なアイテムとして登場しています。
加藤 僕が学生時代にはSNSと呼ばれているメディアはまだなくて、高校の頃にミクシィが始まったぐらい。そういう世代の人間からすると、小説でSNSを出すことってチャレンジという感覚があるんです。小説の文章、いわゆる文語と、SNS特有の口語のような文語は相性が良くないというか、一緒に並べるとちぐはぐになりやすい。無自覚なまま書くと、SNSの部分が記号的になりかねないんです。近年SNSを描く文芸作品が増えてきていて、みなさん大なり小なり悩んでいるのかなぁと思ったりしていたんですが、宇佐見さんの小説はめちゃめちゃナチュラルに混ざり合っている。
宇佐見 私は小説でSNSを書くことに関しては、チャレンジであるとか、難しさは感じていなくて。というのも、私は今二一歳なんですが、中高校生の頃からSNSは浸透していたんです。当り前のように生活に溶け込んでいるので、「衣・食・住・SNS」みたいな。
一同 (笑)
宇佐見 現代が舞台の小説を書こうとした時に、自然と出てくるものなのかなぁと感じていました。
加藤 さらっとやってのけるのがすごいですよね。小説界の「第七世代」だ(笑)。ただ、『かか』も『推し、燃ゆ』も、SNSを通して何を描いているかというと、人間を書いている。そこは意識されていましたか?
宇佐見 はい。『オルタネート』も、架空のSNSの面白さが全編にありつつ、描かれているのは結局「人間について」なんだなと思ったんです。小説を書いていくと、最後はそこに行き着くのかもしれないですね。
――『オルタネート』には三人の主人公が登場します。高校三年生で調理部部長の新見蓉、高校一年生で帰宅部の伴凪津、学年的には高校二年生ですが中退したフリーターの楤丘尚志。宇佐見さんの「推し」は?
宇佐見 みんな大好きですけど、やっぱり凪津ちゃんです。『オルタネート』はディテールが本当に素晴らしくて、好きなシーンや心に残る言葉がいっぱいあるんですが、その中でも特に好きだったのは凪津ちゃんが、他の生徒たちと一緒に聖書で雨をしのぎながら学内の講堂に入っていくシーン。敬虔なキリスト教徒の方からすると、神聖なものである聖書を傘がわりにするなんて、あり得ないことじゃないですか。
加藤 あれは、僕の母校では見慣れた光景なんです(笑)。
宇佐見 そうなんですね(笑)。凪津ちゃんは宗教への関心はないから、礼拝中もずっとスマホをいじっている。凪津ちゃんは自分にとっての「運命の相手」を、オルタネートに選んでもらおうとしているんですよね。自分の感情なんてあやふやなものではなく、オルタネートという客観的な第三者に遺伝子情報も渡して、科学的に相手を決めてもらおうとしている。そういう意識が、お話が進むにつれてどんどん宗教的なものへと近づいていくのが面白かったんです。礼拝のシーンではあんなにあった宗教と科学のギャップが、クライマックスのシーンでは一致していく。その構造が、読んでいて本当に鮮やかでした。
加藤 彼女にとっての神は、オルタネートなんですよね。現代って、神様がいっぱい作れる時代だと思うんです。ある人物が何を信仰の対象としていて、どれぐらいの熱量で信じているかは、人間を表現するうえで大事な部分になってくると思う。例えば、何かを信じたいって感情は、それに寄りかからないと立てないって弱さの象徴かもしれない。宇佐見さんの『かか』もそうだし、特に『推し、燃ゆ』はそういう神様であり、信仰の話ですよね。主人公は、「推し」のアイドルを祈るように応援することによって、なんとか立つことができている。
――加藤さんはアイドルとしても活動されていますから、推される側ですよね。『推し、燃ゆ』の感想はぜひお伺いしたかったです。
加藤 読みながら、ちょっと気が気じゃないところもありました。もちろん主人公に感情移入して読んでいったんですが、終盤の、推しのインスタライブのシーンは……「ごめん!」と思いましたよ。心苦しくて。
宇佐見 この小説を読んで「ごめん!」と思った、という感想をいただいたのは初めてです(笑)。
群像劇ならではの広がり
一人称ならではの視野の狭さ
――加藤さんにはデビュー作『ピンクとグレー』の刊行時にもインタビューさせていただいたんですが、「純粋なラブストーリーは照れ臭くて絶対に書けない」とおっしゃっていたんです。今回、心変わりした理由とは?
加藤 デビューの頃「書かない」と言っていたのは、「ジャニーズが恋愛小説書いたらしいよ」って色眼鏡に耐えられなかったからだと思います(笑)。なんて言うか、いかにも書きそうじゃないですか。だからその後の作品でもずっと恋愛とは向き合ってこなかったんですけど、書いていくうちに肩の力が抜けていったんですよね。とにかく今自分が書きたいものを書いていけばいいんだって、当たり前のことに気付くことができた。そんな時にマッチングアプリという題材と出会って、ストレートな恋愛群像劇を書いてみたいなと思ったんです。
宇佐見 『オルタネート』は中盤から終盤にかけて、バラバラだった三人の主人公たちがぐーっと集まってきますよね。結末を絶対に見届けなくてはいられなくなるような、のめり込まされる、ものすごい疾走感がある。それは私の小説にはないものなので、「小説ってこんなことができるんだ!」って感動しました。
加藤 嬉しいです。
宇佐見 最後、登場人物たちの行く末を見届けていくような終わり方をするんですよね。そこには、群像劇ならではの世界の広がり方があるように感じました。この物語を世界に敷衍して、自分も群像の中の一人になっていくような、自分自身にも広がりを持たせてくれるような終わり方なんですよ。この広がり方は、まだ私には書けない。
加藤 ……小説、僕ももうちょっと頑張って書いていこうって気持ちになりました(笑)。『推し、燃ゆ』のラストも絶妙でしたよね。主人公が自分をめちゃくちゃにしてしまいたいと思った時に、掴むものが「アレ」。そんなに感情的になっても、冷静なんですよね。この先この子がどうなるのか知りたい、まだまだ読んでみたいって気持ちになりました。宇佐見さんの小説は今のところ、主人公の一人称で書かれていますよね。それはどうして?
宇佐見 主人公の、視野の狭さが書きたかったんです。小説の中でのリアルさを求めた時に、一人称の方が書きやすかったというのもありました。ただ、三冊目は三人称に挑戦してみようかなと思っています。
加藤 語り口でいうと、『かか』の主人公は独自の「かか弁」を使っている。宇佐見さんの小説は、一文一文が濃密で気が抜けない。全てがパンチラインなんですよ。それって本当に力がないとできないことだし、書くのに相当時間もかかるんじゃないかなと。
宇佐見 かかります(笑)。ただ、加藤さんの小説は、私の小説の四倍ぐらいの長さがあると思うんです。逆にお聞きしたいんですが、例えば『オルタネート』ってどのぐらいの期間をかけて書きましたか?
加藤 四ヶ月ちょっと、ですね。
宇佐見 え!?
加藤 直しの期間を入れたらもっとありますよ。初稿はそれぐらいです。初稿は長い下書きだと思って、粗くてもいいからとにかく最後まで書くようにしているんです。
宇佐見 私もそのやり方です。でも、二作とも四ヶ月よりは時間がかかっています。小説家、やめたくなりました。
一同 (笑)
――この辺りで、会場の書店員さんから質問を受けたいと思います。
Q1 小説を書きたいと思っている、若い世代にアドバイスをするなら?
加藤 偉そうなことは言えないですけど、まず書き上げることだと思います。書き始めることは誰でもできるけど、つまらなくてもいいから最後まで書いてみることは、経験値としてものすごく大きいと思うんです。それから、「これが書きたい」という初期衝動と熱量を持続できる、テーマというか対象を見つけることが大事だと思います。頭の中で考えていただけでは見つからないことも多いので、この時代はなかなか難しいですけど、外に出たり人と会って世界を広げた方が、発見は多いんじゃないかなって思います。
宇佐見 私も加藤さんがおっしゃったように、まず書き上げることが重要だなと思います。それと私自身が常に意識しているのは、絶対に自分の言葉で書くことと、新しいものを作るということ。この世界に小説は本当にたくさんあるわけで、それでも自分は新しいものを書くんだという気概があれば、書けるんじゃないかなっていうふうに思います。「この感情は自分にしかないんじゃないか?」とか、自分の中でくすぶっているものは探せば誰しも必ずあると思うんですよね。そういったものを、「全部乗せ」という気持ちで一度書いてみたら、またその先に行けるんじゃないかなと思います。
Q2 店頭で『オルタネート』と『推し、燃ゆ』を並べて展開したいです。お互いの作品に紹介文を書くなら?
加藤 ムズッ!(笑) 持ち帰りたいくらいですけど……「不器用な主人公にとっての推しが、神なのか、悪魔なのか」。そこがこの作品の面白いところだと思うし、悪魔だとしたら救いはないのか? っていう感じかな。
宇佐見 私は……あとでご連絡することってできますか(笑)。その場で考えるのが不得意なタイプなので、ごめんなさい!
加藤 じゃあ僕は、あとで本屋さんに答えを見に行きますね(笑)。
(かとう・しげあき)
(うさみ・りん)
「切断」と「選択」がもたらすもの―『オルタネート』刊行記念対談を終えて―
吉田大助
対談から一週間後、書店に二作のポップが立った。宿題として持ち越された、宇佐見りんによる『オルタネート』へのコメントは――〈迷いながらも走り抜ける彼らの姿に目を奪われました。幾多の「私」の物語だと思います〉。
老舗エンターテインメント小説誌を創刊以来初の重版に導いた加藤シゲアキと、純文学ど真ん中の三島由紀夫賞を史上最年少二一歳で受賞した宇佐見りん。かけ離れた場所で活動しているように思える二人の小説家は、対談記事にある通り、共鳴し合う部分が無数にあった。ここでは一点だけ、二人の同時代作家の共通点を指摘しておきたい。
『オルタネート』は一本の筋道だった物語を形成しない。三人の主人公の目的も関係性も、バラバラだ。ただし終盤の「祝祭」と題された章において、三人は共通の身振りを行うことによって、目には見えない連帯を結ぶ。その身振りは、二一世紀初頭の日本で生まれた流行語とも共鳴する。「そんなの関係ねぇ!」だ。
人はただ生きているだけで、さまざまな関係との接続を強いられる。人間関係もそうだし、道徳との関係もそうだ。常識やルールの名のもとに、あなたは、若者は、親は子供は、男は女はこうであれと突き付けてくる、世間の呪いもそう。それらを全て受け入れることは、無個性で代替可能な人間になることと同義だ。代わりのきかない自分自身になるために、人は「そんなの関係ねぇ!」と、さまざまな関係の中から切断すべきは何かを選ぶ必要があるのだ。つまり、青春小説にとって必要十分条件である、成長の瞬間が、『オルタネート』はクライマックスで三者三様の形で書き込まれている。
その視点を持って、宇佐見りんの『かか』と『推し、燃ゆ』を読んでみよう。すると、二作のクライマックスにはどちらも、主人公が他者に「そんなの関係ねぇ!」と言われる体験が置かれていることに気付く。そして、他者から切断される体験もまた自己の成長に繋がり得るのだということが、『かか』でも、それよりもずっと強い形で『推し、燃ゆ』においても記録されている。〈彼がその眼に押しとどめていた力を噴出させ、表舞台のことを忘れてはじめて何かを破壊しようとした瞬間が、一年半を飛び越えてあたしの体にみなぎっていると思う〉(『推し、燃ゆ』)。
その視点を持って、もう一度『オルタネート』を読んでみよう。「そんなの関係ねぇ!」と繰り出したのは三人の主人公だったが、その身振りを目撃した人物は多数存在する。その経験によって、彼らもまた変化している。成長している。〈幾多の「私」の物語だと思います〉とコメントした宇佐見りんが、数え上げようとした「私」の数は三人ではないし、物語の登場人物だけに留まらない。なぜなら「そんなの関係ねぇ!」を目撃したのは、この小説を読み進めてきた全ての人だからだ。
二人の同時代作家のこれからを、追いかけていきたい。そこで描かれるさまざまな身振りを目撃し、「私」の中身を作り変えていきたい。
(よしだ・だいすけ)
波 2021年1月号より
単行本刊行時掲載

どんなときも「食べる」―フード描写をめぐって―
「フード理論」の提唱者である菓子研究家の福田里香と、福田をして「フード作家」と言わしめた加藤シゲアキ。悲しい時でも人が食べるのはなぜ? フィクションに於けるフード描写の在り方とは? お互いに著作とラジオを通じて十年来のファンだった二人の、フードを巡る縦横無尽なダイアローグ。
ラジオ「タマフル」を通じて
加藤 初めまして。僕は大学生のころから「タマフル」(TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」)のリスナーでして、十年くらい前だったかな、福田さんが出演されたとき、「フード理論」のお話をされていたんですね。もう、その「フード理論」がまさに目からうろこで、とても興味深く聞いていました。『ゴロツキはいつも食卓を襲う』(太田出版)が出たときも夢中になって読みました。あれから時を経て『オルタネート』を執筆しましたが、少なからず影響を受けていると思います。
福田 それは光栄です。私ももともとリスナーだったんですよ。だから出演できて嬉しかったです。とはいえ人前で喋った経験なんてほとんどない、ただの素人だったので、今考えると無謀というかなんというか(笑)。
加藤 対談の機会をいただけたので、最近『ゴロツキはいつも食卓を襲う』を読み直したんですが、改めて読んで、これ怖い本だなと思いました。「スプーンをかき混ぜすぎるひとは、心に悩みを抱えている」とか「逃走劇は厨房を駆け抜ける」とか、記号的な料理の使い方をしている作品の、ある種ピックアップですよね。福田さんは淡々と書いていらっしゃいますが、書き手からしたら「これはもうパターン化されてるからね」「こういう表現からはこんな予定調和が生まれるよ」って教えられてる気がします。それと同時に「それをどう裏切るの?」と問いかけられている気分になりました。
福田 そんな風に読んでくださって嬉しいです。仰る通り、ある意味警告の気持ちを込めて書いたところもあります。みんな食べ物描写を読むことに無防備過ぎるよって。例えば宗教の教えや逸話には万人にわかりやすいから、フード描写が頻発します。
加藤 どういうことですか?
福田 キリストの血と肉はワインとパンで表現され、アダムとイヴの失楽園は林檎を食べたからとか。宗派によって戒律で食べてはダメな食物が厳密に決まっていたり、仏陀の教えにはスジャータの乳粥やうさぎの自己犠牲など食べ物にまつわる逸話が多い。食事をしない人間はいないから世界中どこで布教しても食に喩えると教えやすいというか、そのように工夫されていると昔から個人的にそう感じていて、考えようによってはちょっと怖いんです。
加藤 やっぱりそうなんですね。今回読み直したときに、僕も小説の中で記号的に料理を使っていたんじゃないかと心配になりました。書き上げた後で感じたのですが、料理を扱うってけっこう怖いことだったんだなって。
福田 そう、でも二律背反なんですが、装置として使うことは、すごく有効なことでもあります。アニメや映画、マンガ、小説でもそうだけど、登場人物は血肉が通った生きている人間ですと表現するのに食事シーンは有効な描写です。絶対使っちゃいけないとか、すべてがステレオタイプに見えるということもないですよ。
加藤 以前、又吉直樹さんと「家族が死ぬような悲しいことがあっても、人って食べてるよね」という話をしたことがあります。どんなに悲しくてもお腹が空くのって、ちょっと滑稽ですらありますよね。お葬式のあと、みんなでお寿司とか食べたりするじゃないですか。なんでそんなめでたそうなもの食べてるんだろうって不思議な気持ちになっていました。
福田 たしかに。漢字に「寿」入ってます。通夜振る舞いとか精進落としといって、お通夜やお葬式に来た人たちで食事をともにしたりしますね。
加藤 そう、それです。あの食事がずっと不思議だったんですけど、昨年うちの社長のジャニーが亡くなったときのお別れ会で、初めてその意味というか、意義がわかった気がしたんですよね。
福田 何があったんですか?
加藤 お葬式やって、火葬が終わって、初七日の法要を終えたあと、事務所に所属しているタレントとごく一部の親族の方で食事をしたんです。缶ビールとかチューハイで献杯をして、みんなでお寿司を食べました。その中で、ジャニーさんのエピソードを一人ずつ話していくという時間があったんですよ。その話が本当に面白いんですよね。ジャニーさん自体が面白いからというのもあるんですが、泣ける話だったり笑える話だったり、それぞれのタレントが持ってるジャニーさんのエピソードがいちいち面白くて。そのときはじめて、こうやってみんなで食事をしながら話すというのも、弔いの一つのかたちなんだなと思えました。
福田 素敵な時間ですね。ジャニーさんを囲んで、みんなで大皿から取り分けて食事をすることで腹の底を見せ合った感じですよね。
加藤 そう、同じ釜の飯を食うっていうやつですね。文字通り同じ釜の飯を食ってきた仲間と、社長の最期にみんなで食事をして、みんなで弔った、見送ったという実感がありました。
福田 本当に素敵なエピソードです。一緒に食事をすると不思議な一体感が生まれるんですよね。
加藤 小説の中で料理を使おうとすると、そういう悲しいときに食事をさせるシーンを書くのって難しいんです。悲しいのに食べてるのって変じゃない? と思ってどう書いたらいいか悩みます。僕は『オルタネート』の中で、ダイキが失恋したとき彼の好物のカルボナーラを食べさせてるんです。最近『ゴロツキはいつも食卓を襲う』を読み直したら、「失恋のヤケ食いはいつも好物」と書いてあって、無意識にそう書いていたと思って、なんだか身につまされるというか、福田さんから見透かされているみたいでドキッとしましたよ(笑)。
フード作家・加藤シゲアキ
福田 先ほど「タマフル」リスナーだったって仰っていましたが、加藤さんも「タマフル」に出演されていましたよね。実は私、加藤さんが出演された回をリアルタイムで聞いていたんです。その時に宇多丸さんが、加藤さんのデビュー作『ピンクとグレー』(KADOKAWA)は「章タイトルが全部飲み物」とご紹介されていて、それは読まねばと思ってすぐに書店で買いました。
加藤 嬉しいです。お互い「タマフル」を通じて知ったんですね(笑)。『ピンクとグレー』、最初は違う章タイトルだったんですよ。でも、それはちょっとわかりにくいという意見があったのと、小説の中で印象的に飲み物を使っていたということもあって変えたんです。
飲み物も面白いですよね。年齢とともに飲むものって変わるじゃないですか。二十歳になったらお酒が飲めるというのは分かりやすいですが、二十歳の人が飲むお酒と五十歳の人が飲むお酒は違うし、その時代で流行るものもあれば、個人的にやたらハマってずっと飲んでる飲み物とかもありますよね。
福田 なるほど。でも、章タイトル全部にしちゃうなんて、こんなに潔く書いてあるのを読んだのは『ピンクとグレー』が初めてでした。書きたい感情は同じでも、どういう風に書くか、その感情を表現するのに何を使うかで作家性が出ますよね。この章タイトルもそうですが、加藤さんは、食べ物を見たときに発想が湧く人なんだな、フード作家でもあるんだなって思いましたよ。
加藤 福田さんにフード作家と言っていただけるなんて光栄です。
福田 新刊の『オルタネート』にも、ほんとに料理がたくさん出てきて。読んでいてすごく楽しかったです。付箋をたくさんつけながら読みました。
加藤 嬉しいです。
福田 本当に面白く読みました。私、「食べ物のマンガが好きなんです」と言うと「食べ物のマンガって『美味しんぼ』とかでしょ?」って言われることが多いんですけど、『美味しんぼ』だけじゃないんですよね。羽海野チカさんの『3月のライオン』には食べ物がたくさん出てくるんですけど、あれは将棋マンガです。美内すずえさんの『ガラスの仮面』は女優を目指す少女たちの演劇マンガですが、よく読むとマヤと亜弓さまは、ほとんど食事演技で対決しています。食そのものを描いた物語より、下支えをしているのが食だという物語のほうが好きなんです。『オルタネート』も、小説の中に三つの柱があって、その中の一つは蓉が主人公の料理バトルの筋ですが、それだけじゃないですものね。
加藤 印象に残ったシーンはありましたか?
福田 凪津は一度めは桂田と、二度めは君園と一対一で同じ喫茶店で会うのですが、そのときの飲み物描写が秀逸です。三角形な三者の内面がふと顕現するんですよね。それから今回、作中の料理をいくつか再現させていただいたのですが、三浦くんが「とうもろこしのバターおにぎり」を欲しがる場面は、フード的に胸キュンだったので、作れてうれしかったです。あとやっぱり「ワンポーション」対決は読んでいてワクワクしました。モチーフは料理なんだけれど、加藤さんはそこに、何かに一生懸命に打ち込むこととか、十代特有の悩みとかを込めて書いていますよね。食べ物を使うことでいろんな感情を顕現させてる。フード的に奥行きを感じて、すごく面白かったです。
加藤 それはやっぱり僕が料理が好きだからなんだと思います。あと、食べるものって毎回変わるじゃないですか。食べるという行為自体は変わらないですが食べるものは一食ごとに変わる。何を食べるかを書くと、そこに意味を持たせることができる。僕自身が、どういうときに何を食べるか意識して生きてるというのもあると思うんですけど。そうだ、一つお伺いしたいことがあるんですが、「ステレオタイプフード」って、アップデートされていくものですか。
福田 『ゴロツキはいつも食卓を襲う』の中でほとんど網羅出来ていると思います。出版から八年経ちますが、付け加えたいものはないですね。
加藤 食べ物に対する扱いというのは普遍的なもので、あまり変わらないってことなんですね。
福田 変わらないんじゃないかしら。どんな時代でも、やっぱり食べてる人はいい人っぽく見えるし、食べ物を粗末に扱う人は悪い人に見える。みんなが食事している中でひとりだけ食べないヒトは正体不明者に見える。だからこそ、表現の中で、その通りの人ですって認識させる装置としてフードを使ってもいいし、逆に言えば、何も食べないけど実は腹に一物もない人ですというふうに展開してもいいと思います。
加藤 かなり応用が利く考え方ですよね。作家はもちろんですが、役者もちゃんと知っておいたほうがいい。作家としては後から読むとほんとひやひやしますが(笑)。
福田 書き手でもあり役者でもある加藤さんならではの視点ですね。加藤さんが『オルタネート』で書いた中でお気に入りのフードの描写はありますか?
加藤 えみくがイチジクで何を作るかというシーンは、えみくのキャラクターを表現するうえで上手に使えたかなと思っています。あと個人的には、もやしが『オルタネート』の中でお気に入りのフードです。自分で言うのも恥ずかしいですけど(笑)。
福田 凪津の家で出てくるもやしと、蓉の実家の和食屋で出てくるもやしですね。
加藤 そうです。一方の家庭では安い食材としてのもやし。一方の家では和食屋で、ひげ根を取って出すもやし。同じ食材でも家庭や料理の方法が違うだけで、全く別のものになるということが書けました。
井戸の深さ
福田 私は上京してきた人間なので東京を舞台にした青春ものが好きなんです。『花より男子』とか『有閑倶楽部』みたいな、絶対にありえない派手な東京の学園ものも好きなんですが、『オルタネート』で書かれているような、東京の普通の高校生の生活が描かれている物語も好きなんです。都会に生きる現代の高校生の機微みたいなものをとても丁寧に書かれていますよね。そこに「オルタネート」っていう新しいツールを上手に組み込んでて。アプリの名前「オルタネート」に込められた意味もすごく面白いです。
加藤 僕、ニコラ・テスラ(編集部注・セルビア系アメリカ人の科学者。テスラコイルの発明などが有名)がすごく好きなんです。エジソンとの電流戦争の話とか面白いですよね。雷な感じって運命っぽいし、なんかマッチングアプリ的だなと思いました。
福田 確かに。インターネットの世界での結びつきと運命的なものとどちらもイメージできますよね。
加藤 小説の中の「オルタネート」は、高校生限定で、安全が保証されてるサービスなんです。親とか国家とか、大人が推奨してるようなイメージ。でも、もしもそういうものだとしたら、やっぱり意志を持ってやらない人って出てきますよね。絶対に全員がやるわけではないだろうな、高校生なりにいろんなことを考えるだろうなっていうところがスタートでした。
福田 キャラクターとストーリーはどこから降りてくるんですか。
加藤 テレビの企画で最新のマッチングアプリ事情を取材したことがあるんです。そこで、マッチングアプリの賛否について議論というか、賛成と反対両方の意見を聞く機会があったんです。「オルタネート」っていう高校生限定のサービスが存在する世界で僕が高校生だったとして、僕はやらないタイプだなって思ったんですよね。だから、やらない子、めちゃくちゃハマる原理主義な子、やりたくてもやれない子、この三人を書きたいなと思いました。
福田 それぞれ蓉、凪津、尚志に当てはめたのはどうしてですか?
加藤 十代でそういうのに熱中するのは女の子かな、と思って凪津が最初に生まれました。「やらない子」は凪津との対比もできるから同性のほうがいいと思って蓉も女の子にしました。二人が女の子なので「やりたくてもやれない子」は男の子にしようと尚志のキャラクターを作りました。
福田 なるほど。蓉を料理部という設定にしたのは何か思いがあるんですか?
加藤 蓉みたいな「やらない子」は、他の何かに打ち込んでたほうがいいなと思って、部活に所属している設定にしました。日本一を目指すスポ根的な価値観で生きている高校生。部活って日本独特の文化だし、十代にしかない世界だし、ちょっと特殊ですよね。そういう世界を書いてみたいなと思ったのと、僕が料理が好きだったので、料理バトルを書いてみたいと思って料理部にしました。
福田 それで「ワンポーション」というフードバトルが生まれたんですね。現実の未来でも起こりそうな設定ですごく惹き込まれました。
加藤 高校生の料理コンテスト、結構あるんですよね。めちゃくちゃレベルの高い高校生も実際にいて面白いんですよ。そういう現実の企画もいろいろ調べましたし、料理本も資料として沢山読み込みました。
福田 『エスコフィエ』が参考文献にありましたね。コンスタントに小説を書き上げている加藤さんを見ていると、明らかに「職業・作家」だと感じます。書き始める前は、自分の中にある書きたい欲の井戸がどのくらい深いのか分らないじゃないですか。一冊書き上げたら気が済んだ、というお気持ちにはならなかったんですか?
加藤 『ピンクとグレー』を書き終えたときに、書店回りをしたんですよ。いろんな書店員さんが応援してくれたんですが、その中で「書き続けてくれないと応援できない」と言われたんです。
福田 それは、ちょっと背筋がピンとなりますね。
加藤 「書店が応援するということは売るということだから、書き続けてくれ」という意味だったんですけど、それを聞いて、書かなかったら「自称作家」とか「元作家」になってしまうなと意地になったところもあります。幸い、二作目に書きたいこともあったのですぐに取り掛かれました。
福田 加藤さんの井戸はとても深かったんですね。
加藤 そうかもしれません。でも、書くことの井戸というよりは、書くことを知るための井戸というか、好奇心が異常に強いんだと思います。書くためにはいろんなことを知らなきゃいけないんですよね。『オルタネート』でいうと料理とかドラムとか、いろんな景色を知らなきゃいけないんですが、僕は幸いにもタレントという立場でお仕事させてもらう中で、いろんな経験ができるんです。どの仕事も全部小説の種になるというのはとてもありがたいことだと思っています。二作目に書いた小説はカメラがモチーフの一つなんですが、僕がカメラが趣味だったので小説にできました。結局、好きなものを小説にしているだけなんですよね。
福田 加藤さんはそれが普通だと思っているかもしれないけど、そうじゃない人ばかりですよ(笑)。ほとんどの人にとって、趣味はあくまで趣味なんです。そこから物語を生み出せる人なんて尋常じゃないです。興味があるもの、好きなものを物語に転化するって、すごいことです。
加藤 そうなんでしょうか……。でも突き詰めたら、僕はやっぱり「タマフル」のおかげだと思っています。
福田 いや私もヘビーリスナーでしたが小説は書けませんよ。「タマフル」を聞いていて、小説を書こうと思ったんですか?
加藤 そうです。小説を書こうと思ったときに、宇多丸さんのラジオの映画評論を聞いてきた中で知ったことがベースになったんです。こういうときに人は面白いと思うんだっていうことは「タマフル」で学びました。例えばデビュー作の『ピンクとグレー』は、「タマフル」で知った「(500)日のサマー」の構造を参考にすることで書きあげられたんです。何を書くかは自身の芸能の経験だったり、料理の経験や興味ですが、物語にできたのは宇多丸さんの映画評論のおかげなんです。
書くこと、演じること
福田 私、役者としての加藤さんの演技で好きなのがテレビドラマの「金田一耕助」シリーズなんです。
加藤 え、本当ですか。ありがとうございます。
福田 石坂浩二さんが演じてらしたころ、封切りで映画を見に行っていた世代ですが、加藤さんが演じる金田一耕助もとても素敵です。あの髪型、ばっちり似合ってます。ドラマでは加藤さんで15代目、金田一は代々いろいろな俳優さんが演じるという特異なキャラクターですが、歴代の俳優さんの中で本格的に小説を書かれる方はいないです。金田一という横溝正史の超有名な愛されキャラを演じながら、一方でご自身の小説の中でも架空のキャラクターを作り上げていますよね。どういうお気持ちになりますか?
加藤 金田一耕助は、本当にいろいろな方が演じてこられたから演じるのは正直とても難しいですね。いまだに本当に悩みます。一方で、横溝正史の小説を読み返すと、映像で見る金田一とはまた違うエンターテインメントなんですよね。文体がポップというか、アクロバティックというか。ミステリーを書くならこういうものが書きたいと思わせる小説です。
福田 書いてみたいって思われるんですね。そんなことを考える俳優はいませんよ。すごく稀有な感覚だと思います。
加藤 そうですね。演じるときは、映像作品の中の一つのキャラクターなので、この監督の世界で自分がどう役を表現できるかということを考えます。でも小説を読むと、いや僕ならここはこう書くな、ということを考えちゃいますね。横溝正史に言うなんて恐れ多いですけどね(笑)。
福田 最近ホームズもので盛んなパスティーシュならアリでは? 加藤シゲアキ版金田一、読んでみたいです。ところで、金田一って、すごくよく食べますよね。
加藤 食べますね。金田一が飄々としたキャラクターだというのを表現するためだと思うんですが、映像の中でも食べるシーンがすごく多いんですよ。芋を口に突っ込まれたりとか、事件が起きても、走る前にとりあえず一口食べてから動くとか。マイペースで、何かを食べながらでも死体を見れそうな、ちょっと変わったキャラクターを表現するための装置として使われていますね。
福田 テレビに出るときや役者さんのときの加藤さんは何かしらのキャラクター=性格を演じていて、小説を書くときにパーソナリティ=人格が出るのかなと思いました。
加藤 そうですね、書いているときは自分の人格や人間性がどうしても出ちゃいます。自分のことをしゃべるよりも、自分の本を読まれることのほうが、自分のキャラクターがばれてしまう気がします。
福田 深いです。でも読者がつくということは、その加藤さんの個性が愛されてるってことですよね。
加藤 最近は、その境界線が少しずつなくなってきたような気もします。『ピンクとグレー』を書いたときは小説家を演じながら書いてたんです。あまり正しくないのかもしれないですけど、小説家役をやっているようなイメージでした。
福田 小説家を憑依させてる感じですか?
加藤 そんなにかっこいいものでもないんですけど(笑)。小説家はきっとこんな格好で書くだろうとか、そんな感じですね。でも書いているうちに、登場人物を演じながら書くような感覚になってきたんです。だから、ちょっと変ですけど、蓉を書いているときは、蓉を演じながら、凪津のときは凪津を演じながら書いてるんです。三人称ではありますけど、蓉の視線で景色が浮かんでたりするんですよね。僕にとって、この先も書くことと演じることはそんなに遠くない感じがしています。
(ふくだ・りか 菓子研究家)
(かとう・しげあき アイドル・小説家)
小説新潮 2020年12月号より
単行本刊行時掲載
「運命」と「その先」の物語を描きたかった。
高校生限定のマッチングアプリ「オルタネート」が必須となった現代。東京のとある高校を舞台に、若者たちの運命が、鮮やかに加速していく――。新しいけど、普遍的。そんな、著者の新境地を開く最新長編がついに刊行。作品にかけた思いを聞いた。
――長編第六作となる『オルタネート』は、加藤さんにとって初となる小説誌での連載でした。初回が掲載された「小説新潮」2020年1月号は、創刊六三年の歴史において初の重版に。加藤シゲアキが文芸のど真ん中へやって来たぞ、という期待と応援の結果だったと思うんです。連載が決まった時のことや重版という反響のことなど、まず最初にお伺いできればと思います。
三作目の『Burn.』を出した時に、新潮社さんからご連絡をいただいたんです。デビュー作で終わりではなく、書き続けてきたからこそ信頼してもらえた、いただけたご縁だったと思うので、素直に嬉しかったですね。名だたる作品を生み出してきた出版社の雑誌なので、最初は緊張もあったかなと思うんですが、編集さんと打ち合わせて作品が具体的に走り出してからは気にならなくて。ただ、連載のことが発表になった時の周りのざわめきはすごかったです。ファンの人たちもとても喜んでくれました。若い子が小説誌を買っている光景って、なかなかないじゃないですか。若い子には歴史を動かすパワーがあるんだなと、実感させられました。
――作家とはアプリすらも開発してしまう生き物なのか、と驚いたんですが、物語の基幹部には、高校生限定のマッチングアプリ「オルタネート」が据え置かれています。主な舞台は、東京にある円明学園高校。オルタネートによって生じる出会いや別れ、運命に対するさまざまな態度を描いた青春群像劇です。着想のきっかけは?
まず最初に、編集さんから「『Burn.』みたいな青春群像劇」というお題をいただきました。同じ時期にたまたまレギュラーのバラエティ番組(「NEWSな2人」)で、マッチングアプリについて取り上げる機会があったんです。もう三年以上前なので今みたいにすごく流行っているわけではなかったんですが、そこで若者たちの意見を聞けたことが面白くて。いいという人もいれば、偏見を持ってしまう人たちもいたんですよね。マッチングアプリを前にした時に生じる思いや価値観が、人によってぜんぜん違う。これを真ん中に持ってくれば、物語が生まれやすいんじゃないかと思いました。それまで恋愛モノをやってこなかったから、ここで一回やってみるのもアリだぞ、と。ましてや高校生ってアンバランスなところがあるというか、振れ幅が極端じゃないですか。ちょっとしたことで深刻に落ち込んじゃうし、元気にもなるし、昨日までノーだったことが今日はイエスになる。一〇代後半の子たちの物事に一喜一憂していく感覚は、こういう題材を描くうえで合っているなと思いました。もし大人たちを主人公にしたら、もっと肉体的にドロドロなものになる(笑)。「運命の相手ってなんなんだ?」みたいな、価値観のドロドロが描きたかったんです。
――まさに価値観が乱立していますよね。しかも章ごとに視点人物が変わる形式なので、読者はそれぞれの内面を追体験し、個々の価値観に納得しながら読み進めていくことになります。
いろんな価値観を出さないと、オルタネートというものが見えてこない。少なくとも三人ぐらいは主人公が欲しいかなぁと考えて、オルタネートに対する距離感で三人の人格を作っていきました。やりたくない人、めっちゃやりたい人、やりたくてもやれない人、ですね。
――調理部部長で、ある出来事から人付き合いが苦手になった三年生の新見蓉。オルタネートを信仰し、「運命の相手」との出会いを待つ一年生の伴凪津。学年的には二年生ですが、大阪の高校を中退しオルタネートにアクセスできなくなったことに苛立つ、楤丘尚志。
基本的な設定だけ決めて、ストーリーをどうするかはあえて事前に固めなかったんです。まずオルタネートが生活必需品みたいになっている高校生の社会があって、三人のキャラクターがいて、それぞれが物語の中で走っていく姿をどんどん書き留めていった。蓉に関しては「ワンポーション」という料理バトルの大会に出る、それを書くことは決まっていたんですが、他の二人は行き先を決めていませんでしたね。その結果何が起こったかって言うと、三つの小説を同時に書いている感覚になりました。三人とも、性格が真っ直ぐなんですよ。真っ直ぐすぎて、なかなか三人が交錯しない(笑)。もうちょっとクロスするかなと思ったんですが、話が全然絡まなくて終盤までドキドキしました。
――三本のラインがギリギリまで一本に交わらなかった分、物語の熱量は増幅し続けましたよね。三人の周囲にいる人物も個性を放っていますし、みんながそれぞれの事情で、パートナーを探している状況にある。恋愛に限定されない関係性が無数に描かれています。
マッチングアプリの話なので、三人のキャラクターたちが誰と出会うか、出会った人からどう影響を受けるのかは、丁寧に書いていかなければと思っていました。全員そうなんですが、出会った人のせいで、自分がブレるんですよね。そうなった時に、元に戻そうとするのか、変わろうとするのか。どちらが正しいということはなくて、本人がいかにストレスなく「自分」を生きるか、ということが大事だなと思うんです。「運命の出会い」とか、「自分ではコントロールできないような影響力を持った出会い」って、確かにあるなぁと思うんですよ。そこで相手の方に一歩踏み出すか、踏み出した後でどう自分をコントロールするかというところが、生きていくということだと思う。いろんな出会いを、自分にとっていいものにどう変えていくのか。だから、出会うことが大事なんじゃなくて、出会った後が大事。運命は、それ以上のことはしてくれないんですよね。
――「運命の出会い」と聞くと、なんとなくいいもののように感じますが、実はそれまでの自分だとか人生のレールを変えてしまうものでもある。その怖さが、物語にさまざまな形で溶かし込まれていると思います。
僕の中にそういう感覚があるから、そういう書き方になるんだと思います。特に恋愛に関する部分はそうで、自分が変わってしまうんじゃないか、というのが僕は怖いんですよ。でも、変化していくことは悪いことではないとも思っている。……自分のセンチメンタルでロマンティックなところがどうしても出ちゃいましたね(笑)。
アイドルとしての活動で得た感覚をフィクションに変換
――『オルタネート』は遺伝学、園芸、料理、音楽そしてルッキズムなど、と盛りだくさんのアイデアが投入されています。恋愛がメインにはなっているんだけれども、ストーリーは一本道ではなく、サブストーリーが縦横無尽に走っている。この小説のどこが好きでどう楽しんだかという読者の感想は、間違いなくバラけると思うんですよ。この書き方の変化は、自覚的ですか?
『オルタネート』を書く前にこれまでの自分の作品を振り返ってみて、最後にどんでん返しが起こる話が多いなと気付いたんです。ちょうどその頃、読者として読んでいた小説もどんでん返しのある作品で、正直あんまり面白くなかったんですね。最後のどんでん返しはそれなりに面白かったんですが、そこまでの過程が退屈で「この最後だけで許されると思うなよ!」という気持ちになった(苦笑)。終わり良ければすべて良しとは言うけれども、クライマックスの高揚感とかラストの驚きで勝負しているものって、それだけの良さになっていないか、そこに寄りかかってないかな、と。本を読むことの楽しさって、そこではないんじゃないか。「読んでいる時間がずっと楽しい」が、一番いいじゃないですか。これ、実はあんまりみんなやれてないんじゃないかと思ったんです。これまでの作品もそういうつもりで書いていたのですが、そのテーマに今一度向き合ってみよう、と。「結末なんかどうでもいいよね!」くらいの感覚で、序盤から終盤までずっと面白く読ませる。一個一個のシーンやエピソードや文章を磨き上げる、ということを意識したんです。
――青春小説というジャンルを引き受けるうえで、意識したことはありましたか? というのも、青春は誰もが通過している、あるいは真っ只中にいる季節だからこそ、それを小説にしようとすると「青春あるある」になりがちだと思うんです。『オルタネート』はそこが回避されている。一般的な青春小説は読み進めるうちに自分の記憶が蘇る、青春時代への回想が起こるんですが、『オルタネート』は自分の中にある価値観がざわめいて、新たな思弁が起こるんです。
自分の学生時代だとか、自分の体験に引き付けるというよりは、没入して欲しいなと思ったんです。架空のマッチングアプリが流行っている世界の、架空の高校に通っている感覚になってくれたらいいな、と。だから、それこそ「青春あるある」はなるべく使わない青春小説にしたいなと思っていました。ありがちなシーンって、あんまりないんじゃないかな。キャラクターの名前をキラキラネームっぽく、ちょっと虚構性を高くしたのも、現実から切断されるような効果があるかもと思ったからなんです。他に意識していたのは、例えば「イケメン」のような記号的な言葉でキャラ化をしないようにすること。使った方が瞬間的には伝わりやすいんだろうけど、そういうものに頼らないで書くほうが、小説自体は豊かになると思うんです。
――大人と違い物事に一喜一憂する一〇代の姿を、青春を、今もこんなにも生々しく書けるのはなぜなんでしょう。
高校生だった頃の記憶を引っぱり出した部分ももちろんあるんですが、アイドルとしての活動の中で得てきた感覚を、フィクションに変換したりしているんですよね。例えば、うちのグループはもともとメンバーが九人いたんですが、どんどん減っていって三人になりました。メンバーが抜けるたびに、話し合いをしてきたんです。自分たちはグループを続けるのか、続けるとしたら誰のために、なんのために活動するのか。そういう問いかけって、青春っぽいですよね。しかも、ありがたいことに歌番組に三人で出させていただいて、活動をまたイチからやり直すなんてめちゃめちゃ青春じゃないですか(笑)。大人だから三人ともちょっと照れくさいんですが、歌番組が終わった後に無意識でハイタッチしていたりする。手をパチンとした瞬間にそれに気が付いて、「俺たち青春してるなぁ」みたいに思うわけなんです。そういう時に、初めて歌番組に出た時の感覚が呼び起こされるんですよね。
――どうやらアイドルと作家の二足のわらじは、必然のようですね。
メンバーと別れた、苦しい、つらい。この気持ちを小説にして元を取ろう、みたいな流れもあります(笑)。アイドルって、自分という物語を見せるものだと思うんです。作家としてやっていることも一緒なんですよね。だから、自分の中では既に、二足のわらじではなくなっています。僕がやりたいのは、自分の人生を使って、魅力的な物語を作る、ということなんです。
聞き手 吉田大助
(かとう・しげあき アイドル、作家)
波 2020年12月号より
単行本刊行時掲載
著者プロフィール
加藤シゲアキ
カトウ・シゲアキ
1987(昭和62)年生れ、大阪府出身。青山学院大学法学部卒。NEWSのメンバーとして活動しながら、2012(平成24)年1月に『ピンクとグレー』で作家デビュー。その後もアイドルと作家活動を両立させ、2021(令和3)年『オルタネート』で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞。同作は直木賞候補にもなり話題を呼んだ。他の小説作品に『閃光スクランブル』『Burn.―バーン―』『傘をもたない蟻たちは』『チュベローズで待ってる AGE22・AGE32』、エッセイ集に『できることならスティードで』がある。