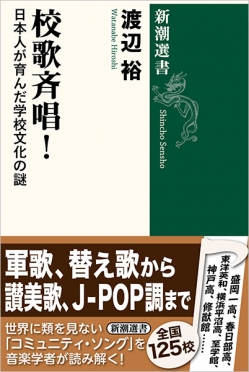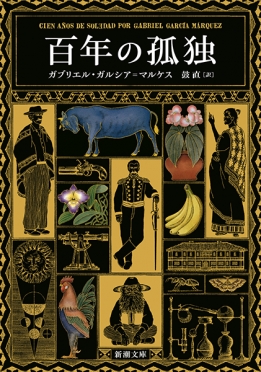思い出すこと
2,200円(税込)
発売日:2023/08/23
- 書籍
詩集か、エッセイか、あるいは小説か――。円熟の域に達したラヒリの文学的冒険にみちた最新作。
ローマの家具付きアパートの書き物机から、「ネリーナ」と署名のある詩の草稿が見つかった。インドとイギリスで幼少期を過ごし、イタリアとアメリカを行き来して暮らしていたらしい、この母・妻・娘の三役を担う女性は、ラヒリ自身にとてもよく似ていた。――イタリア語による詩とその解題からなる、もっとも自伝的な最新作。
伝記のための仮説
本文についての断り書き
訳者あとがき
書誌情報
| 読み仮名 | オモイダスコト |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |
| 装幀 | Still Life with Pomegranates,Sea Shells and a Beetle/Cover Painting、Giovanna Garzoni/painted、新潮社装幀室/デザイン |
| 発行形態 | 書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 224ページ |
| ISBN | 978-4-10-590190-5 |
| C-CODE | 0397 |
| 定価 | 2,200円 |
書評
宿命の紛失と再生
引越し先のローマのアパートには、古い書き物机が置かれていた。ラヒリは引き出しの奥に、詩のノートを発見する。表紙にボールペンで「ネリーナ」という女性の名前が記されている。引き出しにはノートとともに、三人の女性が写った写真がしまわれていた。真ん中の女性は、陽の加減で顔も表情も読み取ることができない。ネリーナとは彼女であろうと、ラヒリは直感する。
ネリーナとは一体どのような人物だったのか。ラヒリは、詩のノートをイタリア詩の研究家であるヴェルネに託す。ヴェルネによる解説を読み進めることで、物語は動き出す。
詩は、非常に個人的なものだ。ある物事について、散文で説明することはできるが、詩で説明することはできない。詩は、他者の理解を必ずしも必要とはしていない。他者に理解されることを意図しない心の声は、散文よりも詩の形に近くなる。
心に流れる電気信号を、誠実に掬い取った詩。詩のノートを点検していくことで、詩の書き手であるネリーナの、偽りのない生々しい部分に触れることができる。初めは探偵にでもなったような気分で、詩のノートをめくっている。
詩の面白さは、詩の語り手の声と、自分の声が重なるように共鳴し合う瞬間が生まれることだ。詩をつづるネリーナの声と、自分の声の境界が次第にぼやけていく。多くを語らずとも、親友と目をあわせて頷く、あの瞬間に起きる作用と似ている。この本を閉じる時には、ネリーナという心の友を得たような感覚すらあった。
「イタリア語しか話さない人には想像できない語彙の誤りが随所に見られる」という詩の特徴を、ヴェルネは指摘する。詩はイタリア語で書かれてはいるが、ネリーナはイタリア語を母語とする人間ではないということだ。さらに、生まれ育った家庭で使用されていた言語の他に、もう一つ言語を習得している形跡がみられる。つまりネリーナは、個人的な詩を書く言語として、自分の意思でイタリア語を選択していたのだった。
「紛失」は重要なテーマの一つだ。詩の中で繰り返される紛失。それに続く、死別、除去手術。これらを短絡的に「喪失」という言葉で一括りにしたくなるが、詩人ペソアの名詩をネリーナは引用する。「死は道の曲がり角/死ぬとは姿が見えなくなるだけのこと/耳を澄ませばおまえの足音が聞こえる/私が存在するように存在している」。ジュエリー、プレゼント、人形、美しい男の写真。紛失した物は姿が見えなくなるだけで、失われてはいない。それでも、紛失には戸惑いと悲しみが伴う。必死に紛失したものを探し出そうとするなかで、紛失物の代わりに、真実が浮かび上がってくる。
今でも自分を苦しめる、娘時代の思い出。それは、宿命的に避けることができなかった言語を象徴するものでもある。言語には、国という所属名がつきまとうものだ。ネリーナは言語の間で呆然としている。一人の女性として成熟し「今まで重ねてきた年を祝う」と顔をあげる一方で、空港の保安検査で「こうしてわたしは死者となる。/この詩の作者は存在しない。/かれらの決定により亡き者にされる。」と亡霊のように顔を失ってしまう。自分の顔がぼやけている写真を、机に大事にしまうという行為。詩のノートに貼りつけられた、身元不明の水死体が引き揚げられたという新聞記事。正体不明であるということが、ネリーナが感じている自分自身の正体なのだ。
一方で、イタリア語を使って遊ぶネリーナはどこまでも自由だ。「わたしの知らないうちに/待っていてくれる言葉を/くまなく探すこと。」という詩の言葉は、清々しい生きる希望に満ち溢れている。ネリーナは、宿命的に避けられなかった言語を故意に紛失するために、イタリア語を選び取ったのではないかという考えが浮かんでくる。娘時代の言語を道に置き去りにして、曲がり角の先にある新しい言葉に出会う。イタリア語との出会い、新しい言葉との出会いによって、ネリーナは自分の顔を見出そうとしている。
本作品は詩と小説を融合させた、ヴァース・ノベルと呼ぶこともできる。ただこの作品は、単なる文学的技巧の挑戦ではない。人の生(声)にどこまで誠実に向き合えるかに挑んだ、イタリア語を母語としないジュンパ・ラヒリの再生の物語だ。
(まーさ・なかむら 詩人)
波 2023年9月号より
単行本刊行時掲載
インタビュー/対談/エッセイ
探しまわること。見つけること。

ジュンパ・ラヒリの最新刊『思い出すこと』は、はじめての「詩集」。この本のなかでラヒリは、ネリーナという詩人、彼女を発見した作家の自分、作品を解説する文学研究者の三役を担っている。詩という形式を取ったもっとも自伝的なこのイタリア語作品をめぐるインタビュー。
聞き手:ナディア・コルヴィーノ
翻訳:中嶋浩郎
ジュンパ・ラヒリの最新作『思い出すこと』は、英語で創作活動を始め、何年も前からイタリア語でも創作を続けている彼女の初の詩集である。だが、ラヒリのイタリア語での活動はこれに留まらず、イタリア語の作品を英語に翻訳し(ドメニコ・スタルノーネの『靴ひも』など)、最近ではあまり知られていないイタリア人作家たちの短篇集の編纂も行っている。
新しい言語的な挑戦にも乗り出していて、『わたしのいるところ』の英語版では、作家と翻訳家の二つの役割を同時にこなしている。
『思い出すこと』でも、ラヒリはいくつかの役を同時に担っている。序文において、ラヒリはもっともらしい叙述の枠組みを創りだす。本書に収録されている詩は、ネリーナという無名の作者が机の引き出しに残していったノートに記されていたもので、ラヒリはローマのアパートでそれを見つけたというのだ。
従って、この枠組みのなかでラヒリは、編者であり、詩の作者ではない。だが、多くの詩のなかにラヒリ自身との類似点が見つかるのは明らかである。この文学的試みにおいて、注は余分なものではなく、作品の重要な構成要素となっていて、ラヒリは文芸評論家、言語学者としても登場しているのである。
詩集に収められた詩は、イタリアやイギリスの偉大な詩人の引用に、自然で奥深い日常的場面が結びついている。失くしたり見つかったりした品物、象徴的な過去の一瞬、遠い場所や近くの場所、亡くなった人、甘やかであると同時に痛みをともなう情緒的繋がりなどにしばしば焦点が当てられている。言葉の意味の意外なゲーム性に注目した詩や、行間に隠された意味を明らかにしてゆく注など、言葉遊びも多く見られる。
「イル・リブライオ」は作者にインタビューを行い、『思い出すこと』や現在の自身の文学的状況について語ってもらった。
――あなたはこれまで長篇小説、短篇集、エッセイを書いてきましたが、詩を書こうと思われたのはどんな理由からですか?
実際のところ、選択したわけではなく、これらの詩は自然に生まれてきたものなんです。わたしはこれまで英語の詩について学んできて、深い知識を得てはいましたが、英語ですら詩を書いたことがありませんでした。書くことがしばしば読んでいるものへの返答であるという意味で、読むことが書くことにつながったのです。このような方法で表現する能力が自分にあるとは思っていませんでした。『わたしのいるところ』の出版のためにローマにいたころ、詩という表現形式を取るようになり、それからこの道を歩みはじめました。
――「《Rovistare》探しまわる」という詩の注で、あなたは「紛失という主題をたどる作品の鍵となる言葉」と書いています。しかし、見つかった品物という別の赤い糸があり、それは紛失とは反対の発見というテーマを暗示しているように思えます。
失って見つかった物、これは一つの赤い糸です。それは『わたしのいるところ』にも、もっと細い形ですが存在していました。わたしにとって「探しまわる」ことと「見つける」ことは同じメダルの裏表です。探しまわる――一生懸命探す――行為は、つねに欠けているものとの対話関係にあります。それはわたしたちを失くした品物、あるいは一つの発見(ネリーナのノートが引き出しのなかを探したことで見つかったように)に導いてくれます。わたしにとって「探しまわる」という言葉はとても不思議な力をもっています。「再び出会う」というラテン語に由来するこの言葉が、わたしにとって書くことの出発点なのです。「探しまわる」意味に深く関わる「わたしたちが知らなければならないのは、一度見ただけでは物事を理解することはできず、二度見てようやくわかるということだ」というパヴェーゼの考察にわたしは強い印象を受けました。再び出会うことは「語義」の章のテーマでもあり、そこにはイタリア語の単語に注目し、べつの言語で自分自身に再び出会おうとする考えがあります。また、いくつかの詩はわたしがローマに移ってからの経験だけでなく、子ども時代や遠い過去に根ざしています。はるか遠い過去に遡るためにイタリア語を使ったということに衝撃を受けています。
――再び出会えましたか?
実際のところ、すべては試みです。ですが、新たなゴールに到達したとは思っています。新しい言葉、すなわちイタリア語の一部である詩の言葉を発見したのですから。このことによって、これまでは捉えられなかったことを掘り下げ、理解できるようになりました。真実に到達しようとする試みはつねに存在します。その意味で、この本は一つの試みなのです。すべてを語りつくすことは決してできませんから。何らかの方法である領域に触れたとしても、それは決定的なものではなく、当然またべつの本を書くことになります。記憶や経験はだんだん薄らぐもので、ずっと留めておくことは不可能です。
――ちょうどこの時期、あなたがイタリア語で書いた『わたしのいるところ』をご自分で英訳なさった本が出版されました。自作を翻訳するのはどんな経験でしたか?
大いに啓発されました。自分の本が変わる過程を体験したのですから。それから、翻訳することでもう一度イタリア語のテキストに立ち返ることができました。ある言語からべつの言語に移るたび、言語的な新たな変化と新たな認識が生まれるのです。翻訳するにはその本を深く掘り下げることが必要で、必然的に原文を整えたり推敲したりすることになりました。こうして、わたしはかつて歩いた道にもどって歩き直すことになったのです。それは、論評、序文、詩、注のある、この新しい本のテーマでもあると思います。
――詩人と監修者という二つの役割をこなし、自身の詩に注をつけるという選択は自分の作品を翻訳する経験と同一視できますか?
翻訳中、わたしはある錯覚に陥っていました。同じ人間でありながら、本に対して異なる態度を取ることを要求されているように感じていたのです。『思い出すこと』では自分ではないネリーナという詩人のオルター・エゴを、彼女のアイデンティティーの背後に隠れることなくつくりだしました。わたしは詩の監修者、注釈者でもあるので、実際そこには三つのアイデンティティーがあります。ある意味で『思い出すこと』は、わたしの近年の活動のすべてを含んでいるのです。『イタリア短篇集』を編纂した経験も役に立っています。
――詩のテーマにもどると、もう一つの重要な要素は、自然で奥深い日常生活です。それはあなたにとってどんな価値をもつものですか?
わたしにとって、奥深さのすべてがそこにあります。日常生活はつねにわたしが人生の意味を考えるための鍵でした。それはわたしの言語であり、多くの作家の言語です。とくに詩においては、日常生活への留意を表現することが可能です。過ぎていく一日、習慣、さほど重要でないように見えて、じつは生活の中心にある物。そうした物をわたしたちは使い、失い、求め、欲します。日常生活の行きつもどりつが、人生は一つの歩みであることをわからせてくれるのです。
――いまはあなたの作家生活にとってとても実り多い時期のようです。ほかのプロジェクトにも取りかかっていますか?
はい、パンデミックを除けば、とても充実していて、今年は仕事ばかりしています。近年、翻訳もはじめましたし。秋にはドメニコ・スタルノーネのConfidenza(信頼)の英訳が出ますし、来年にはもう一つわたしのイタリア語の作品、短篇集が出版されるはずです。あと、翻訳をテーマにしたエッセイを集めた英語の本をいま仕上げています。さらに、オウィディウスの『変身物語』のラテン語から英語への翻訳にも取りかかっています。同僚のラテン語学者といっしょにこのすばらしい山を登っているところです。このプロジェクトは長い時間と細心の注意を必要とします。ラテン語を勉強したのはずっと昔のことで、思い出さなければならないことが多く、たいへん刺激的です。毎日20~30節の詩句に取り組むことはとても楽しく、純粋で明確な注意を言葉に向けることができています。このところたくさんのことを経験したので、これからなにが起こるか自分でもわかりません。
――パンデミックはあなたがいままで以上に実り多い活動をすることを可能にしましたが、テーマの面でも影響を受けるでしょうか?
それはなんとも言えません。まだ終わっていませんから。多くの親しい人が依然として厳しい状況のインドにいることもあり、完全に自由だとは感じられません。この時期経験してきたことすべてが、いい意味でも悪い意味でも人生を変えるのは間違いありませんが、たとえば、誕生や喪失のことを思います。わたしは今年、母を亡くしましたが、間もなく出る本のなかでは生きています。だからこそ、この作品のなかでの考察はとても重要な意味をもっています。わたしの創作に変化があるかどうかはわかりませんが、いま、自然との関係にますます感銘を受けるようになっています。それは決して失われることのないレベルであり、わたしはそのなかに自分自身を見出しています。詩はこのテーマを掘り下げるのを助けてくれるのではないでしょうか。
(2021.6.14)
LA POESIA È IL LINGUAGGIO DEL QUOTIDIANO
Published in Il Libraio.it
Jhumpa Lahiri interviewed by Nadia Corvino
Copyright © https://www.illibraio.it/
Permissions granted by Il Libraio.It
via Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
「新潮クレスト・ブックス 2023-2024」小冊子より
単行本刊行時掲載
短評
- ▼Martha Nakamura マーサ・ナカムラ
-
他者に理解されることを目的としない心の声は、散文よりも詩の形に近くなる。ラヒリが古い机の奥から発見したのは、詩を書き綴ったノートだった。注釈を読み進めることで物語は展開していく。身元不明の水死体に思いを馳せる「顔の見えない」ネリーナ。曲がり角の先に待ち受ける新しい言葉に手を伸ばし、過去の宿命的な言葉を故意に喪失する。そうして、ネリーナは自分の顔を認識していく。単なるヴァース・ノベル(詩と小説の融合)ではなく、どこまで誠実に生に触れることができるかに挑んだ、生(声)への挑戦である。
- ▼succedeoggi スッチェーデオッジ
-
まず英語、次いでイタリア語による散文を長く創作してきたジュンパ・ラヒリが到達した詩は、濃密な内容とよく磨かれたスタイルで、すでに円熟の域に達している。『思い出すこと』は、ラヒリをよく知る読者にとっては新たなデビューとも言えるもので、彼女にとってのいくつかの重要なテーマが詩という形式のなかに姿を変えて現れている。
- ▼Avvenire アッヴェニーレ紙
-
バフチンは他人の視点に積極的に関与するために、自身の判断を停止して他人の視点でものを見る方法について語っている。自伝と芸術的創作のあいだにある本書では、この特別な叙述テクニックが使われている。
著者プロフィール
ジュンパ・ラヒリ
Lahiri,Jhumpa
1967年、ロンドン生まれ。両親ともコルカタ出身のベンガル人。2歳で渡米。コロンビア大学、ボストン大学大学院を経て、1999年「病気の通訳」でO・ヘンリー賞、同作収録の『停電の夜に』でピュリツァー賞、PEN/ヘミングウェイ賞、ニューヨーカー新人賞ほか受賞。2003年、長篇小説『その名にちなんで』発表。2008年刊行の『見知らぬ場所』でフランク・オコナー国際短篇賞を受賞。2013年、長篇小説『低地』を発表。家族とともにローマに移住し、イタリア語での創作を開始。2015年、エッセイ『ベつの言葉で』、2018年、長篇小説『わたしのいるところ』を発表。2022年からコロンビア大学で教鞭を執る。
中嶋浩郎
ナカジマ・ヒロオ
1951年、松本生まれ。東京大学教育学部卒業。フィレンツェ大学留学。長年、フィレンツェ大学で講師を務め、2023年8月現在広島在住。著書に『フィレンツェ、職人通り』『図説メディチ家』、訳書にジュンパ・ラヒリ『べつの言葉で』『わたしのいるところ』、ミレーナ・アグス『祖母の手帖』、『ルネサンスの画家ポントルモの日記』、ステファノ・ベンニ『聖女チェレステ団の悪童』など。