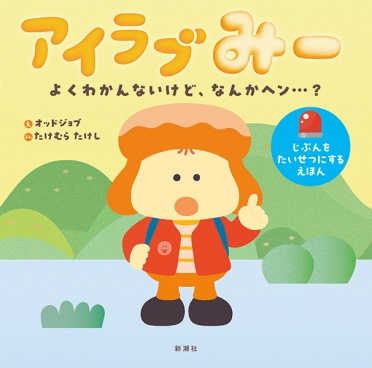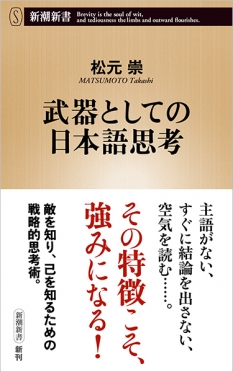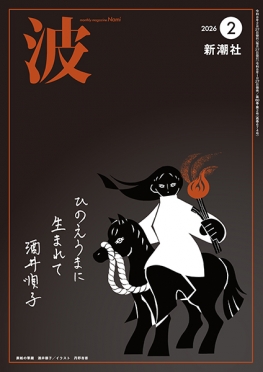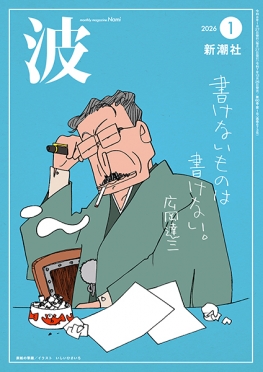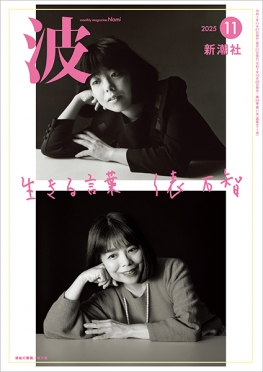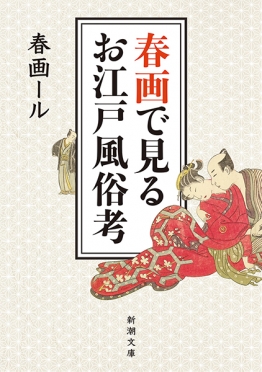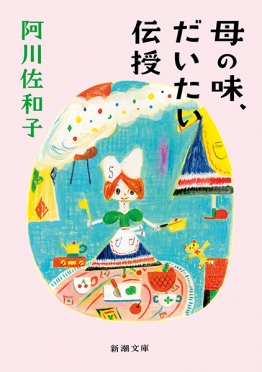今月の表紙の筆蹟は、酒井順子さん。
波 2026年2月号
(毎月27日発売)
| 発売日 | 2026/01/27 |
|---|---|
| JANコード | 4912068230267 |
| 定価 | 100円(税込) |
【筒井康隆スペシャル シリーズ第31回】
[掌篇小説]筒井康隆/両誅剣玄輔
[老耄美食日記]筒井康隆/ふたたび美食放浪
阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第101回
酒井順子『ひのえうまに生まれて─300年の呪いを解く─』
奥山景布子/女性史の「栞」になった丙午
町田 康『朝鮮漂流』
戌井昭人/漂流と交流
【今野 敏『分水─隠蔽捜査11─』刊行記念】
[インタビュー]棚瀬 誠/捜査現場と小説が結ぶ「旧」と「新」
川越宗一『絢爛の法』
大石 眞/素材にしにくい人物を小説化する妙味
ミヒャエル・ケンペ、森内 薫 訳『ライプニッツの輝ける7日間』(新潮クレスト・ブックス)
森田真生/徹底的な「接近」でライプニッツの謎に迫る
望月諒子『踊る男』
寺地はるな/平凡な異常さ
渡辺京二『私の明治時代史』(新潮選書)
三砂ちづる/歴史的人物への理解を深める人間類型と逸話
「芸術新潮」2月号 大特集「攻殻機動隊 深化する電脳世界」
「芸術新潮」編集部/現実感を増す近未来風景の魅力
【内田若希『意味ある敗北とは何か─アドラー心理学で読み解くトップアスリートの言葉─』刊行記念】
[対談]国枝慎吾×内田若希/階段を一段上がるのは勝利のときばかりじゃない
【新連載】
シリ・ハストヴェット、柴田元幸 訳/ゴースト・ストーリーズ
【エッセイ】
バッキー井上/京都、裏寺。酒場の老スパイの告白。
【私の好きな新潮文庫】
草刈民代/踊ること、生きること
メリメ、堀口大學 訳『カルメン』
泉 鏡花『歌行燈・高野聖』
平松洋子『筋肉と脂肪 身体の声をきく』
【今月の新潮文庫】
角田光代『ゆうべの食卓』
森 絵都/多彩で自由な人間関係のレシピ
【コラム】
小澤 實/俳句と職業
[とんぼの本]編集室だより
和田秀樹『死ぬまで元気―88の読むサプリ―』(新潮新書)
和田秀樹/「がまん」はやめよう
【連載】
椎名 誠/こんな友だちがいた 第18回
梨木香歩/猫ヤナギ芽ぶく 第24回
古市憲寿/絶対に挫折しない教養入門 第6回
中村うさぎ/老後破産の女王 第23回
高木 徹/東京裁判 11人の判事たち 第3回
下重暁子/九十歳、それがどうした 第9回
大木 毅/錯誤の波濤 海軍士官たちの太平洋戦争 第11回
【明治安田企画広告】
リレー連載「もしも、エピローグ・レターがあったなら……」 第二回
五木寛之/風俗の表層から時代の地底へ
編輯後記 いま話題の本 2月に出る本 編集長から
立ち読み
編集長から
今月の表紙の筆蹟は、酒井順子さん。
◎今年の映画初めは「プラハの春 不屈のラジオ報道」。民主化の進むチェコにソ連軍が侵攻し、ラジオ局の技師トマーシュは厄介な立場に追い込まれて……。やはりプラハの春が背景にあるクンデラ『存在の耐えられない軽さ』の主人公も同じ名前でした。そしてこの二人は、それぞれの物語の後半である同じ行為をします。尤も映画の主人公の名にあの小説の影響があったかどうか。トマーシュはチェコではありふれた男の名だから、彼が平均的なチェコ人であることを示したかっただけかもしれません。
◎吉田修一さんの『国宝』に出てくる女形の大物の名は小野川万菊(映画版で演じたのは田中泯)。既に指摘されている通り、三島由紀夫の短篇「女方」の主人公は一字違いの佐野川万菊で、共に中村歌右衛門をモデルにしているようです。三島の描いた新劇青年に恋する女形が老いて吉田版の化物の如き名女形になったかと思うと趣き深いですが、これは偶然の一致?
◎さらに小池真理子さんの最新作『ウロボロスの環』は、主人公高階俊輔の名が三島『禁色』の檜俊輔から来た気配濃厚。高階は檜同様、自分が仕組んだ恋の企みによって自滅していきます。やがてその破綻した恋の果てに、題名で示唆されている「永遠の繰り返し」が浮かび上がってくるのが何とも感動的。小池さんはエピグラフに『存在の耐えられない軽さ』の一節を掲げていますが、クンデラがあの長篇小説で依拠したニーチェの永劫回帰とも、三島の『豊饒の海』四部作の輪廻転生(とその頓挫)とも違った、甘美で、無常で、妙な具合に力強い考え方が展開されます。大江健三郎『懐かしい年への手紙』末尾と並ぶ、〈時間の円環〉をめぐる最高に美しいヴィジョン。
▽次号の刊行は二月二十七日です。
お知らせ
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。
創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。
創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。
現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。
これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。