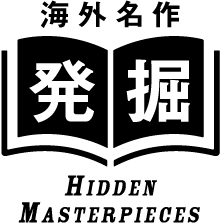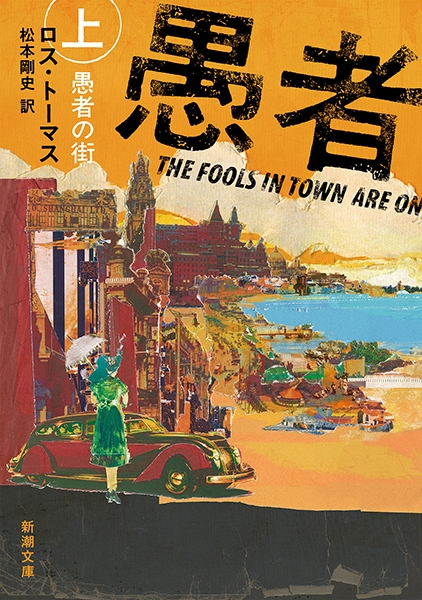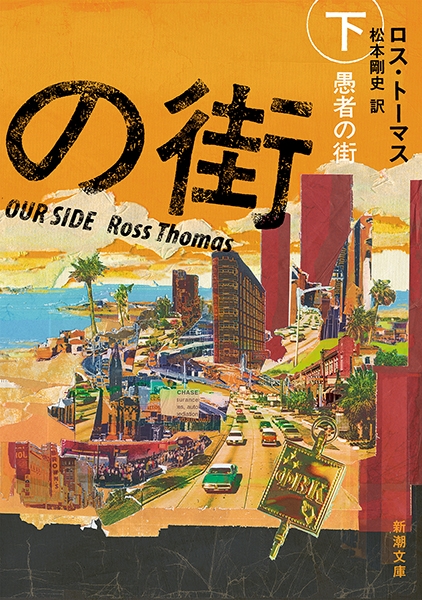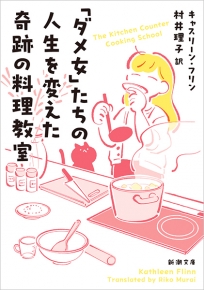
『「ダメ女」たちの人生を変えた奇跡の料理教室』を刊行しました。単行本が刊行された際に話題になった一冊が、満を持しての文庫化です。
マイクロソフトなどで長年キャリアを築いてきたものの、ある日突然失業し、36歳にしてパリの名門料理学校に入学したという異色の経歴を持つ著者キャスリーン・フリンが、料理とうまく付き合うことのできない10人の女性たちとともに食事を作りながら、それぞれが「自分らしい料理との付き合い方」を見出していく物語です。
ともに料理を作った女性たちは十人十色。彼氏と同棲中でマーガリンが大好きな23歳。息子が「肥満児なのに栄養不足」というバリキャリママ、4年前の冷凍鶏肉が捨てられないというバツイチ46歳、「料理好きの女子会に入れてもらえない」のが悩みの25歳。太りやすいのに料理は夫の担当でどうにもできないという26歳。みなそれぞれに悩みを抱えています。同じような思いを持っている女性は多いかもしれません。
そんな女性たちに、キャスリーンが送るメッセージはたったひとつ。「失敗したっていいじゃない。たかが1回の食事なんだもの。明日になったらまた作ればいい」。これです。キャスリーンと女性たちはさまざまな料理に挑戦しますが、焦がしてしまっても、煮過ぎてしまっても、生焼けでも、味気なくても、いい。失敗したって、たかが一回の食事。そう思えば、また元気に台所に向かうことができるかもしれません。
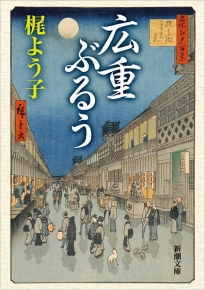
ゴッホにも影響を与え、北斎と並び日本を代表する絵師、歌川広重。「名所江戸百景」や「東海道五拾三次」の絵は、某お茶漬けの付録として見たことがある人も多いでしょう。
ただその人生は意外なほど知られていませんでした。そもそも、広重は武士の家の出で、侍から絵師にキャリアチェンジした人なのです。
もちろん江戸も今も、〈転職〉事情は甘くなく、最初はまったく売れない絵師でした。その広重が、どのようにブレイクし、なぜ「名所江戸百景」をライフワークとし、名実ともに日本美術史に名を刻印するまでになったのか。知られざる人生を生き生きと描く傑作です。新田次郎文学賞も受賞し、読み巧者を唸らせました。
さて、絵師になりたてのころ、人気を博していたのは葛飾北斎や歌川国貞でした。彼らの絵は発売と同時に飛ぶように売れ、売れることが地位を高め盤石にしていきます。いつの世も変わらないベストセラー作家の強さ。
それにひきかえ、広重の美人画や役者絵は、「色気がない」とか、「まるで似ていない」と酷評ばかりでした。今でいえば、星一つのレビューが、さらにマイナスの評価を生む最悪の循環。当然、絵は売れず、金もなく、鳴かず飛ばずの貧乏暮らしでしたが......。広重を支えたのは糟糠の妻、加代。世に認められず焦る広重をそばで見守り、夫の夢を信じていました。
追いつめられても、自分には絵を描くことしかないと切歯扼腕する広重は、ついにある色に出会います。それは、舶来の顔料「ベロ藍」。その藍色は、簡単に使いこなせる色ではありませんでしたが、しかし広重の胸は熱く高鳴ります。
――俺は描きたいんだ、江戸の空を、深くて艶やかなこの「青」で――。
無名の絵師が、やがて「東海道五拾三次」や「名所江戸百景」を描き、西洋画家たちを魅了する〈世界の広重〉になるまでを描く、意地と涙の物語です。
NHKBSプレミアム4KでTVドラマ化も決定。「広重」が面白い2024年の春です。
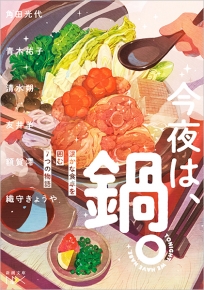
食卓を囲んで大勢でご馳走を食べる機会が制限されていた数年があったことで、この冬、あらためて特別な人たちと温かいお料理を囲むひとときの素晴らしさを実感した人も多いのではないでしょうか。寒い冬のご馳走といえば、ほっかほかの鍋♪ お肉、海鮮......何を食べるかもよりどりみどりですが、鍋は「誰と食べるか」もだいじな要素ですよね。そんな、大切な人たちと鍋を囲む冬の至高のひとときを描いた、アンソロジーが誕生しました。『今夜は、鍋。―温かな食卓を囲む7つの物語―』(新潮文庫nex刊)です。
角田光代の「餃子鍋」、青木祐子の「火鍋」、額賀澪の「牡蠣鍋」、織守きょうやの「やみ鍋」、清水朔の「水炊き」、友井羊の「鍋パ♪」 大人気作家たちによる"読む絶品鍋"を、あなたも、さあ召し上がれ。『飯テロ!』のもみじ真魚さんによる温かくて美味しそうなカバーイラストが目印です。
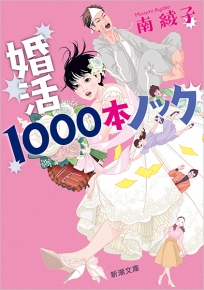
この物語の主人公はわたしである。わたしというのは名前のない登場人物の名前のかわりの「わたし」とかそういうややこしいやつじゃなくて、そのまま筆者のことである。筆者は一九八一(昭和五十六)年一月生まれ、職業は小説家一割アルバイト九割、独身、現在のところ結婚の見通しはまったくたっていない――
南綾子・著『婚活1000本ノック』はこんな書き出しで始まります。小説が「わたし」や「僕」といった一人称で書かれることはよくありますが、そうではなく、本作は著者の南さん自身の人生や経験を描いたものだと明言されています。
そうかと思うと2ページ先では、
さて、唐突だが、読者のみなさまは、"霊視体験"をしたことがおありだろうか。わたしはある。
と宣言し、以前に関係をもった男・山田が幽霊となって自分のもとに現れた日のことを語り始めます。山田は成仏するために、生前に誰かと交わした約束を果たさねばならず、南さんの「彼氏と温泉に行きたい」という願いを叶えるため、婚活の手伝いをすると申し出ます。こうして、南さんの「婚活1000本ノック」はスタートしました。
実話と言いながら「幽霊」。婚活成功が成仏への道。真面目なのかふざけているのか、この奇妙な構造と、南と山田の遠慮のない掛け合いが本書の大きな魅力です。
もう一つの魅力が、コミカルな文体と展開のなかに、「誰かと出会って、ともに生きる」ことへの真摯な渇望が描かれているところです。
「でもみんなちょっと不器用なの。ちょっと不器用っていうかさ、なんか変なこだわりがあったりさ、人づきあいが苦手だったりさ、空気が読めなかったりさ、髪の毛なかったりさ、そういうことがあってなかなかうまくいかないけど、でもみんな、誰かのことを好きになって、その人と結ばれて、幸せになりたいだけなんだよ」
第五話で南さんが泣きながらこう叫ぶ場面には心を揺さぶられずにはいられません。婚活経験の有無にかかわらず、思いきり笑って泣いて、気づけば他人事ではなくなっているような作品です。
そして本作は、1月17日(水)22時よりフジテレビ系にて連続ドラマ化が決定しました。南さん役は3時のヒロイン・福田麻貴さん、山田役はFANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征さん! 激しくて切ない婚活の行方を、小説でもドラマでもぜひ見届けていただけたら幸いです。
|
第1位 ミステリマガジン「ミステリが読みたい! 2024年版」ベスト・ランキング海外篇
第4位 宝島社「このミステリーがすごい! 2024年版」BEST 10 海外編
第7位 週刊文春「文春図書館 ミステリーベスト10」2024年版海外編
年末アンケートの結果発表の時期を迎えて、発表後半世紀の時を経てようやく翻訳紹介された小説が、海外ミステリーの読み巧者の方々に高く評価されました。その小説というのが、"プロが惚れこむプロ作家"ロス・トーマスが1970年に発表した第4作『愚者の街(The Fools in Town Are on Our Side)』です。
腐敗した南部の小さな街をさらに腐敗させ再興させるという、突拍子もない仕事の依頼を受けた元諜報員を主人公に据え、コンゲームに人間ドラマ、ハードボイルドにノワール小説といった、さまざまなジャンルの魅力を兼ねそなえ、さらに、先の読めない展開が待ち受けるという、小説好きにはたまらなく魅力的な犯罪エンターテインメント小説です。
『冷戦交換ゲーム』、『女刑事の死』といった作品で知られ、多くの作品がすでに邦訳紹介されていた著者のトーマスですが、初期の最高傑作との評判も多かったこの『愚者の街』は、これまでずっと邦訳紹介されずに陽の目を見ないままだったのでした。
新潮文庫の〈海外名作発掘〉シリーズは、このように、これまで邦訳紹介されなかった数々のエンターテインメント作品のなかから、海外作品を愛する読者の方々に喜んでいただけるようなものを見つけ出してこようという企画。
これまでに、ジャン=リュック・ゴダール監督による映画の原作小説『気狂いピエロ』(ライオネル・ホワイト著)、犯罪小説の巨匠ドナルド・E・ウェストレイクのスラプスティック・ミステリー『ギャンブラーが多すぎる』、ポール・オースターが別名義で発表したハードボイルド小説『スクイズ・プレー』(ポール・ベンジャミン著)、英国推理作家協会(CWA)第1回最優秀長篇賞を受賞したウィンストン・グレアムの『罪の壁』、Netflixオリジナル映画化作品の原作小説となったノワール怪作『悪魔はいつもそこに』(ドナルド・レイ・ポロック著)と、人気作家の未紹介作から知る人ぞ知る超絶マニアックなものまで取り揃えた、ユニークなラインナップを組み立ててきました。
シリーズでは、この『愚者の街』以外にも、フランソワ・トリュフォーが惚れ込み前述のゴダールに薦めて映画化が実現したという、ドロレス・ヒッチェンズによる原作小説『はなればなれに(Fools' Gold)』(1958年)が、本年度の「ミステリが読みたい!」で第11位に、「このミステリーがすごい!」でも第17位に、ランクインしました。これまたなんと60年以上も前に書かれた作品です。
面白い小説というのは色褪せない。少しでもその証左となったのなら、編集部としてこれほど嬉しいことはありません。シリーズの目印は、文庫オビにある〈海外名作発掘〉のロゴだけ。ぜひともこの目印を見つけて、その古びない魅力を堪能していただきたいものです。