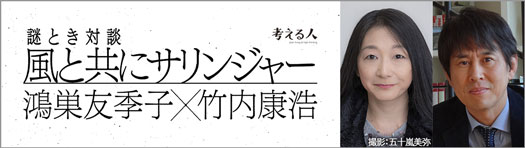謎とき『風と共に去りぬ』―矛盾と葛藤にみちた世界文学―
1,430円(税込)
発売日:2018/12/26
- 書籍
- 電子書籍あり
それは時代の先端にして、生まれながらの古典だった。
『風と共に去りぬ』は恋愛小説ではない。分裂と融和、衝突と和解、ボケとツッコミ――高度な文体戦略を駆使して描かれたのは、現代をも照射する壮大な矛盾のかたまり。全編を新たに訳した著者ならではの精緻なテクスト批評に、作者ミッチェルとその一族のたどってきた道のりも重ね合わせ、画期的「読み」を切りひらく。
『風と共に去りぬ』あらすじ
註
主要参考文献
謝辞
書誌情報
| 読み仮名 | ナゾトキカゼトトモニサリヌムジュントカットウニミチタセカイブンガク |
|---|---|
| シリーズ名 | 新潮選書 |
| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |
| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |
| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |
| 判型 | 四六判変型 |
| 頁数 | 288ページ |
| ISBN | 978-4-10-603835-8 |
| C-CODE | 0395 |
| ジャンル | 文芸作品、文芸作品 |
| 定価 | 1,430円 |
| 電子書籍 価格 | 1,430円 |
| 電子書籍 配信開始日 | 2019/06/14 |
書評
「通説」を覆す「全身翻訳家」の挑戦
「第二芸術論」で知られるフランス文学者の桑原武夫は、とんでもない研究者に出会ったときに「おもろい」という言葉を発したという。「頭がいい」でも「できる」でもなく「おもろい」。これが桑原の最上級の褒め言葉だった。哲学者・鷲田清一さんが何かの著書で紹介していたエピソードだ。
「頭がいい」や「できる」は既存のものさしで測られた評価でしかないが、「おもろい」というのは、これまでの通説やそれが依って立つ基盤そのものを揺るがし、場合によっては解体してしまうような兆候を感じとったときに発せられる言葉だ。鷲田さんにこのエピソードを教えてもらってはっきりしたのだが、私は「100分de名著」で講師を選ぶ際に、この「おもろい」があるかどうかを大事な選択基準にしているのである。
去年、この「おもろい」を心の中で何度も呟くような幸運に巡り会った。翻訳家・鴻巣友季子さんとの出会いである。
鴻巣さんの翻訳はJ・M・クッツェーの諸著作などで親しんでいた。どのような語りをされる人なのかという好奇心からトークショーに参加したのをよく覚えている。期待にたがわず、ビビッドな語り口で魅了された。確か、その感想をSNSでつぶやいたのをきっかけに、SNS上で鴻巣さんとのやりとりが始まったと記憶する。ぶしつけながら、鴻巣さんに、『風と共に去りぬ』の解説をお願いできないかメッセージをお送りしたところ、興味をもっていただき、お会いすることになった。
一抹の不安はあった。エンターテイメント感満載で、誰に教えられずとも読めてしまうこの本を、番組で解説する必要はあるのだろうか、と。
ところが、その懸念は鴻巣さんにお会いしていっぺんに吹き飛んだ。社員食堂でお茶を飲みながらの打ち合わせだったのだが、途中カップをもつ手が止まってしまった。「この小説、ディストピア小説としても読めるんですよ」「映画では全然目立たなかったメラニーがカギなんですよね、この小説って」「自由間接話法を使った高度な文体戦略がこの小説の面白さを支えているんですよ」等々と、読み解きのアイデアが鴻巣さんの口から次々に飛び出してきた。私はその間、ずっと心の中で「おもろい」という言葉を繰り返し呟いていた。まさに『風と共に去りぬ』を取り巻く通説ががらがらと音を立てて崩れさっていく、快感に満ちた時間だった。
鴻巣さんはご自身のことを「全身翻訳家」と呼んでいるが、全身で作品に没入し、最深部まで潜ってその細部を味わい尽くし、再び水面に浮上してきて、私たちが表面的にしか読めていなかった、作品の深部にある「宝物」を届けてくれる……私は、そんなイメージで鴻巣さんのお仕事を眺めている。鴻巣さんの近著『謎とき『風と共に去りぬ』―矛盾と葛藤にみちた世界文学―』や「100分de名著」での解説には、そんな「宝物」がたくさんちりばめられていた。
(あきみつ・よしひこ NHK「100分de名著」プロデューサー)
波 2019年5月号より
「し、知らなかった、なんですって!?」
翻訳家というのは、すごい仕事だと常々思っている。
小説家は、効果的な文体や語彙を選んで、自分の書く小説に命を吹き込もうとするものだ。完璧なプロットを仕上げてから執筆にかかる作家もある。でも、どんな作家でもある程度は、勘や直感を頼りに書いているものではないかと思う。
でも、翻訳家は違う。他人の文章を、己の勘で訳すわけにはいかない。どういう効果を狙ってその文体や語彙、そしてプロットを使ったのかはもとより、勘を頼りに書き上げた文章まで、その勘のよって来たるところを探り出して解明し、日本語に移し替える。訳す、というのはどうも、そういう作業らしい。「腑分け」という言葉が頭に浮かぶ。
本書は当代きっての翻訳家による見事なメス捌きを、手術室の上から眺めることができる、そんな印象の一冊だ。
とはいえ、無菌でひんやりした器具類の音が静謐な手術室に響くのではなく、そこではわくわくするようなドラマが、スリリングな考察が、ときに活きのいいユーモアとともに展開されている。
例えば、冒頭のスカーレット・オハラの外見。映画と違って小説では、いわゆる美人さんではない。そのくらいのことは、読者も小説の一行目を読んで知るのだけれど、実際、どういう容姿だったかまでは、さほど気にせず読んでいるのではないだろうか。
「背は低めで、吊り目で、スクエア・ジョー、首は猪首気味で(ふっくらし)、腕はむっちりしていて、バストは年齢にしては並外れて大きいが、ウエストは恐ろしく細く、脚が美しい。」
これは翻訳家がまとめてくれたスカーレットの容姿だが(スクエア・ジョーは、エラ張りっぽい顎のことだそう)、どちらかというとジョディ・フォスターのようなタイプをイメージさせるものではないか。そして、実際、スカーレットのコワモテぶりには、ヴィヴィアン・リーよりジョディ・フォスターのほうが、合ってるんじゃないだろうか(ジョディだとちょっと聡明すぎる感じもするが)。少なくとも作家は、ああいう雰囲気の外見を主人公に選んでいるのだ。
そして文体。これに関しては、やや挑発的ともとれるこんな文章に驚かされる。
「本作の文体は何に似ているかと問われれば、わたしは「ミッチェルと同時代の作家であれば、ある意味ではヴァージニア・ウルフ、時代をさかのぼれば、フローベールの『ボヴァリー夫人』ではないかと思う」と答えるだろう。」
「ミッチェルの文体には、語り手からある人物の内面へ、また別の人物の内面へと、視点のさり気なく微妙な移動があり、それに伴う声の“濃度”のきめ細かい変化、そして、間接話法から、自由間接話法、自由直接話法、直接話法に至るまでに、何段階ものグラデーションが存在している。」
のだという。
翻訳する人間が嫌でも気づかざるを得ない文体上の工夫は、読み手にはほとんど意識されずに来た。それは、「技法」や「文体」のことなど気にせず読んでほしいという作者の希望でもあり、同時代の先進的な手法も含め、あらゆる「技法」を、小説のおもしろさ、読むための推進力に奉仕させた作家の到達点であったというのが、とても興味深い。
いくつも読みどころはあるのだが、やはり注目したいのは「メラニー」だろうか。
ドクターストップがかかっているにもかかわらず、お堅いメラニーが、いかにして、そして誰の子供を妊娠したかに関する考察には、唸らされた。こう書くと、ややワイドショー的なトピックに聞こえるだろうけれども、アシュリをめぐる二人の女の三角関係(あるいはレットも含めた四角関係?)の物語とも読める小説のクライマックスは、メラニーが二度目の子供を妊娠し、そのせいで命を落とす場面だ。それまで長い、長い小説の中で緊張感を持って保たれてきた人物関係図が、ここでがらりと一変する。あの日、あの夜、いや、あの夜に至るまでの間、彼らに何があったのか! さあ、みなさん、もう一度読み直して、考えたくなるでしょう?
笑ったのは、「この主人公はいつも、いつも、「し、知らなかった、なんですって!?」と驚いている」という話。たしかに、冒頭からして彼女以外のすべての人にとって自明なアシュリとメラニーの婚約が、寝耳に水だったというところから始まる小説の中、何度スカーレットが「えっ?」と驚くかを数えるだけでも楽しそうだ。本書を案内役に、もう一度大作の迷宮に入り込みたくなる。
(なかじま・きょうこ 作家)
波 2019年1月号より
インタビュー/対談/エッセイ
神楽坂ブック倶楽部PRESENTS
『風と共に去りぬ』にツッコミまくる夜
「ツッコミどころ満載」な物語として常に読者の心をくすぐり続ける名作『風と共に去りぬ』。その新訳を手がけ、『謎とき「風と共に去りぬ」―矛盾と葛藤にみちた世界文学―』を上梓した鴻巣友季子さんと、『風共』を愛してやまない柚木麻子さん、そして峰なゆかさんによる超! 豪華トークイベントが開催されました。「風共愛」が炸裂した夜の模様をお届けします。
早過ぎた「イクメン」ウィル

鴻巣 語れることは山ほどあるんですが、まずは好きなキャラクターから始めてみましょうか。
峰 私が好きなキャラは、ど真ん中で申し訳ないですが、スカーレット・オハラ。私、主人公を好きになることはめったになくて、大抵は脇役が好きになるんですが、普通の主役っぽくないスカーレットにはすごく惹かれるんです。
柚木 私は『風と共に去りぬ』は基本的に「箱推し」で、メラニー・ウィルクスとスカーレットの関係性、カップリングを楽しむんです。でも最近気になってしょうがないのは、あれやこれやとスカーレットの世話を焼くマミーと髪型が面白いピティパットおばさん。中瀬ゆかりさん(新潮社出版部部長)がマミーの真似がめちゃめちゃ上手くて! 一緒にお酒を飲んでいて、店内が寒かったりすると、「お嬢さま、肩掛けを」って古典名作コントが始まるんですよ(笑)。あと、育児を始めてからは、イクメンとして使えそうなウィルもじわじわ来る。
鴻巣 スカーレットの右腕として農園の再建を支え、スカーレットの子どもの面倒もよくみるウィル・ベンティーン。いいですよね。私もウィル推しです。
柚木 彼と結婚すればよかったと毎日痛感しております!(←育児中)
鴻巣 あはは。私はもし今この作品を再び映画化するとしたら、ウィルは最前面に押し出されるキャラだと思います。とくにスカーレットとの隠微な関係性。上司と部下でもあり、姉と弟のようでもあり、でも二人とも独身で、「何よ、私との結婚を狙ってるの?」的なことを言ったりするような、非常においしい、贅沢な関係です。
柚木 「男女のBL」ですよ、うん。
峰 男女のBL……! なんかわかんないけどすごい……!!
鴻巣 たしかに! スカーレットはもう、男とみなしていいですよね。宝塚でもスカーレットは男役の方がやりますし。ウィルって実はイケメンでもあるんです。ちょっと赤みがかった髪に、野性味のある顔をしていて、戦争による傷で義足をつけているんですが、わらを噛みながら常に冷めた目で世の中を見つめている。生まれは貧しいんだけど気品があって、萌えどころ満載。
柚木 たぶん早過ぎたんですよ、彼は。2019年だったら一番人気でしょ。
鴻巣 なのに1939年公開の映画では存在ごとカットされるという扱い(笑)。
柚木 宝塚でもいないことになっているんです。
峰 あ、いないですね、そういえば。かわいそう!
鴻巣 私は黒人の使用人の娘プリシーが大好きなんですよ。訳していると、ミッチェルが気に入っていたことがよくわかります。どうでもいいようなことで、しょっちゅうスカーレットに引っぱたかれているんですが。『謎とき「風と共に去りぬ」―矛盾と葛藤にみちた世界文学―』を書くためにミッチェルの評伝を読んでいたら、プリシーがお気に入りと書いてあって、「やっぱりね」と。プリシーはスカーレットの一部なんです。嘘つき、見栄っぱり、いつも怒られている――、みんな共通してます。
アラサーちゃんはスカーレットか?

鴻巣 お二人は映画版はどう評価していますか? 小説と違う部分も多いですが。
柚木 原作が好きな人は映画にはハマらないかもしれませんが、配役はすごくいいと思います。なんといっても素晴らしいのはスカーレットのお母さんのエレン役の女優さんとメラニー役の女優さんが激似なところ! ここ太字でお願いします! スカーレットがなぜメラニーを嫌っているかというと、自分がなりたくてもなれないお母さまに似た、完璧な女だからですよね。
鴻巣 一種の〈代理戦争〉ですね。自分対母エレン。そして作者のミッチェル対ミッチェルのお母さんの代理戦争でもある。ミッチェルのお母さんも、エレンのように立派で、何でもできて、躾に厳しい人だったそうです。
柚木 峰さんの大傑作四コマ漫画の『アラサーちゃん』で、主人公のアラサーちゃんのお母さんが、アラサーちゃんのライバルであるゆるふわちゃんとすごく似てるっていうのも同じなのかなと思ったんですが。
鴻巣 『アラサーちゃん』の男女四人の主人公は、やっぱり『風と共に去りぬ』を意識しているんですか?
峰 それは以前にも編集さんに聞かれたことがあって。その時点ではまだ私、映画と宝塚版しか観ていなくて、そうなのかもと思った程度でしたが、その後小説を読んでみて、これは『アラサーちゃん』だと(笑)。それ以降はものすごく影響を受けています。この前も最終回を描くときに、『風共』を読み返して、ゆるふわちゃん=メラニーが死ねばいいのかな?と思ったり。
柚木 最後の方のゆるふわちゃんは確かに死亡フラグ立ってました(笑)。
鴻巣 オラオラ君がレットで、もちろんアラサーちゃんがスカーレット、文系くんがアシュリというのが本当にピッタリで。文系くんと結ばれるのは絶対無理だから!って読者は思うのに、アラサーちゃんは一途に好きなんですよね〜。
柚木 アシュリはまさに文系くんで、キザ野郎。アシュリが詩とか引用すると、スカーレットは何もわからないから「何言ってんだ、こいつ」状態で。私、ゆるふわちゃんが石田衣良さんの本が好きだというのを聞いた時の文系くんの反応が大好きなんです(笑)。
鴻巣 文系くんはボルヘス読みですからね。スカーレットとアシュリがあわや結ばれそうになる、有名な果樹園の場面では、アシュリに「メラニーはかつて南部が栄えていた頃の美しい過去を思い出させてくれる存在で、スカーレットは向き合わなければならない現実だから、君から目を背けたかったんだ」というようなことを滔々と語られますが、スカーレットは抽象論ダメだから、ちんぷんかんぷんになりますね。
柚木 めっちゃつまんなさそうに聞いてますよね。「そういうのいいんだけど。この話早く終わんないかな?」みたいな。
鴻巣 スカーレットは「二人でメキシコに逃げよう」と返す。話が具体的です。
柚木 具体的になっちゃうと、今度はアシュリのほうが「そういうことを言ってるんじゃないんだ。そういうのいやだな」ってなる(笑)。
峰 行けなくもない距離ですよね、メキシコ。現実主義者なんでしょうね。
柚木 介護や子育てから逃げたいというのも具体的だし。
鴻巣 でもそれはアシュリには伝わらない。結局「君にはまだ残っているものがある、それはこのタラ農園の土だ」なんてアシュリに丸め込まれて、妙に納得してしまう。スカーレットって、「お金」握ったときと「土」を握ったときだけ納得するんですよね(笑)。
ドキンちゃんはスカーレットがモデル

柚木 メラニーは、スカーレットを溺愛する「女オタ」という認識です、私。しかも「トップオタ」、TOですよ、完全に。
鴻巣 スカーレットのほうは当初「何よ、この女」としか思っていないけど、だんだんメラニーに対して尊敬の念が芽生えていきます。
柚木 私、メラニーがスカーレットを庇う時の言いっぷりが好きなんですよ〜。「推しに対するアンチのコメントを全部包んで撃ち返す!」みたいな。彼女は早過ぎたドルオタなんだと思うんです。
鴻巣 「メラニーがアシュリと結婚したのはスカーレットのそばにいたいから」というのが柚木説ですよね。スカーレットがその腹いせに、メラニーの兄と最初の結婚をする時も、メラニーは「今日から私たち、姉妹ね☆」って嬉しそうでした。
柚木 いわば、「推し」と家族になるみたいなことですから。オタにとってそんな名誉はないです。アシュリとメラニーが寝室に入っていくのを見てスカーレットがショックを受ける場面がありますが、メラニーの側はスカーレットが好きな男を介してスカーレットと間接的につながりたいと思っているんじゃないかと思うくらい。
鴻巣 よじれた欲望ですよね。メラニーはレットのことも最初から高く評価していますが……。
柚木 メラニー的には、レットはいわば「推しを任せられる男」です。メラニーがレットを評価しているのは、推しを大事にしてくれる人だからだと思います。
鴻巣 スカーレットって、寝室へ入っていくのを見るまで、メラニーとアシュリが夫婦だってはっきり認識できない。アシュリは自分のものみたいに思ってて。スカーレットのセクシュアリティ意識って本当に面白い。肉食なのにエロスが発達していないんです。「私のアシュリを取りやがって」とは思ってるけど、性的な面ではあんまり嫉妬してないんじゃないかと思う。
柚木 「アンパンマン」に「ドキンちゃん」っているじゃないですか。やなせたかし先生は、ドキンちゃんのモデルはスカーレット・オハラだと公言していて。だから瞳が緑で、頭が赤いんです。
鴻巣&峰 えー!?
柚木 ふふふ。ドキンちゃんはしょくぱんまんが大好きなんですが、しょくぱんまんはアシュリにあたるので、二人は絶対に結ばれないんです。そしてばいきんまんがレット・バトラーなんですよ! 「私はドキンちゃん」という歌があるんですけど、「なるべく楽しく暮らしたい/お金はたくさんあるのがいい/おいしいものを食べたいし/遊んで毎日暮らしたい/この世の終りがきたときも/私ひとりは生き残る」みたいな歌詞なんです。
鴻巣 スカーレット!
峰 完全に一致!!
柚木 もしアンパンマンに最終回があるとしたら、ばいきんまんはバイキン城の扉をあけて、「俺は行くぜ、君はしょくぱんまんのところに行けばいい」ってなるんじゃないかと思って心配です。
峰 泣けるー(笑)。
柚木 「しょくぱんまんは食品で、ドキンちゃんはバイ菌なので、結ばれることはないが、叶わない恋をすることだってある」とやなせ先生はおっしゃっているそうです(笑)。
鴻巣 世の中の色々なものが実は『風と共に去りぬ』をベースにしていて、それだけ影響を与えているということですね。
柚木 アンパンマンって大体、ドキンちゃんの「あれ欲しい」っていうところから話が始まるんです。
峰 私、子どもの頃からドキンちゃんが一番好きでした。
柚木 終盤の、アシュリたちが北軍に討入りをかけたものの負傷して、帰ってきたところに北軍の憲兵がやってきた場面がありますけど、そこでメラニーを中心に全員でとぼけた猿芝居をして難を逃れる場面では、スカーレットだけ何が起こっているのか最後まで分からない(笑)。
鴻巣 ヒロインにして常に蚊帳の外という稀有なキャラ。
柚木 アラサーちゃんもそうですよね。ヒロインだけど、企みみたいなところからいつも外れたところにいる。スカーレットはすごくモテて、男心が分かるはずなのに、どうしてこれだけ脈のないアシュリに告白して、「いける」と思い続けていられるんだろう?
鴻巣 アシュリは妄想の相手ですからね。
柚木 アシュリはスカーレットの肉体には興味があって、これも文系くんとアラサーちゃんの関係と同じ。
鴻巣 アシュリはスカーレットの魅力を表現するときに必ずbody=体という言葉を使ってほめるんです。
女性の「生き方小説」としての『風共』
柚木 作中で北軍の話が出るたびに、ちょうど同時代に『若草物語』の物語が起きてるんだなあと思うんです。
鴻巣 そう、ちょうど同じ時代です。
柚木 『若草物語』の女の子たちは職業婦人を目指して勉強していて、婦人参政権のことにも触れられています。彼女たちは北部(ニューイングランド)の人たちですが、アメリカってめちゃくちゃ広いんだなぁと思います。
鴻巣 かたや南部ではどうやって男を捕まえて生き残るかみたいなところもある。
柚木 『若草物語』では「私は
鴻巣 ヘレン・ケラーの生涯を描いた『奇跡の人』のサリバン先生も北部(マサチューセッツ)から来た人です。
柚木 独身でキャリアウーマンで、当時としてはとても珍しい存在ですよね。
鴻巣 『ジェーン・エア』もそうですが十九世紀の小説には「
柚木 スカーレットは、田嶋陽子さんが言うところの〈母の娘〉なんですよ。女の人には「父の娘」と「母の娘」、つまり男性主体で考える人と、女性主体で考える人がいるそうです。スカーレットはモテようとはしていても、いつも女性側に立って考える人です。荒廃した農園で空腹のあまり生の大根を齧って吐く場面なんか私大好きで。よっ、待ってましたっ! オハラ屋!って感じです。
鴻巣 誰も飢えさせないために、人を殺すし嘘もつく。盗みも働く。聖書で禁じられていることをすべてやります。
峰 私、屋敷を襲ってきた北軍兵士を殺す場面が一番好きなんですよ〜。
鴻巣 お母さまの形見の裁縫箱に手をかけた北軍兵士を撃つという、グロい描写ですよね。
峰 そのシーンでもスカーレットが口にする「明日考えよう」というセリフも、ポジティブな、いい意味だって捉えられていますけど――。
鴻巣 ちょっと違うんですよね。彼女にとっては、とにかく自分の身を守るための防衛本能なんです。
峰 ギリギリのね。
鴻巣 そう。一番最後の「Tomorrow is another day」もいい言葉として捉えられていますけれど。
峰 「スカーレット・オハラのように生きてみませんか」みたいな、女性の生き方の象徴のように捉えられていますが、そんないい意味じゃなくね?って思いますね。
柚木 私は「風共メイク」って呼んでいますが、そのへんにあるものをメイク道具にしちゃうテクニックがあると思うんです。それって究極の「時短」だなと思って。ほっぺをグーパンチして、ギューッとこすって、それでチークの代わりにするテクとか。
鴻巣 唇を噛んで赤くして、口紅を省略するなんてテクもありました。
峰 香水でうがいしてモンダミン代わりにしたり。
柚木 戦時下でも美人になるためなら使えるものは何でも使うという、究極の生命力。
峰 カーテンでドレスを作るのもそれかも。
鴻巣 農園の窮状を救うために、レットの前で羽振りの良さを装うシーンですね。でもスカーレットの手が「農民の手」だとレットに見破られてしまいます。アシュリには「このタコのある手はなんて尊いんだ、勲章だ」なんて言ってもらえる手が、レットには通用しない(笑)。
柚木 そのくせアシュリは、自分の手にタコがない(笑)。アシュリ! おまえはそういう男だよ! カーテンのドレスを着たスカーレットって、ほんといじらしいのに。
鴻巣 その後、タラを再建すると、本当に羽振りがよくなりますね。
柚木 後ろに男を従えて歩いたりして。ブルゾンちえみ感がすごい。
鴻巣 スカーレットってめちゃめちゃ算数ができるんですよ。学校の科目は何もかも得意じゃなかったけど、算術だけはできる。三桁ぐらいの数字が並んでいるのを暗算して「はい、じゃ、これぐらいの予算でどうですか」ってできちゃうから、どんどん顧客を引き抜けるんです。ミッチェルのお母さんがすごく数字に強い人だったみたいです。
不朽の「オープンエンディング」
柚木 メラニーが亡くなる時、そんなスカーレットを任せられるのはレット・バトラーだけになってしまいます。
峰 「トップオタ」の座をバトラーに譲って死んでいくという。
柚木 「TOの継承だ……ゲフッ……」みたいな感じ。推しに看取ってもらうなんて、最高のオタ人生ですよ。その後、妻を亡くしたアシュリはすっかり色褪せてしまうわけだけど。
鴻巣 そして、ようやくレットの愛に気がついたスカーレットが霧の中を無我夢中に走ります。このラストシーンは今までスカーレットが繰り返し見た夢の再現なんです。その夢の中では「いつかどこかに行き着けるかしら」と聞くと、レットが「行き着けるさ」って答えてくれて、ハッピーエンドのフラグになっていたはずなのに!
柚木 私たちは結末を知っていますが、まったく知らずに見た当時の人からすれば――。
鴻巣 「えぇー?」って感じですよね。当時はこういうオープンエンディングってまだあまりなかったから、「あのあと二人はどうなるんだ」っていう意見がミッチェルに殺到したそうです。
柚木 続篇を書いちゃう人がたくさんいたとか。この結末は二次創作したくなりますよ、本当に。スカーレット、この状況でよく「まだいける!」と思いますよね。レットがこんなに終わった感出してるのに。
鴻巣 最初のアシュリへの告白と同じですよ。「今気づいたの。あなたを愛しているわ」って、そう言えば誰でも戻ってくると思っている。
柚木 この人は最初から最後まで成長しなかったんですよ。もしも続篇があったとしても、これが繰り返されるってことでしょうか。
鴻巣 人としてはずいぶん成長したんだけど、恋愛の部分に関しては――。
峰 おぼこちゃん。
柚木 ほんとに、おぼこい……。
鴻巣 最後のレットの「I don’t give a damn」というセリフはずっと「君を恨みはしないよ」と訳されていたんです。本当は「I don’t care=知ったこっちゃない」っていう意味なんですけれど。これは訳としては間違っているんだけど、日本人の心には訴える表現だなあと思うんです。
柚木 ある意味、名訳ですよね。レットに捨てられて、希望がゼロになったところからの〜?
鴻巣 「私にはタラの土がある」!
峰 ポジティブすぎ(笑)。
柚木 希望ゼロの状況で、スカーレットのたった一つの特効薬、それが赤土! そう、私にはタラさえあればそれでいい! 土地こそがこの世で最後に行き着くところだ! 土地大好き!
鴻巣 スカーレットってこれだけ読者にツッコまれながら、最後には応援され愛されるんですよね。ほんとにミッチェルはキャラクターの描き方がうまいです。
(こうのす・ゆきこ 翻訳家・評論家)
(ゆずき・あさこ 小説家)
(みね・なゆか 漫画家)
波 2020年1月号より
関連コンテンツ
イベント/書店情報
キーワード
著者プロフィール
鴻巣友季子
コウノス・ユキコ
1963年、東京生れ。英米文学翻訳家。主な訳書にエミリー・ブロンテ『嵐が丘』、クッツェー『恥辱』、ウルフ『灯台へ』など。著書に『全身翻訳家』、『熟成する物語たち』。