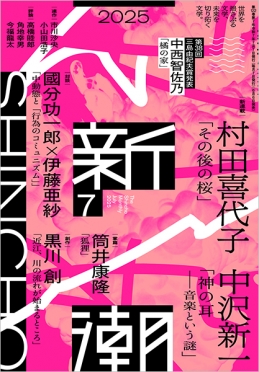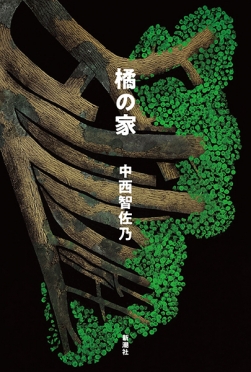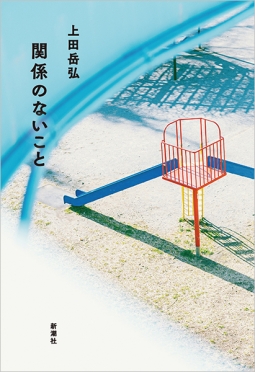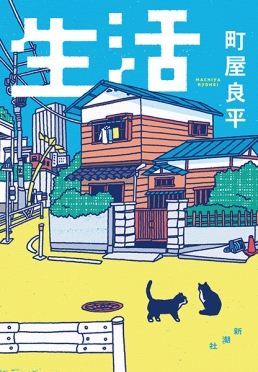◆作家生活50周年記念小説(短期集中掲載1) 臈たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ/大江健三郎
新潮 2007年6月号
(毎月7日発行)
| 発売日 | 2007/05/07 |
|---|---|
| JANコード | 4910049010679 |
| 定価 | 943円(税込) |
序章 なんだ君はこんなところにいるのか/
第一章 ミヒャエル・コールハース計画
追い詰めた奇妙な映画案が、唐突に姿を現した。
封印は、解かれるのか? 後期の仕事(レイター・ワーク)の新局面。
タタド/小池昌代
・カデナ(二)/池澤夏樹
・決壊(八)/平野啓一郎
・太陽を曳く馬(九)/高村 薫
・神器―浪漫的な航海の記録―(十八)/奥泉 光
・城砦(二十三)/加賀乙彦
・転換期の文学――『湖の南』をめぐって/富岡多惠子+辻井 喬
文学が歴史と人間を描く、その意味とは?
文化の二極解体を明かす衝撃的な問題提起
・苦難を越える明るい人/小川国夫
・別つことのできないもの/小栗康平
――プチ佐藤友哉論(「論」の上からバツ)
・脱「イジメ」としての脱構築/藤本一勇
・本にまつわるあれこれ/生田紗代
・ミシェル・ウエルベック『ある島の可能性』/岡田利規
・島本理生『大きな熊が来る前に、おやすみ。』/田中弥生
・ドナルド・キーン『渡辺崋山』/野口武彦
・いしいしんじ『みずうみ』/堀江敏幸
・明治の表象空間(十五)/松浦寿輝
・極薄の閾のうえを(十六)/磯崎 新
・〈記憶〉の中の源氏物語(三十四)/三田村雅子
編集長から
◎大江健三郎氏の作家生活のなかでも格別に重要な区切りをなす三部作小説『燃えあがる緑の木』の第一部で、14歳で命を終えようとしている少年に向け、年長者が励ましの言葉を贈る。「ほとんど永遠にちかいほど永い時に対してさ、限られた生命の私らが対抗しようとすれば、自分が深く経験した、一瞬よりはいくらか長く続く間の光景を頼りにするほかないのじゃないか?」。この一瞬とも永遠とも違う新しい時間を“発見”した大江氏の、小説家として生き続けた50年とは、いかなる時間なのだろうか。そう、「奇妙な仕事」でのデビューから今年5月で50年。本号より4回連続で、大江氏の長篇小説「臈たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ」を掲載する◎運河沿いの道を、老作家が知的な障害をもつ息子と歩いている。と、そのとき、背後から予期せぬ声が作家を不意打ちする。「なんだ、君はこんなところにいるのか?」。その一瞬のことだ、かつて禍々しい結果を残し、未遂に終わったはずの奇妙な映画案「ミヒャエル・コールハース計画」が30年ぶりに生々しく姿をあらわしたのは……◎区切りとしての、時の積層としての、一瞬よりはいくらか長く続く間の喜ばしい起点としての、大江氏の見事な後期の仕事(レイター・ワーク)に御注目いただきたい◎『湖の南』で大津事件(明治24年)を現在に召還した富岡多惠子氏。『父の肖像』で明治22年生まれの〈父〉の生涯を描き切った辻井喬氏。両者の対話から、今この瞬間もまさにそうであるような〈時代の転換期〉への深い考察が示された。近来最大の批評的事件というべき800頁を超える大著『文学環境論集』を上梓したばかりの東浩紀氏が仲俣暁生氏と、『東京から考える』(東氏と北田暁大氏との対談集)を契機に、ゼロ年代における都市・生・文化の本質的な変容を徹底討議した。
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
新潮とは?

文学の最前線はここにある!
人間の想像力を革新し続ける月刊誌。
■「新潮」とはどのような雑誌?
「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。
■革新し続ける文学の遺伝子
もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。
■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。































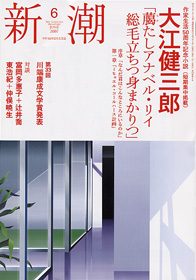
 公式X
公式X