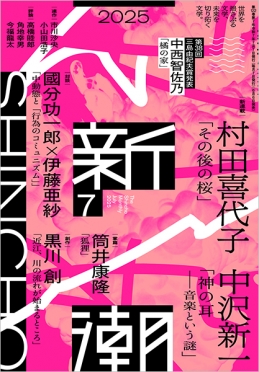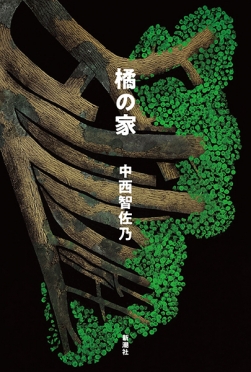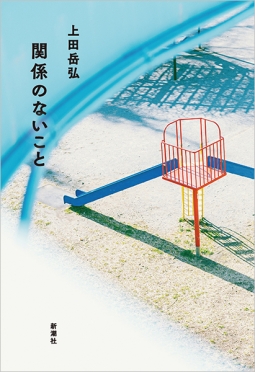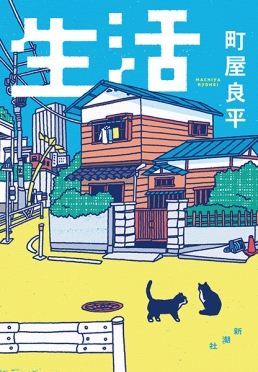日韓中・三文芸誌による文学プロジェクト 文學アジア3×2×4
新潮 2010年6月号
(毎月7日発行)
| 発売日 | 2010/05/07 |
|---|---|
| JANコード | 4910049010600 |
| 定価 | 特別定価1,047円(税込) |
文學アジア3×2×4 【第一回「都市」篇】
作家紹介/前田 塁
作家紹介/パク・ソンウォン
作家紹介/賀 紹俊
作家紹介/佐々木 敦
作家紹介/ジョン・ヨウル
作家紹介/賀 紹俊
・トモスイ/高樹のぶ子
・暴力論の消息/福田和也
・連続と不連続/安藤礼二
・おおきな人/別役 実
第二回 大陸の夢が編み出すウェブ
文明の外へ――P・ロック『捨て去ること』
・歌舞伎座の声/渡辺 保
・「ん」と日本人/山口謠司
・お座り/赤木和雄
・福田和也『アイポッドの後で、叙情詩を作ることは野蛮である。』/大澤信亮
・入江敦彦『イケズ花咲く古典文学』/小山太一
・村田沙耶香『星が吸う水』/斎藤 環
・黒井千次『高く手を振る日』/正津 勉
・古井由吉『やすらい花』/諏訪哲史
・岡田利規『エンジョイ・アワー・フリータイム』/古谷利裕
・空に梯子(五)/角田光代
・マザーズ(六)/金原ひとみ
・フィルムノワール/黒色影片(六)/矢作俊彦
・還れぬ家(十五)/佐伯一麦
・ネバーランド(十五)/藤野千夜
・幸福の森(三十)/加賀乙彦
・屋根裏プラハ(十)/田中長徳
・明治の表象空間(四十四)/松浦寿輝
編集長から
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
新潮とは?

文学の最前線はここにある!
人間の想像力を革新し続ける月刊誌。
■「新潮」とはどのような雑誌?
「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。
■革新し続ける文学の遺伝子
もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。
■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。































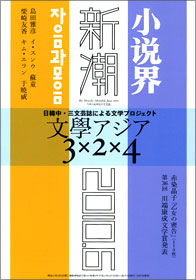
 公式X
公式X