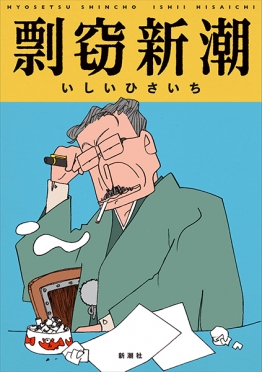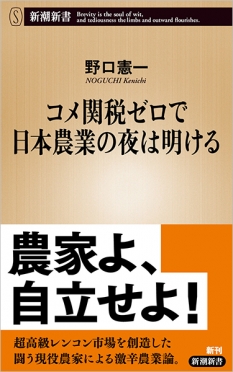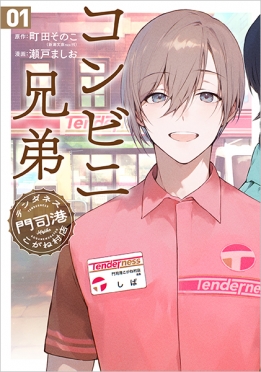新潮新書
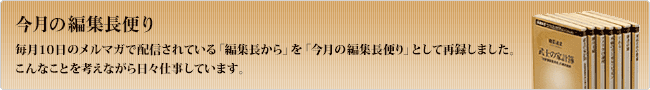
現代社会の変質を読み解く

先日、車のディーラーに行ったときのことです。新車で買って2年、まだ何年も走れることは言うまでもありませんが、案の定、乗り換えを勧められました。かつて車の買い替えメドはざっくり10年とか10万キロとかいわれたものですが、今やサブスクやリースが当たり前になり、大枚はたいても長く付き合う「愛車」イメージは年々薄れています。
『リキッド消費とは何か』(久保田進彦・著)では、若者から中高年まで、あらゆる世代に広がる消費行動の大変化──「高級車より今しかできない経験」「洋服は7回着たらゴミ箱行き」「自分に合う商品をコスパよく入手」──などを徹底分析。モノも情報も溢れかえる現代の消費は、何を新たな基準として、どのように変化しているのか。マーケティングの専門家が迫ります。
現代社会で行きかう情報はあまりに膨大、かつ素早く消費されるため、一つ一つ吟味することはとてもできません。そして、深刻なニュースや涙を誘う美談から、映画やマンガ、つい頬を緩めてしまう「ゆるキャラ」まで、そこには常に何らかの「意図」が隠されています。『プロパガンダの見抜き方』(烏賀陽弘道・著)は、前作『フェイクニュースの見分け方』に続いて、多くの具体例を取り上げながら、読者の「見抜く目」を養います。
『移民リスク』(三好範英・著)もまた、現代社会の水面下で広がるリスクに警鐘を鳴らします。川口・蕨市に集住するクルド人の犯罪や迷惑行為が注目を集めていますが、ヨーロッパの移民問題に精通する著者は、埼玉の現地を皮切りにクルド人の故郷トルコ、さらにメディアで批判されがちな入国管理局、規制に舵を切る"移民先進国"ドイツの現状をルポ。人権の名のもとに移民流入に手をこまねく「日本的ゆるさ」に警鐘を鳴らします。
一つの分野を長年探究してきた人にはそれだけの俯瞰と洞察があるものですが、『至高の近代建築─明治・大正・昭和 人と建物の物語─』(小川格・著)は、建築編集者歴じつに60年余におよぶ著者の最新刊。前著『日本の近代建築ベスト50』では、1960年代に隆盛を迎えた後期モダニズム建築を主にとりあげましたが、今回は、明治、大正、昭和戦前までの約80年間、欧米建築をひたすら模倣した時代からオリジナルを生みだす時代の32の現存建築を独特の視点で解説します。
『リキッド消費とは何か』(久保田進彦・著)では、若者から中高年まで、あらゆる世代に広がる消費行動の大変化──「高級車より今しかできない経験」「洋服は7回着たらゴミ箱行き」「自分に合う商品をコスパよく入手」──などを徹底分析。モノも情報も溢れかえる現代の消費は、何を新たな基準として、どのように変化しているのか。マーケティングの専門家が迫ります。
現代社会で行きかう情報はあまりに膨大、かつ素早く消費されるため、一つ一つ吟味することはとてもできません。そして、深刻なニュースや涙を誘う美談から、映画やマンガ、つい頬を緩めてしまう「ゆるキャラ」まで、そこには常に何らかの「意図」が隠されています。『プロパガンダの見抜き方』(烏賀陽弘道・著)は、前作『フェイクニュースの見分け方』に続いて、多くの具体例を取り上げながら、読者の「見抜く目」を養います。
『移民リスク』(三好範英・著)もまた、現代社会の水面下で広がるリスクに警鐘を鳴らします。川口・蕨市に集住するクルド人の犯罪や迷惑行為が注目を集めていますが、ヨーロッパの移民問題に精通する著者は、埼玉の現地を皮切りにクルド人の故郷トルコ、さらにメディアで批判されがちな入国管理局、規制に舵を切る"移民先進国"ドイツの現状をルポ。人権の名のもとに移民流入に手をこまねく「日本的ゆるさ」に警鐘を鳴らします。
一つの分野を長年探究してきた人にはそれだけの俯瞰と洞察があるものですが、『至高の近代建築─明治・大正・昭和 人と建物の物語─』(小川格・著)は、建築編集者歴じつに60年余におよぶ著者の最新刊。前著『日本の近代建築ベスト50』では、1960年代に隆盛を迎えた後期モダニズム建築を主にとりあげましたが、今回は、明治、大正、昭和戦前までの約80年間、欧米建築をひたすら模倣した時代からオリジナルを生みだす時代の32の現存建築を独特の視点で解説します。
2025/02