新潮新書
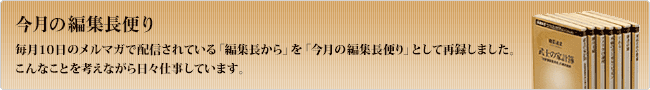
言葉・脳・記録・科学

4月は新社会人スタートの季節です。自分が入社した30数年前と比べて最大の違いは、やはりアナログからデジタルへの移行です。原稿用紙にエンピツ書きだった当時から、ワープロ、パソコン、スマホになり、文字は書くものから打つもの、タッチするものになり、コミュニケーションの主役は、対面や電話での会話からテキストでの交信へと大きく変わりました。それは今や社会全体に及び、効率性を高めている反面、ちょっとした言葉の誤解や相手の意図の取り違えなど、様々なマイナス面も現れるようになりました。
今月の新刊『生きる言葉』(俵万智・著)は、あらゆるデジタルツールがデ・ファクトになったいまの時代に、「普通の人が普通に使う書き言葉としての日本語」の足腰を鍛えるにはどうすればいいのか、自分の思いを誤解なく相手に届けるには何が大切なのか、言葉のプロフェッショナルが実体験をふまえて考えます。ネットやSNSから、恋愛、子育て、歌会、音楽、AIまで、言葉の飛びかう現場を通して見えてくるもの──言葉とは、人生をともに歩く頼もしい相棒です。
「すぐに気が散る」「計画が苦手」「人の話を聞かない」......その一方では「エネルギッシュ」「集中力がすごい」「発想が自由」「くよくよしない」など、ADHD(注意欠如・多動症)には普通の人とは異なる長所もあるといいます。『多動脳─ADHDの真実─』(アンデシュ・ハンセン・著、久山葉子・訳)は、『スマホ脳』をはじめ『ストレス脳』『最強脳―『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業―』などシリーズ累計120万部超のベストセラー最新作。ADHDだったモーツァルトやエジソンのような突出した才能はなぜ生まれるのか? 彼らが学校教育に不向きなのはなぜなのか? 人類史の中で「多動な脳」はなぜ綿々と生き残ってきたかを読み解きます。
春はプロ野球開幕の季節でもあります。『野球の記録で話したい』(広尾晃・著)は、長年、「野球の記録で話したい」と題するブログを運営する著者が、趣味と遊び心から「面白いデータ」ばかりを選び出して徹底考察します。王の868本塁打や金田の400勝のような通算記録、江夏の401奪三振や稲尾の42勝、イチローの210安打などのシーズン記録、ほとんど注目されることのない「守備記録」、ファームの記録、NPBとMLBの「実力差」のデータ分析、出身校や名前別に組んでみた「ベストナイン」などなど、野球が好きな人(だけ)は読むほどに楽しめる超マニアックな内容となっています。
『すごい科学論文』(池谷裕二・著)は、薬理学者の著者がふだん日課にしている「朝の科学論文百本ノック」、つまり、片っ端から世界中の最新論文に目を通す習慣から生まれた、お得に学べる万能理系コラム集です。医療から生物、科学、化学、AIまで、この世界の森羅万象に通じる75本のコラムは、長寿のヒントから生物のふしぎまでじつにバラエティ豊かです。本書に収録された数々の科学論文を通して見えてくる世界のありようは、今までとは少し違ってくるはずです。
今月の新刊『生きる言葉』(俵万智・著)は、あらゆるデジタルツールがデ・ファクトになったいまの時代に、「普通の人が普通に使う書き言葉としての日本語」の足腰を鍛えるにはどうすればいいのか、自分の思いを誤解なく相手に届けるには何が大切なのか、言葉のプロフェッショナルが実体験をふまえて考えます。ネットやSNSから、恋愛、子育て、歌会、音楽、AIまで、言葉の飛びかう現場を通して見えてくるもの──言葉とは、人生をともに歩く頼もしい相棒です。
「すぐに気が散る」「計画が苦手」「人の話を聞かない」......その一方では「エネルギッシュ」「集中力がすごい」「発想が自由」「くよくよしない」など、ADHD(注意欠如・多動症)には普通の人とは異なる長所もあるといいます。『多動脳─ADHDの真実─』(アンデシュ・ハンセン・著、久山葉子・訳)は、『スマホ脳』をはじめ『ストレス脳』『最強脳―『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業―』などシリーズ累計120万部超のベストセラー最新作。ADHDだったモーツァルトやエジソンのような突出した才能はなぜ生まれるのか? 彼らが学校教育に不向きなのはなぜなのか? 人類史の中で「多動な脳」はなぜ綿々と生き残ってきたかを読み解きます。
春はプロ野球開幕の季節でもあります。『野球の記録で話したい』(広尾晃・著)は、長年、「野球の記録で話したい」と題するブログを運営する著者が、趣味と遊び心から「面白いデータ」ばかりを選び出して徹底考察します。王の868本塁打や金田の400勝のような通算記録、江夏の401奪三振や稲尾の42勝、イチローの210安打などのシーズン記録、ほとんど注目されることのない「守備記録」、ファームの記録、NPBとMLBの「実力差」のデータ分析、出身校や名前別に組んでみた「ベストナイン」などなど、野球が好きな人(だけ)は読むほどに楽しめる超マニアックな内容となっています。
『すごい科学論文』(池谷裕二・著)は、薬理学者の著者がふだん日課にしている「朝の科学論文百本ノック」、つまり、片っ端から世界中の最新論文に目を通す習慣から生まれた、お得に学べる万能理系コラム集です。医療から生物、科学、化学、AIまで、この世界の森羅万象に通じる75本のコラムは、長寿のヒントから生物のふしぎまでじつにバラエティ豊かです。本書に収録された数々の科学論文を通して見えてくる世界のありようは、今までとは少し違ってくるはずです。
2025/04

































