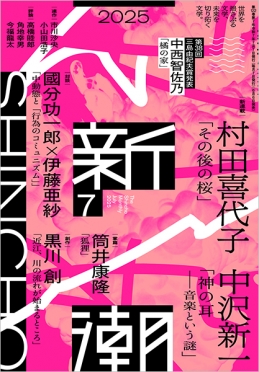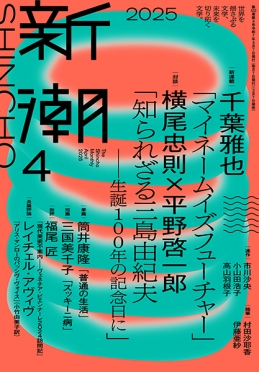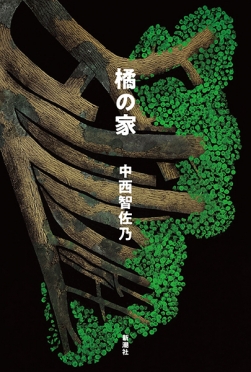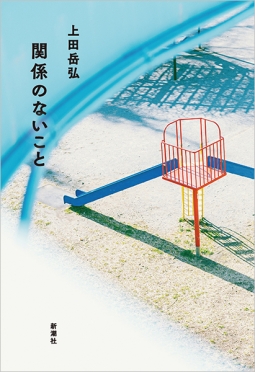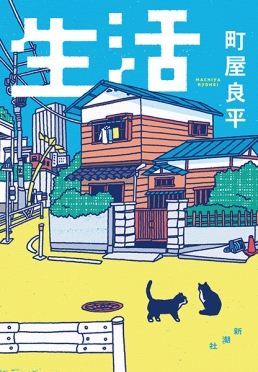第39回新潮新人賞発表
新潮 2007年11月号
(毎月7日発行)
| 発売日 | 2007/10/06 |
|---|---|
| JANコード | 4910049011171 |
| 定価 | 特別定価1,047円(税込) |
六年の財産【インタビュー】
十年の批評【記念原稿】
・カデナ(六)/池澤夏樹
・決壊(十三)/平野啓一郎
・太陽を曳く馬(十四)/高村 薫
・神器―浪漫的な航海の記録―(二十三)/奥泉 光
・城砦(二十八)/加賀乙彦
【受賞作】とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起/伊藤比呂美
【選評】入沢康夫 岡井隆 白石かずこ 高橋源一郎 平田俊子
文学の命としての「言葉」をいかに愛し、いかに畏れるか。世代を超えた対話。
・レディ・チャタレーの騎乗位/鹿島田真希
・飛ばない蝶、ふれあう甲虫/津村記久子
・ゾンビたちは歌を歌う/平倉 圭
・島本理生『あなたの呼吸が止まるまで』/岩宮恵子
・鹿島田真希『ピカルディーの三度』/田中弥生
・大西巨人『地獄篇三部作』/福永 信
・W・G・ゼーバルト『土星の環』/松永美穂
・マキノ雅弘(四)/山根貞男
・明治の表象空間(十九)/松浦寿輝
・〈記憶〉の中の源氏物語(三十八)/三田村雅子
編集長から
第39回新潮新人賞受賞作が高橋文樹氏「アウレリャーノがやってくる」(小説)と大澤信亮氏「宮澤賢治の暴力」(評論)に決定した。選考会場の空気は一見和やかだが、第一級の小説家、批評家が価値観を正面からぶつけ合うのだ。司会者は今年も極度に緊張し、祈るような思いで選考過程を見守った。新人にしては悪くない、といった議論は一切ない。選考委員が眼前の原稿に顕在する欠点に容赦をしないということは、潜在する未知の可能性に賭けるということとまったく同義なのだ。だから、「もしかすると高橋さんは、私などが考えるよりもっともっとスケールの大きな小説へ向かって、歩き出そうとしているのかもしれない」(小川洋子氏)、「この詩人の過激な平和主義が過激な暴力性と背中合わせになっているという謎にこだわり続けた、誠実な思考の軌跡である」(浅田彰氏)という「賭け」を担った二人の新人を送り出せることを心から喜びたい。
バックナンバー
雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。
雑誌から生まれた本
新潮とは?

文学の最前線はここにある!
人間の想像力を革新し続ける月刊誌。
■「新潮」とはどのような雑誌?
「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。
■革新し続ける文学の遺伝子
もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。
■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために
デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。
































 公式X
公式X