世界史は現代の鏡
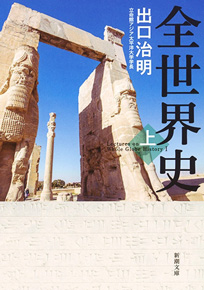 出口治明『全世界史 上巻』
出口治明『全世界史 上巻』
|
「全世界史」という言葉はちょっと聞き慣れないかもしれません。普通、歴史は東洋史とか西洋史という形で勉強しますし、書店でもそのように棚が作られています。しかし、本当に世界は東洋と西洋に分かれているのでしょうか? 本書にはそういう予断をいとも簡単に反証してしまう例が満載されています。
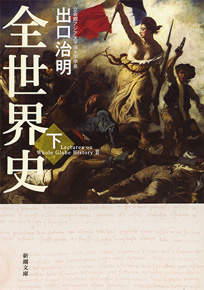 出口治明『全世界史 下巻』
出口治明『全世界史 下巻』
|
日本は海という自然の国境に囲まれていますが、よく考えてみれば、海は陸路に比べれば便利な「道路」なのです。トボトボ歩いていくよりも、風を上手に使えばどこまででも行くことができるからです。なにしろ平城京の住民は7割が外国人だったという説もあるくらいで、
つい頑張ってしまう人に贈りたい、新食感のごはん小説!
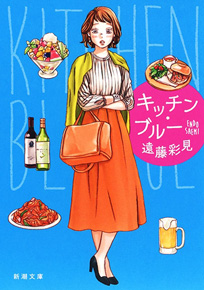 遠藤彩見『キッチン・ブルー』
遠藤彩見『キッチン・ブルー』
|
最初に収録された「食えない女」は、映像翻訳家の
弱点をなんとか克服しようとする灯の行動は、ユニークでいながら切実でもあり、思わず応援したくなります。「食欲も性欲と同じだ。隠したときに恥に変わる。コントロールできないことが醜いのだ。」と自分を責める灯の言葉が沁みる......。予想外の結末にも、驚くこと間違いなしです。
他にも、料理が下手すぎて新婚の夫に罪悪感と怒りを覚える沙代や、隣人の騒音のせいでストレス性の味覚障害に陥ってしまった希穂など、食に悩みを抱える主人公たちが登場します。タフにユーモラスに問題に立ち向かっていく様子がなんとも爽快です。いわゆる「飯テロ系小説」ではないのですが、美味しそうなお料理もたくさん出てきます。
食べることは生きること。夏バテに打ち勝つ元気が出てくる、絶品ごはん小説です。
「100年前のトランプ支持者」を描いた
アメリカ文学屈指の名作
アメリカ文学屈指の名作
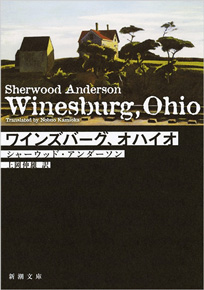 シャーウッド・アンダーソン 、上岡伸雄/訳『ワインズバーグ、オハイオ』
シャーウッド・アンダーソン 、上岡伸雄/訳『ワインズバーグ、オハイオ』
|
本書『ワインズバーグ、オハイオ』はそのルーツともいえる作品です。トランプが選出された大統領選からさかのぼること約百年、1919年に発表されたこの作品もまた、発展から取り残された人々の悲哀を描いています。1908年にT型フォードの製造が始まり、アメリカは農業国から一気に工業化へと舵を切りました。『風と共に去りぬ』でおなじみの、綿の花が揺れる田園風景は後退し、北部の工業地帯が賑やかになっていく時代。それはちょうどいま、シリコンバレーでIT産業が次々とビリオネア=億万長者を生み出す一方で、物作りや重工業に従事していた人々が置き去りになっている現在のアメリカとよく似た時代です。大きな変化についていけない人々に寄り添って書かれたのが、この『ワインズバーグ、オハイオ』なのです。
本書の巻末に収録された解説で、川本三郎さんはこう書いています。〈一見、平穏に見えるスモールタウン、ワインズバーグだが、「革命」「すさまじい変化」にさらされようとしている。変革期は人の心を揺さぶる。これまでの生活が壊されてゆく。時代の変化に付いてゆけなくなる。ワインズバーグの「いびつな者たち」の孤独、不安、疎外感の背景には、この十九世紀末にアメリカを襲った大きな変化がある。アンダーソンは、その変化を小さな町に暮す人々の心を通して、描くことに成功している〉
ワインズバーグは実際には存在しない、作者が創造した架空の町です。ひとつの町を舞台とし、そこに住む人々を描きながら、町全体を主役にした連作短篇という形式は、後続の作家たちに大きな影響を与えました。山本周五郎の名作『青べか物語』、宮本輝さんの『夢見通りの人々』、佐藤泰志さん『海炭市叙景』、川上弘美さん『どこから行っても遠い町』などなど、例に事欠きません。
アメリカ文学史上では、土着的なマーク・トウェインから、フォークナーやヘミングウェイらモダニズムの作家たちへの橋渡しをしたと見做されているこの『ワインズバーグ、オハイオ』、いまこの現代にこそ読む価値がありそうです。



































