映画キャストサイン入り原作本、図書カードをプレゼント! 映画公開記念「私の日日是好日」Instagramキャンペーン開催中!
雨の日は、雨を聴く。雪の日は、雪を見る。夏には、暑さを、冬には、身の切れるような寒さを味わう。五感で季節を味わえば、「毎日がよい日」......。森下典子さんの『日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ―』(新潮文庫)が映画化され、10月13日に公開されます。原作&映画のプロモーションの一環として、8月1日から「私の日日是好日」Instagramキャンペーンがスタートしました。
「気持ちよく晴れた日には、お気に入りのランチバッグに『茶碗』や『建水』に見立てた100均の器を詰め込んで、カジュアルな野点を愉しんでます」「いつもはバスにゆられる通勤路をぶらり歩いてみたら、路傍に見事なアジサイを発見!」......などなど、みなさんが実践している、あるいは体験した「私の日日是好日」を、ぜひ、素敵な写真で投稿してください。
キャンペーンに参加してくださった方の中から抽選で、映画キャストサイン入り原作本を5名に、新潮文庫特製図書カード3000円分を10名にプレゼントします。投稿の際には、公式Instagramをフォローして、ハッシュタグも忘れずにつけてくださいね!
[→]詳しくはこちら
乃南アサさんの新たな代表作 戦争を考える夏にしよう
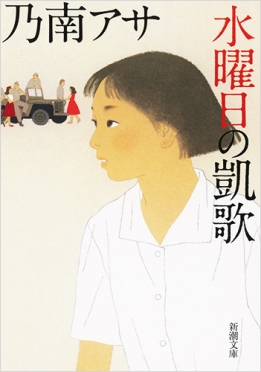 乃南アサ『水曜日の凱歌』
乃南アサ『水曜日の凱歌』
|
進駐軍が上陸し、性暴力被害が広がることを怖れた日本政府は、敗戦から二日後の閣議後すぐに、当時の警視総監に対し、「日本の娘を守ってくれ」という依頼をします。警視総監は阿吽の呼吸ですぐさま東京料理飲食業組合の役員を呼びつけ、「特殊慰安施設協会」(通称RAA)の設立を指示。設立声明では「狂瀾を阻む防波堤を築き、民族の純血を百年の彼方に護持培養すると共に、戦後社会秩序の根本に、見えざる地下の柱たらんとす」(「RAA協会沿革誌」国会図書館蔵)と謳い、進駐軍を相手にする慰安婦を集めた慰安所を作ることが決まったのです。
「日本人慰安婦」がいた――。現代に生きるわれわれにとっては、直視しにくい現実です。鈴子は、英語が少し話せた母親がこの特殊慰安施設協会で通訳として働くことになったのにともない、進駐軍の相手をする慰安婦たちと寝起きをともにし、その苛酷な生活を誰よりも間近で見ることになります。集められた慰安婦たちは大部屋をカーテンなどで仕切っただけの場所で、一日に何十人もの米兵の相手をさせられたそうです。劣悪な環境で精神に異常を来す女性が続出し、鉄道に飛び込んだり、首を吊って命を絶った女性もいたといいます。「敗戦」という厳しい現実を、これほど厳しく突きつけられる環境はありません。
しかし、なぜ本書のタイトルは、勝利を意味する「凱歌」なのでしょうか。それは読んでのお楽しみですが、ヒントをひとつだけ。本書の解説は朝日新聞の書評委員でもある評論家・斎藤美奈子さんにお願いしましたが、こう書いています。
「戦争の犠牲になるのは女性と子どもだ、といわれます。しかし、『水曜日の凱歌』に登場する女たちはみな、それぞれのやりかたで戦っている。重い題材にもかかわらず、本書が心地よい読後感を残すのは、そのためでしょう。思えば乃南アサはデビューした当時から、戦う女を描いてきた作家です。直木賞を受賞した『凍える牙』(1996年)で初登場した音道貴子も、パワハラやセクハラが横行する男性社会の警視庁で働き、戦う女性刑事でした。立場や時代がちがっても、逆境に負けない人は私たちを勇気づけてくれます。本書も例外ではありません」(文庫版解説より)
本書は女性たちの戦いの原点、「#MeToo運動」の原点といってもいい作品なのです。この夏は、多感な時期の少女の力強い成長を見守りながら、戦争を考える季節にしてください。第66回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した、乃南アサさんの「新たな代表作」となった本書を、ぜひお楽しみいただけましたらと思います。
音楽バトル×ミステリー、エンタメ×純文学、SF×青春
宮内悠介が紡ぎ出す物語のカッコ良さをぜひ体感して欲しい!
宮内悠介が紡ぎ出す物語のカッコ良さをぜひ体感して欲しい!
"本好きとして、彼を知らないのはモグリでは?"と言っても過言ではない新進気鋭の作家の一人だ。
そんな彼の文庫本最新作が本書『アメリカ最後の実験』である。
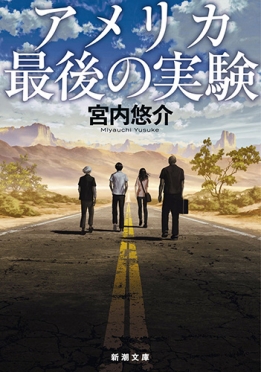 宮内悠介『アメリカ最後の実験』
宮内悠介『アメリカ最後の実験』
|
失踪した音楽家の父・俊一を追ってアメリカの難関音楽学校・グレッグ音楽院を受験する脩。彼は素晴らしいピアノの才能を持ちながら、とある事情から「音楽はゲーム」だと斜に構えた態度をとっていた。癖のある受験生や型破りな試験に対峙する中、試験会場で「アメリカ最初の実験」と書き残された殺人事件が発生する。そのメッセージに触発されて、第2、第3と全米へ連鎖するその事件に巻き込まれた脩は、かつて自分の父とその仲間が音楽によって果たそうとした夢こそが、一連の事件に深く関わっていると知る。
あらすじに収まりきらないほどの読みどころがこの小説には存在している。
脩という主人公を通じて、子供らしく生きられなかった子供がやがて家族とどう向き合うかライバルたちを通じて、才能を持った人間の幸福とは何か。
そしてそういった、音楽を志す人間の個人的な問題を端緒に、音楽という行為が持つ暴力性、宗教性、民族性といった本質について、ひいてはアメリカという国家が抱える深い傷の存在へと考察がつながっていく。
また、脩が用いるのは父からある女性へ託された架空のシンセサイザー<パンドラ>で、これは弾き手が奏でる曲の調を自ら解析し、本来の調から外して音の一部を半音下げにする。ピアノでは演奏不可能だったブルーノートを可能にした楽器だ。これが巻き起こす父子の物語もまた、ひとつの読みどころになっている。
そんなまぎれもなく洗練された音楽青春SF小説でありながら、中盤にはまさに殴り合って血を流すような演奏バトルシーンがある。(それがこの学校の入学試験のひとつなのだ)
そこでの主人公と、とあるライバルとのやりとりが、なんとも泣ける。
こいつにだけは負けたくない、という熱いバトルが少年漫画のように展開されるのである。この盛り上がりの面白さをぜひ本書で確かめて欲しい。




































