新潮新書
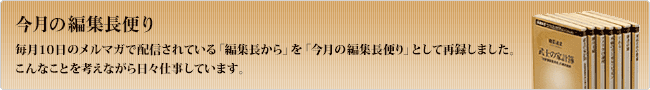
スター・ウォーズの話

「スター・ウォーズ」の第1作が公開された頃、私は小学生でした。現在ほどではないにしても、当時もかなり色々な関連グッズが流通しており、その中に「May the force be with you」という有名な台詞をプリントしたものがありました。
これはどういう意味なんだろうか。疑問に思った私は家にあった英和辞典を引いてみました。問題は英語力も辞典を引く能力も足りないという点で、「May」を「5月」と訳してしまうというありがちな勘違いをしたため、導き出された訳文は「5月の力は君と一緒」という意味不明なものに。
5月って何のことだろう。なぜ宇宙に5月が? さっぱりわかりません。
映画を観て、ちゃんと台詞まで聞き取れていれば問題なかったのでしょうが、そんな能力もあるはずもなく、「5月の謎」が解けたのは、何年も後だったように思います。ちなみに、今は「force」のことを「フォース」とそのまま言いますが、当時は「理力」と呼んでいました。
12月の新刊『スター・ウォーズ学』(清水節/柴尾英令・著)は、若い頃に「スター・ウォーズ」に出会って人生が変わったという著者2人が、その思いと知識を思いっきり詰め込んだ1冊。「そういえばそんなことがあったなあ」という懐かしさと「そんなことがあったのか」という発見の両方が味わえました。個人的に一番興味深かったのは、第1作を公開前に見たブライアン・デ・パルマがルーカスに対して「失敗作だ」と酷評していた、というエピソードでした。
他の新刊3点もご紹介します。
『イスラム化するヨーロッパ』(三井美奈・著)は、読売新聞の前パリ支局長が徹底的に現地を取材したレポート。いまヨーロッパはどうなっているのか。なぜそうなったのか。世界の今後を左右する問題がこの1冊で把握できます。
『戦略がすべて』(瀧本哲史・著)は、『武器としての決断思考』『僕は君たちに武器を配りたい』等のベストセラーで知られる著者の2年ぶりの新作。AKB48、東京五輪等、世の中の様々な事象から「必勝の法則」を見出していくその分析力は圧巻です。行き当たりばったりで仕事をしている場合ではないと改めて思いました。
『ほめると子どもはダメになる』(榎本博明・著)は、近年特に幅をきかせてきた「ほめることで伸ばす」といった言説に正面から立ち向かった問題作。「自分、ほめられて伸びるタイプなんです」なんてことを本当に言う学生が存在するそうです。何となく「ほめて伸ばす」というのが欧米流かと思っていたら、そんなことは全くなく、むしろ欧米は子どもに厳しい、といった指摘に驚かされました。
「5月の力は君と一緒」で「よくできました」とほめられなくて良かったと思いました。
今月も新潮新書をよろしくお願いします。

































