新潮新書
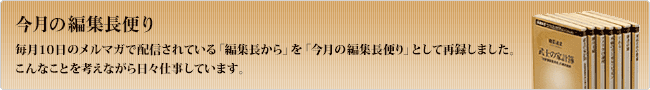
歴史を感じる話

新潮社で働いていると、時折歴史を感じることがあります。少し前までは、トイレが和式であることに感じていました。
太宰治先生の担当だった人が、廊下をうろうろしているのを見たときにも感じました。
つい最近は、小林秀雄先生の担当をしていた大先輩が会社を去ることになり、「お別れ講演会」のようなものが会社の大会議室で開かれました。ノルマではなく希望者が参加する形であるにもかかわらず、社長、役員から若手までが数多く集結。担当編集者の生の声で小林先生の素晴らしさを聞く貴重な機会を得ました。
残念なのは、私がほとんど小林先生の著作を読んだことがないことです。講演のメインテーマとなった大作『本居宣長』も未読のまま。
おそらく当分読むこともないのですが、いつか読みたいという気持ちくらいは持っていようと思ったものです。
5月新刊『知の体力』(永田和宏・著)は、読むと「勉強しなければ」
「学び続けなければ」という気持ちが沸き立つ1冊。京都大学名誉教授(細胞生物学)にして日本を代表する歌人でもある著者が、
「知の体力」の鍛え方を自身の経験を踏まえながら、やさしく説いていきます。読めば読むほど、「今からでも遅くない。勉強しよう」
と前向きな気持ちになります。脳に効く、読むエナジードリンクです。
他の新刊3点もご紹介します。
『PTA不要論』(黒川祥子・著)は、猛烈な支持と反発を招きそうなルポ。「支持」をしてくださるのは、「なぜこんな理不尽な目にあうのか」とPTAについて感じたことのある親御さん、特にお母さんたちでしょう。いまだに平日の昼間にベルマークを皆で集まってカウントしている、という事実に門外漢の私は驚かされました。
『発達障害と少年犯罪』(田淵俊彦・NNNドキュメント取材班・著)もまたかなりの問題作かもしれません。発達障害と少年犯罪に直接の関係はない。その点は著者も強調しています。しかし一方で障害を抱えた少年が、犯罪にかかわってしまうリスクがあることも事実です。著者は具体的なケースを追いながら、タブー視されがちなこの問題の現状と解決策を示していきます。
『コンビニ外国人』(芹澤健介・著)は、「なんでこんなに増えたの?」「どんな人たちなの?」という素朴な疑問に答えてくれます。法的にグレイゾーンの人もいれば、東大大学院生という人も。彼らがいなければ、コンビニ、ファミレスその他諸々、日本の産業はもはや成り立たなくなっているのは間違いありません。そんな隣人たちの素顔に迫ります。
5月新刊もさまざまな「知りたい」という欲求に応えるものになっています。
今月も新潮新書をよろしくお願いします。
- マサカの話 |
- 今月の編集長便りトップ
- | モヤモヤの話

































