新潮新書
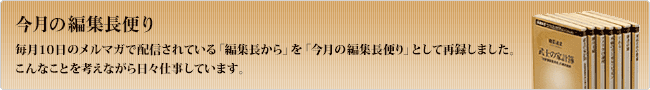
パワハラの話

20年以上前、入社して週刊誌の編集部に配属されて最初の出張先は沖縄でした。部内でも一番のベテラン記者と2人きりです。
ある場所に行く際に、地元の方が私たちのチャーターしたタクシーに乗って、道案内をしてくださいました。その際の私の態度が悪い、と後でベテラン記者に怒られました。
「せっかく案内してくださっている人に、君は道中まったく話しかけなかった。雑談の一つもしない。なんだあれは」
もともと私は人見知りで、初対面の人と話すのが得意ではないのですが、そんなことはその人の知ったことではありません。続けて、こう言いました。
「君はこの仕事に向いていない。辞めたほうがいい」
冗談ではなくて真剣なトーンでした。私も週刊誌の記者に向いているとは思っていなかったので「じゃあ早く異動させてくれ」と思ったものの怖いので言えませんでした。
新入社員に対していきなり「向いていない」「辞めろ」というのも、当時はそんなにおかしなことではなかった気がします。
ただ、仮に言われた側が訴えたら、現代ではおそらくパワハラ認定されて「アウト」の発言とされるでしょう。
10月新刊『パワハラ問題―アウトの基準から対策まで―』(井口博・著)は、この問題について理解するのに最適な1冊です。
著者は1000件以上のハラスメント相談を受けてきた弁護士。今年6月施行された通称「パワハラ防止法」の中味から、企業の危機管理法、管理職の心得等、パワハラに関するすべてを網羅した内容です。
他の3点もご紹介します。
『「池の水」抜くのは誰のため?―暴走する生き物愛―』(小坪遊・著)は、あの名番組「池の水ぜんぶ抜く大作戦」を徹底批判した内容......ではなくて、全国各地の知られざる「生き物事件」のレポートです。「池の水」を抜いて奇麗にすることの意義はあるものの、安易な外来種駆除は、生態系をおかしくすることにつながるようです。それ以外にも、動物を愛する人の善意が、かえって事態を悪化させるケースは少なくないことがわかります。マンガ『しっぽの声』が好きな方もぜひ。
『いじめとひきこもりの人類史』(正高信男・著)は、ベストセラー『ケータイを持ったサル』の著者による壮大な文明論。野生動物の世界では「いじめ」は存在せず、「ひきこもり」もいない。ではなぜヒトの世界では日常的に見られるのか。きっかけは「定住」と「共同体の形成」。500万年にわたる人類史から、ポストコロナの未来までを視野に入れた、画期的論考です。
コロナ時代になって、「身に沁みる」という声が多く寄せられていたのが、五木寛之さんの「週刊新潮」連載エッセイでした。その中から厳選したもの構成したのが『生き抜くヒント』(五木寛之・著)。
敗戦時の引き揚げという極限の体験をした方の言葉は強い、と感じます。「手洗いよりも心の換気を」「うつらぬ用心、うつさぬ気くばり」といった言葉に何となくホッとする方も多いのではないでしょうか。
冒頭に触れたベテラン記者の人とはいまでもつきあいがあります。結局、けっこう可愛がってもらいました(角界の「かわいがり」ではなくて文字通りの意味)。
今ではその人に「よくあんな酷いこと言えましたね」なんてことを言うこともできます。恨みもまったくありません。しかしそれは「たまたま」うまくいったのであって、まあ「辞めろ」とかは言わないのが今も昔も正解なのだろうと思います。
10月も新潮新書をよろしくお願いいたします。
ある場所に行く際に、地元の方が私たちのチャーターしたタクシーに乗って、道案内をしてくださいました。その際の私の態度が悪い、と後でベテラン記者に怒られました。
「せっかく案内してくださっている人に、君は道中まったく話しかけなかった。雑談の一つもしない。なんだあれは」
もともと私は人見知りで、初対面の人と話すのが得意ではないのですが、そんなことはその人の知ったことではありません。続けて、こう言いました。
「君はこの仕事に向いていない。辞めたほうがいい」
冗談ではなくて真剣なトーンでした。私も週刊誌の記者に向いているとは思っていなかったので「じゃあ早く異動させてくれ」と思ったものの怖いので言えませんでした。
新入社員に対していきなり「向いていない」「辞めろ」というのも、当時はそんなにおかしなことではなかった気がします。
ただ、仮に言われた側が訴えたら、現代ではおそらくパワハラ認定されて「アウト」の発言とされるでしょう。
10月新刊『パワハラ問題―アウトの基準から対策まで―』(井口博・著)は、この問題について理解するのに最適な1冊です。
著者は1000件以上のハラスメント相談を受けてきた弁護士。今年6月施行された通称「パワハラ防止法」の中味から、企業の危機管理法、管理職の心得等、パワハラに関するすべてを網羅した内容です。
他の3点もご紹介します。
『「池の水」抜くのは誰のため?―暴走する生き物愛―』(小坪遊・著)は、あの名番組「池の水ぜんぶ抜く大作戦」を徹底批判した内容......ではなくて、全国各地の知られざる「生き物事件」のレポートです。「池の水」を抜いて奇麗にすることの意義はあるものの、安易な外来種駆除は、生態系をおかしくすることにつながるようです。それ以外にも、動物を愛する人の善意が、かえって事態を悪化させるケースは少なくないことがわかります。マンガ『しっぽの声』が好きな方もぜひ。
『いじめとひきこもりの人類史』(正高信男・著)は、ベストセラー『ケータイを持ったサル』の著者による壮大な文明論。野生動物の世界では「いじめ」は存在せず、「ひきこもり」もいない。ではなぜヒトの世界では日常的に見られるのか。きっかけは「定住」と「共同体の形成」。500万年にわたる人類史から、ポストコロナの未来までを視野に入れた、画期的論考です。
コロナ時代になって、「身に沁みる」という声が多く寄せられていたのが、五木寛之さんの「週刊新潮」連載エッセイでした。その中から厳選したもの構成したのが『生き抜くヒント』(五木寛之・著)。
敗戦時の引き揚げという極限の体験をした方の言葉は強い、と感じます。「手洗いよりも心の換気を」「うつらぬ用心、うつさぬ気くばり」といった言葉に何となくホッとする方も多いのではないでしょうか。
冒頭に触れたベテラン記者の人とはいまでもつきあいがあります。結局、けっこう可愛がってもらいました(角界の「かわいがり」ではなくて文字通りの意味)。
今ではその人に「よくあんな酷いこと言えましたね」なんてことを言うこともできます。恨みもまったくありません。しかしそれは「たまたま」うまくいったのであって、まあ「辞めろ」とかは言わないのが今も昔も正解なのだろうと思います。
10月も新潮新書をよろしくお願いいたします。
2020/10
- バブルの話 |
- 今月の編集長便りトップ
- | 空気を読む話

































