新潮新書
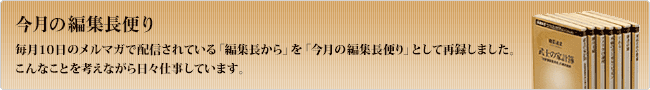
悪魔ちゃんの話

30代以上の方ならご記憶でしょうか。1994年、ある男の子に親が「悪魔」と命名したことで騒動が勃発。その名を認めるべきか否か、メディアや行政で侃々諤々の議論が巻き起こりました。
当時、週刊誌記者だった私は、悪魔ちゃん一家のところに何度か話を聞きに行きました。悪魔ちゃんは角も尻尾もない可愛い男の子でしたし、お父さんはシャレのわかる面白い人という印象でした。ネーミングのセンスなどは、おそらく彼の「ヤンキー的」な感覚がベースになっていたように思います。当時の記事を読み返すと、次の子供の名前は“帝王”か“爆弾”にでもしようか、などと語っています。
元気ならば成人になっているはずの「悪魔ちゃん」は、昨今の「キラキラネーム」ブームをどう見ているのでしょう。
久しぶりに悪魔ちゃんについて思い出したのは、5月新刊の1冊、『キラキラネームの大研究』(伊東ひとみ・著)を読んだのがきっかけでした。
もっとも、『キラキラネームの大研究』は、こういう最近の珍名さんについての考察に終始した本ではありません。キラキラネームについてあれこれ調べるうちに、日本語の本質にたどり着く、という知的興奮に満ちた内容になっています。本邦初の「キラキラネーム論」にご期待下さい。
本邦初という点では同じく5月刊の『小林カツ代と栗原はるみ―料理研究家とその時代―』(阿古真理・著)も負けていません。本邦初の「料理研究家論」です。タイトルの2人の他、江上トミ、有元葉子、辰巳芳子、土井勝、ケンタロウ等々、その世界のオールスターが勢ぞろい。「なるほど、こんな切り口の戦後史があったのか」と驚くこと必至です。
他の新刊2点もご紹介します。
『習近平の中国』(宮本雄二・著)は、元中国大使による一級のインテリジェンス・レポート。習近平とは何者か。何を考えているのか。中国共産党はいかなる論理で動いているのか。これからどうなるのか。習氏と何度も食事を共にした経験を持つ著者が、冷静かつ丁寧に分析を加えていきます。
『呆けたカントに「理性」はあるか』(大井玄・著)は、タイトルだけだとちょっと内容がわかりにくいかもしれません。著者の大井さんは、東京大学医学部名誉教授で、長年、終末期医療にかかわってきました。
私たちは、認知症の老人には、理性的判断の能力は無いとつい考えてしまいがちです。しかし、臨床の現場で体験を重ねてきた著者はそれを明確に否定します。「胃ろうをしたいですか」と尋ねられた多くの認知症患者が明らかに拒否をしたというのです。なぜそうなるのか。この問いから始まった考察は、最終的に「人間の理性は何か」という深く本質的な議論にまで到達していきます。『「痴呆老人」は何を見ているか』が7万部超のロングセラーとなっている著者の真骨頂ともいえる作品です。
昔の記事で、悪魔ちゃんのお父さんはこんなことを語っています。
「(悪魔という名は)一度、聞いたら絶対、忘れない。世の中に名前を売るのは大変だと思う。例えば“セイントフォー”というアイドルグループは40億もの宣伝費を投じて、売り出そうとした。うちの悪魔にはもうすでにそれくらいの宣伝効果があったと思います。この力は大きい」
結局、悪魔ちゃんは改名を余儀なくされたのですが、タイトルでいつも悩んでいる身としては、「あのお父さん、結構鋭いことを言っていたんだなあ」と思いました。
今月も新潮新書をよろしくお願いします。
- 圧力の話 |
- 今月の編集長便りトップ
- | 英会話の話

































