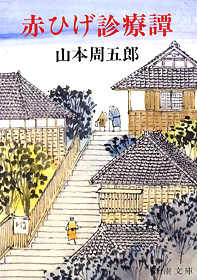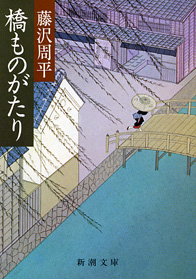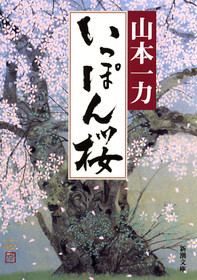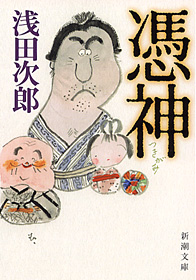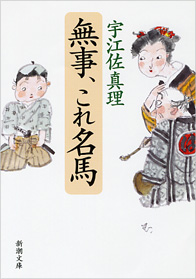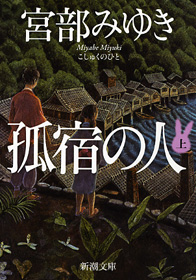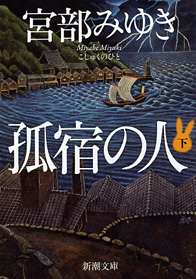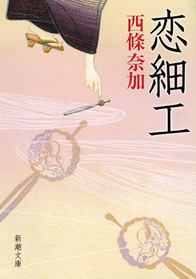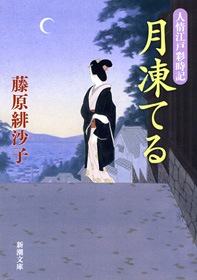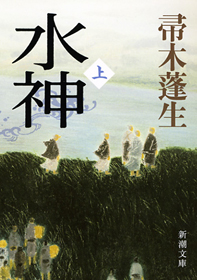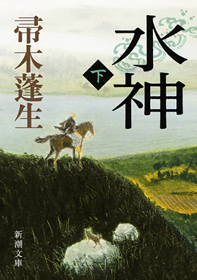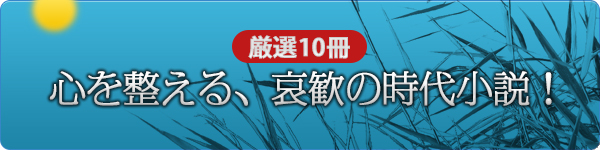
あと少しでお正月ですね。この時期になると一年があっという間に過ぎてしまったな、と思います。毎年のことながら、この一年のことや自分自身のことを考えるのが習慣となっています。
いや、個人的な習慣というより、一年の節目というのは、どんな一年を送っても自分自身を見つめ直す人類共通の一コマではないでしょうか。そして、目標や希望を抱いて新たな年を過ごしていく岐路でもあります。
そう、「一年の計は元旦にあり」との諺(ことわざ)があるように、私たちにとってとても大事な時期なのです!
![]()
今回は、そんな重要な時期にふさわしい、心を整えてくれる時代小説をピックアップしました。
登場人物の胸に秘めた想いや人生模様を鮮やかに描いた珠玉の作品を手に取ってみてください。心がスッキリすると同時に、思いもよらない視界の広がりを感じるはずです。
山本周五郎『赤ひげ診療譚』 |
-
幕府の御番医という栄達の道を歩むべく長崎遊学から戻った保本登は、小石川養生所の“赤ひげ”とよばれる医長新出去定に呼び出され、医員見習い勤務を命ぜられる。貧しく蒙昧な最下層の男女の中に埋もれる現実への幻滅から、登は尽く赤ひげに反抗するが、その一見乱暴な言動の底に脈打つ強靱な精神に次第に惹かれてゆく。傷ついた若き医生と師との魂のふれあいを描く快作。
●山本周五郎『赤ひげ診療譚』
藤沢周平『橋ものがたり』 |
-
幼な馴染のお蝶が、仕事場に幸助を訪ねてきた。奉公に出るからもう会えないと、別れを告げるために。「五年経ったら、二人でまた会おう」年季の明けた今、幸助は萬年橋の袂でお蝶を待つが……。(「約束」)様々な人間が日毎行き交う江戸の橋を舞台に演じられる、出会いと別れ。市井の男女の喜怒哀楽の表情を瑞々しい筆致に描いて、絶賛を浴びた傑作時代小説。
●藤沢周平『橋ものがたり』
乙川優三郎『五年の梅』 |
-
ひどい回り道をしたが、いまからでは駄目だろうか……。山本周五郎賞受賞作!
友を助けるため、主君へ諫言をした近習の村上助之丞。蟄居を命ぜられ、ただ時の過ぎる日々を生きていたが、ある日、友の妹で妻にとも思っていた弥生が、頼れる者もない不幸な境遇にあると耳にし──「五年の梅」。表題作の他、病の夫を抱えた小間物屋の内儀、結婚を二度もしくじった末に小禄の下士に嫁いだ女など、人生に追われる市井の人々の転機を鮮やかに描く。生きる力が湧く全五篇。
●乙川優三郎『五年の梅』
山本一力『いっぽん桜』 |
-
突然「定年」を言い渡された番頭が、一本の桜に込めたのは、娘への思いだった……。人情時代小説の決定版!
仕事ひと筋で、娘に構ってやれずにきた。せめて嫁ぐまでの数年、娘と存分に花見がしたい。ひそかな願いを込めて庭に植えた一本の桜はしかし、毎年咲く桜ではなかった。そこへ突然訪れた、早すぎる「定年」……。陽春の光そそぐ桜、土佐湾の風に揺れる萩、立春のいまだ冷たい空気に佇むすいかずら、まっすぐな真夏の光のもとで咲き誇るあさがお。花にあふれる人情を託した四つの物語。
●山本一力『いっぽん桜』
浅田次郎『憑神』 |
-
抱腹絶倒にして感涙必至。貧乏侍vs.貧乏神!? 幕末時代小説の最高傑作。
時は幕末、処は江戸。貧乏御家人の別所彦四郎は、文武に秀でながら出世の道をしくじり、夜鳴き蕎麦一杯の小遣いもままならない。ある夜、酔いにまかせて小さな祠に神頼みをしてみると、霊験あらたかにも神様があらわれた。だが、この神様は、神は神でも、なんと貧乏神だった! とことん運に見放されながらも懸命に生きる男の姿は、抱腹絶倒にして、やがては感涙必至。傑作時代長篇。
●浅田次郎『憑神』
宇江佐真理『無事、これ名馬』 |
-
頭、拙者を男にして下さい! 武家の息子、火消しの頭に弟子入り志願!? 少年の成長を描く心温まる時代小説。
吉蔵は町火消し「は組」の頭。火の手が上がれば、組を率いて駆け付け、命懸けで火事を鎮める。そんな吉蔵に、武家の息子・村椿太郎左衛門が弟子入りを志願してきた。生来の臆病ゆえに、剣術の試合にどうしても勝てない太郎左衛門。吉蔵の心意気に感化され、生まれ変わることができるのか……。少年の成長と、彼を見守る大人たちの人生模様を、哀歓鮮やかに描き上げる、傑作時代小説。
●宇江佐真理『無事、これ名馬』
宮部みゆき『孤宿の人〔上・下〕』 |
-
加賀様は鬼だ、悪霊だ。この丸海藩にあらゆる災厄を運んでくる。著者の時代小説最高峰、人情味溢れる傑作長編。
北は瀬戸内海に面し、南は山々に囲まれた讃岐国・丸海藩。江戸から金比羅代参に連れ出された九歳のほうは、この地に捨て子同然置き去りにされた。幸いにも、藩医を勤める井上家に引き取られるが、今度はほうの面倒を見てくれた井上家の琴江が毒殺されてしまう。折しも、流罪となった幕府要人・加賀殿が丸海藩へ入領しようとしていた。やがて領内では、不審な毒死や謎めいた凶事が相次いだ。
●宮部みゆき『孤宿の人〔上〕』
-
頑なに閉ざされた加賀様の心を無垢な少女・ほうだけが開いていく。ラストシーンに思わず涙、感動の時代ミステリー。
加賀様は悪霊だ。丸海に災厄を運んでくる。妻子と側近を惨殺した咎で涸滝の屋敷に幽閉された加賀殿の祟りを領民は恐れていた。井上家を出たほうは、引手見習いの宇佐と姉妹のように暮らしていた。やがて、涸滝に下女として入ったほうは、頑なに心を閉ざす加賀殿といつしか気持ちを通わせていく。水面下では、藩の存亡を賭した秘策が粛々と進んでいた。著者の時代小説最高峰、感涙の傑作。
●宮部みゆき『孤宿の人〔下〕』
西條奈加『恋細工』 |
-
一門を任された女。寄る辺のない男。銀線がたぐり寄せた運命の出逢い。職人世界の粋を描き切った、本格時代小説。
百年続く「椋屋」の娘・お凜は、女だてらに密かに銀線細工の修行をしている。跡目争いでざわめくなか現れた謎の男・時蔵は、江戸では見られない技で簪をつくり、一門に波紋を呼ぶ。天保の改革で贅沢品が禁じられ商いが難渋するなか、驚天動地の大注文が入る。江戸の町に活気を与えたいと、時蔵とお凜はこころをひとつにするが──。職人世界の粋と人情を描き切った本格時代小説。
●西條奈加『恋細工』
藤原緋沙子『月凍てる―人情江戸彩時記―』 |
-
文芸評論家、縄田一男氏激賞! 「人情物の名篇がここに誕生した」。人情時代小説、感涙必至の四編。
幼馴染みのおまつとの約束をたがえ、奉公先の婿となり主人に収まった吉兵衛は、義母の苛烈な皮肉を浴びる日々だったが、おまつが聖坂下で女郎に身を落としていると知り……(「夜明けの雨」)。兄を殺した仇を九段坂で張り込む又四郎に国許より兄嫁自害の知らせがもたらされた(「月凍てる」)。江戸の坂を舞台に人びとの哀歓を掬い取った人情時代小説の傑作四編。『坂ものがたり』改題。
●藤原緋沙子『月凍てる―人情江戸彩時記―』
帚木蓬生『水神〔上・下〕』 |
-
「筑後川の恵みで、村人たちを潤したい」庄屋はその大事業に全身全霊で臨んだ。新田次郎文学賞受賞。
目の前を悠然と流れる筑後川。だが台地に住む百姓にその恵みは届かず、人力で愚直に汲み続けるしかない。助左衛門は歳月をかけて地形を足で確かめながら、この大河を堰止め、稲田の渇水に苦しむ村に水を分配する大工事を構想した。その案に、類似した事情を抱える四ヵ村の庄屋たちも同心する。彼ら五庄屋の悲願は、久留米藩と周囲の村々に容れられるのか──。新田次郎文学賞受賞作。
●帚木蓬生『水神〔上〕』
-
故郷・九州の大地に捧げられた熱涙巨篇。老武士は、領民の幸せのために自らの命を差し出した。
ついに工事が始まった。大石を沈めては堰を作り、水路を切りひらいてゆく。百姓たちは汗水を拭う暇もなく働いた。「水が来たぞ」。苦難の果てに叫び声は上がった。子々孫々にまで筑後川の恵みがもたらされた瞬間だ。そして、この大事業は、領民の幸せをひたすらに願った老武士の、命を懸けたある行為なくしては、決して成されなかった。故郷の大地に捧げられた、熱涙溢れる歴史長篇。
●帚木蓬生『水神〔下〕』