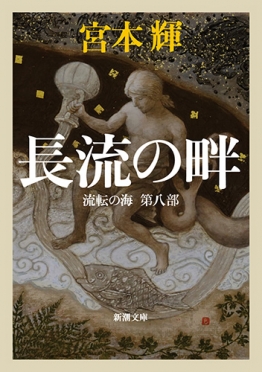 宮本輝/著 『長流の畔―流転の海 第八部―』 |
宮本輝さんが『流転の海 第一部』の執筆に取りかかったのは、1981年(昭和56年)のことでした。父の物語を3巻本の構想で書き始めたのだそうです。雑誌「海燕」での連載を終え、単行本が福武書店から刊行されたのが1984年7月。その後しばらくの中断があって、第二部『地の星』は、雑誌「新潮」連載を経て1992年11月に刊行されます。 そしてこの夏、「新潮」(2018年7月号)で、第九部『野の春』が完結しました。ちょっと並べてみます。
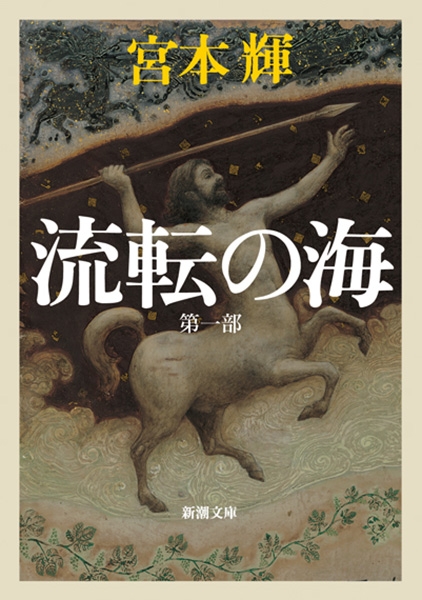
(福武書店版1984年7月刊/ 新潮社版1992年11月刊/ 新潮文庫版1990年4月刊) |
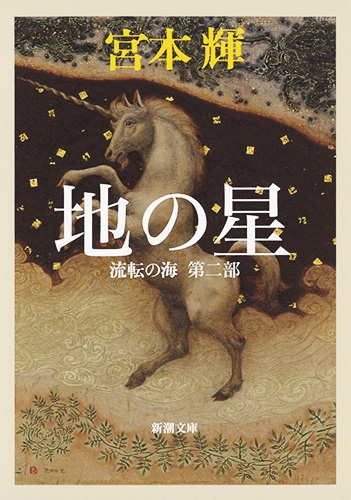
(1992年11月刊/文庫1996年 2月刊) |
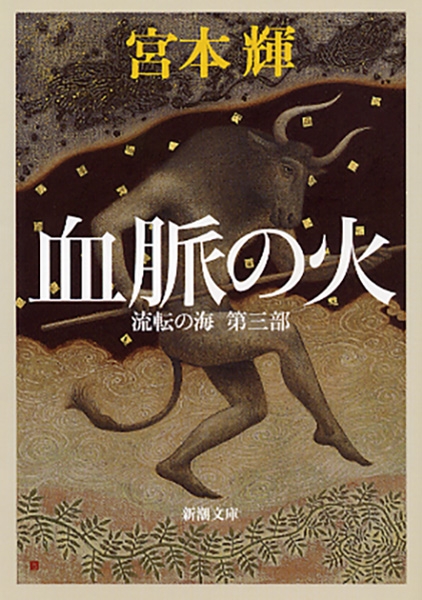
(1996年 9月刊/文庫1999年 10月刊) |
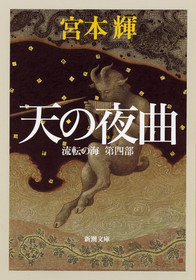
(2002年 6月刊/文庫2005年 4月刊) |
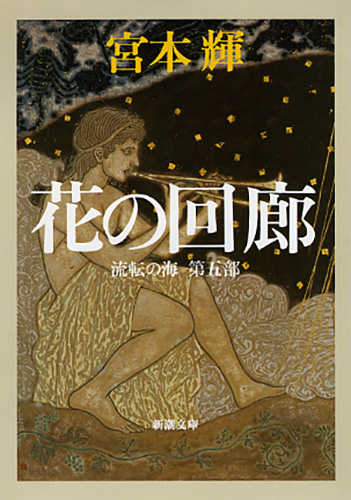
(2007年 7月刊/文庫2010年1月刊) |
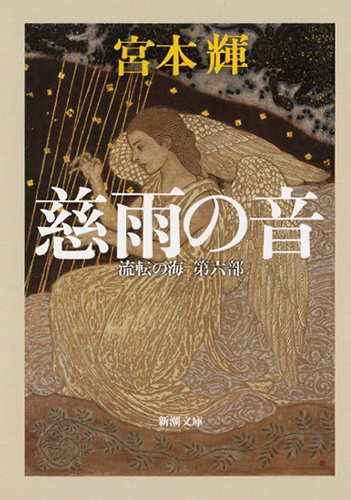
(2011年 8月刊/文庫2014年 3月刊) |
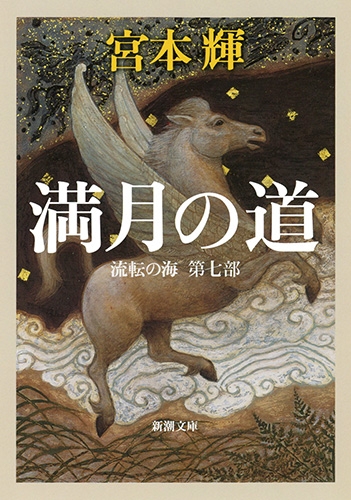
(2014年 4月刊/文庫2016年 10月刊) |
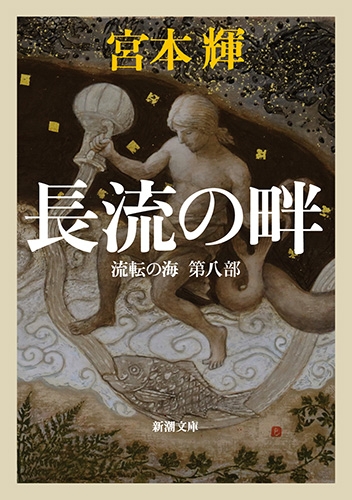
(2016年 6月刊/文庫2018年 10月刊) |
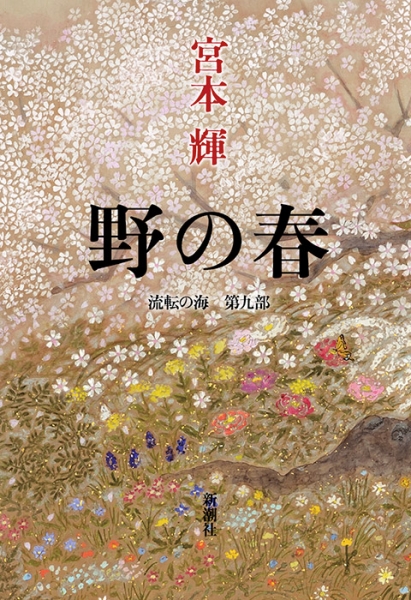
(2018年 10月刊) |
実に37年です。
「流転の海」シリーズは、
1947年(昭和22年)50歳にして、我が子伸仁を授かり、彼はこの子が二十歳になるまでは絶対に死なぬと心に誓うのです。戦後の喧噪と惑乱の中で、熊吾は才覚と度胸で再び事業を立ち上げます(第一部『流転の海』)。
しかし、妻子の心身の不調もあって、いったん郷里の南宇和に沈潜します(第二部『地の星』)。
1947年(昭和22年)50歳にして、我が子伸仁を授かり、彼はこの子が二十歳になるまでは絶対に死なぬと心に誓うのです。戦後の喧噪と惑乱の中で、熊吾は才覚と度胸で再び事業を立ち上げます(第一部『流転の海』)。
しかし、妻子の心身の不調もあって、いったん郷里の南宇和に沈潜します(第二部『地の星』)。
その後、再起をかけて大阪に乗り込みます(第三部『血脈の火』)。
大阪で厳しい戦いを強いられながら、妻子を富山の知人の家に預けます(第四部『天の夜曲』)。
舞台はふたたび大阪に戻るのですが、電気もガスも通らぬ冷たく暗いビルに熊吾と房江は暮らし、小学生の伸仁は半島出身だったりと様々な背景を背負った人々の住む蘭月ビルに住む叔母のタネの部屋に居候することになります(第五部『花の回廊』)。
1959年(昭和34年)、自動車時代の到来に合わせ、熊吾は大規模駐車場の経営に乗り出し、中学生になった伸仁は母とともに駐車場の管理をし、熊吾は中古車販売業にも手を伸ばします(第六部『慈雨の音』)。
熊吾の興した中古車販売会社「中古車のハゴロモ」は順調に売上を伸ばし、支店まで出来るのですが、突然、売上が伸びなくなります。伸仁は高校生になり、虚弱だった体質も少しずつ強くなっていきます。そんな中、熊吾はたちの悪い情夫と別れられないでいるヌードダンサーだった森井博美と再会し、不本意ながら手切金の金策に走ることになります(第七部『満月の道』)。
そして本巻第八部『長流の畔』です。長いネタ振りでした。
1962年(昭和37年)、高校生の伸仁は、母房江の働くホテルでアルバイトしたり、野宿だらけの旅行を計画したりしています。熊吾の方はといえば、せっかく軌道に乗っていた「中古車のハゴロモ」でしたが、部下に、カネを持ち逃げされたのでした。仕入れの資金もありません。房江のヘソクリが活躍して、急場をしのぐのですが、それよりも何よりも、森井博美です。人気ダンサーだっただけあって、スタイル抜群で美貌なんですが顔の横に火傷の跡があります。不注意な事故でそうなったのですが(第四部『天の夜曲』参照)、ダンサーをやめて、小さな飲み屋の老婆の手伝いをしています。この不器用な生き方しかできない女と熊吾は関係を持ってしまいます。
古今、女性というものは鋭いものと決まっています。賢夫人房江が気づかぬ訳はありません。熊吾の不逞を罵り、房江は空気の抜けた風船のようになってしまいます。熊吾は、多感な時期の伸仁にだけは伏せよといいましたが、結局、伸仁の知るところとなり、伸仁も熊吾と距離を置きはじめます。森井博美との関係、資金を持ち逃げされた「中古車のハゴロモ」の経営、深く傷ついた房江と伸仁......さあ、松坂一家はどうなるのか!!!!
というような第八部『長流の畔』です。
最終巻の第九部『野の春』は単行本が10月下旬に刊行されます。文庫になるのは2年半~3年後ですから、2021年春くらいでしょうか。この秋に単行本で読むもよし、2年半待って文庫で読むもよし。壮大な物語が圧倒的な感動とともに完結します。
このシリーズをまだ読まれていない方は、ラッキーです。今から読みましょう。損はさせません。
新潮文庫では、〈新・山本周五郎〉 と銘打って、怒濤の攻撃を仕掛けます。
二本立てです。
A面攻撃は、これまで長く新潮文庫で販売してきた周五郎の主立った名作をリニューアルして出し直します。
「文字拡大」「注釈」「図版(登場人物表や地図や系図)」この三つの編集替えを軸に、カバーも新しく修正して刊行します。
2018年10月
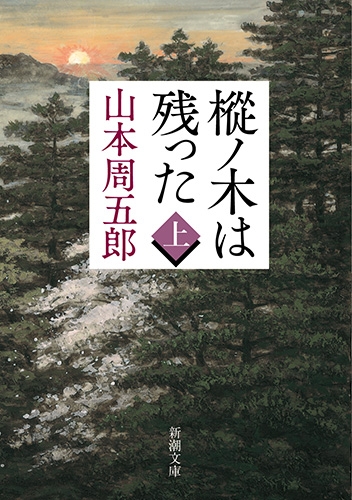
|
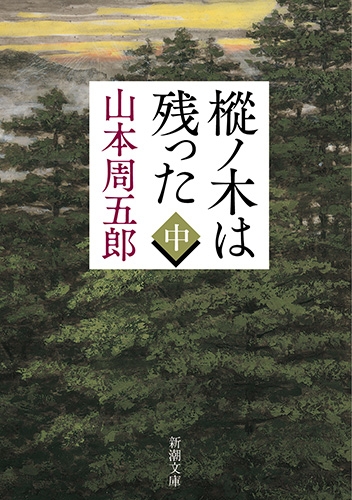
|
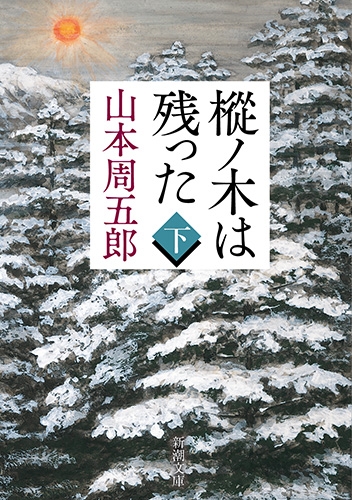
|
2018年11月 『さぶ』『日本婦道記』
2018年12月 『ながい坂』(上下)
2019年 1月 『青べか物語』
2019年 2月 『柳橋物語・むかしも今も』
2019年 3月 『栄花物語』『赤ひげ診療譚』
といったラインナップです。
「注釈」といえば、近代文学の名作、芥川とか鴎外とか漱石とか、そうしたものに付くものと相場は決まっていたのですが、時代小説である山本周五郎も代表的な名作について注釈を付けます。ベテランの読者だったら、必要のない注釈なのかもしれませんが、テレビで時代劇がずいぶん減ってしまった今となっては、若い読者には、
「
「
「
「
というような言葉はあまり馴染みがないと思われます。余計なお世話かもしれませんが、巻末にどんどん注釈をいれました。時代小説初心者も安心してお読みいただけます。
一方で、ベテラン過ぎると登場人物が増えてくると、「あー、これ誰だっけ?」というような事態になったりします。あなたは大丈夫かもしれませんが、私はなります。そんな私のために「登場人物表」が付くわけです。地図は地名の記憶補助に、系図は関係性の記憶の補助になります。文字が大きくなったのも、ありがたいです。つまり、ベテランから若者まで、すべてに喜ばれるリニューアルを敢行していくというわけです。解説もリニューアルしていく予定です。これがA面攻撃。
さてB面攻撃です。
A面が本格的な正面突破とすれば、B面は、搦め手攻撃です。警備の手薄な裏門を攻めるのです。
山本周五郎は、苦難を真摯に生きる人間達の哀歓を通して、読む者に深い感動と生きる喜びを提供し続ける傑出したすごい作家なわけですが、その周五郎が、27歳~37歳〈1930~1940年〉のほぼ10年間 、少年少女向けに痛快な探偵小説や血湧き肉躍る冒険活劇を旺盛に執筆していたのです。
様々な研究者や愛読者がこの少年小説を探してきたのですが、この度新たに十数編の新規発掘作品が文芸評論家の末國善己氏によって発見されました。これらの少年少女向けの活劇小説を五冊に分けて刊行します。
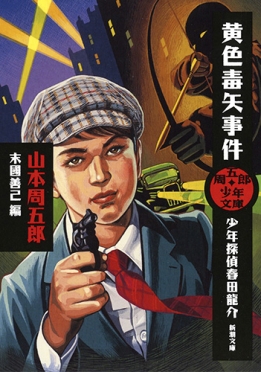
|
2018年10月『黄色毒矢事件―少年探偵春田龍介―』
2018年11月『殺人仮装行列―探偵小説集―』
2018年12月『木乃伊屋敷の秘密―怪奇小説集―』
2019年 1月『少年間諜X13号―冒険小説集―』
2019年2月『南方十字星―海洋小説集―』
痛快な冒険活劇になっています。発表当時は昭和10年前後で、戦争へと傾斜していくそういう世相です。一滴で戦車を吹っ飛ばせる爆液を開発している研究所とか、軍部からの依頼で殺人光線を研究している研究所とか、そういう道具立てで、殺人事件が起き、少年探偵や研究所の助手が、名推理を披露して一瞬にして解決します。痛快無比です。これは買いです。先日、『黄色毒矢事件―少年探偵春田龍介―』の見本ができたのですが、社内のあちこちから、「読ませて、読ませて」と引っ張りだこでした。是非、周五郎の裏芸を堪能されて下さいませ!



































