新潮新書
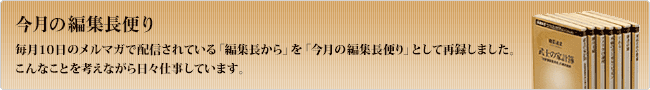
元・新人類、今・中年

毎月4冊ずつ出し続けているといろんな反響があるものなのですが、8月に刊行した『1985年』(吉崎達彦著)に対する反響はなかなか興味深いものがありました。というのも、40代前半から30代後半(要は1960年代生まれですね)とそれ以外の年代では、この本に対する「温度」がまったく違ったのです。
85年当時、学生や社会人1、2年目だった40代前半世代にとっては、この本の中で触れられている出来事の一つ一つが若い頃の思い出と重なるためか、かなり「熱い」反応が返ってきました。発売直後に毎日新聞と朝日新聞のコラムでもさっそく取り上げられましたが、いずれも書いた記者はこの世代の方です。
一方で、周囲の50代、60代の反応は「85年なんて最近の話じゃないか」、30代前半より若い層は「あまりよく憶えてないんですよね」と、まったくピンと来ない様子。最近たまたま話した大学生に至っては、「私が生まれた年です……」。年代によって、これほど反応が分かれたのは、創刊以来はじめての経験でした。
刊行前の勝手な目論見としては、「1985年が戦後史の転換点だったことを知らしめたい」「プラザ合意から20年というタイミングで、政治経済の視点の入った80年代論を送り出したい」――などと考えていたのですが、それよりまず40代前半世代の「懐かしさ」のツボにはまった、ということなのかもしれません。
かく言う私も1963年生まれで、この世代のど真ん中。本書を読んですっかり「懐かしモード」に入ってしまい、本棚をひっくり返して「あの頃の本」を見つけては、一人で喜んでいる始末。本には刊行された時代がくっきりと刻印されていますから、タイムカプセルを開けるような楽しみがあります。本棚の奥から出てきたのは、例えばこんな本たちです(作品名連発につき、適当に読み飛ばしてください)。
『見栄講座』――ビッグコミック・スピリッツの「気まぐれコンセプト」で人気を博していたホイチョイ・プロダクションの単行本第一作。83年に出て、84年にはベストセラーになりました。このパロディ精神、遊び心は時代の空気を見事に反映しています。個人的にはその後の『OTV』(85年)も好きです。物語のパターンを徹底的に茶化して、なおかつそれを楽しむという酒場ネタを、そのまま作品にしたのはこのあたりが始まりでしょう(余談ながら、今スピリッツで連載中の「東京エイティーズ」にはこういう時代の雰囲気が描かれておらず残念。主人公が広告業界を目指すならホイチョイは読んでいたでしょうに。そのへんが20年の時差でしょうか)。
『逃走論』――言わずと知れた浅田彰氏の第二作。84年刊です。オビの文句がなんとも凄い。「ホント、重苦しい『学問』や『主義』なんて、もうアキアキだよね。だから……軽やかに《知》と戯れてみたい!」。このとき浅田氏は26歳でした。
『朝日のような夕日をつれて』――第三舞台、鴻上尚史氏の第一戯曲集。これも気合の入ったオビです。「スウィングする言葉、シェイクする思想、ポップな身体。早稲田、第三舞台をひきいる弱冠24才」。懐かしいなあ、大隈講堂裏のテント。
『ぎゅわんぶらあ自己中心派』――ヤングマガジンに連載されていた片山まさゆき氏の麻雀マンガですが、その力技のパロディ、貪欲なネタ探し、開き直りのギャグ……まさしく80年代前半的作品と言っていいでしょう。今でも忘れられないのは「リクルート麻雀」の回。「証四喜」「都銀無双十三面待ち」といったパロディのおかげで、私は初めて「四大証券」「都銀十三行」なる言葉を知りました(今ではもう成り立たないギャグですが)。
あの頃の文化を語るときには、懐かしさと気恥ずかしさが同時に湧いてきます。これが10年前だったら、気恥ずかしさが先にたって、ちょっと真顔では語れなかったでしょう。今なら、「しょうもない時代だったなあ」と言いながら、「でも、いい時代だった」と照れずに肯定することができます。それだけこちらも歳をとったということでしょう。
恥ずかしいといえば、私たちが学生の頃は「新人類」などという赤面ものの言葉もありました。85年には、朝日出版社が出していた新書シリーズ「週刊本」の一冊として、『新人類論』という本も刊行されているほど(著者は当時「朝日ジャーナル」の編集長だった筑紫哲也氏。読み返してみると、氏の“若者好き”は20年間変わっていないことがわかり、ある意味で感動ものです)。
いまやその「新人類」も立派な中年になり、いつのまにか中堅です。若いつもりでいたのに、新入社員とは20年も開きができて、あまりの文化の違いに愕然とすることもしばしば。気がつけば「最近の若い者は……」という台詞を口にしている向きも多いのでは?
でも思い起こせば、私たちも上の世代からはさんざん言われていたんですね。60年代生まれはちょうど共通一次世代でもありますから、あの頃は「マークシート世代、偏差値世代は使い物にならない」という論調さえありました。どの時代も若者の扱われ方にはたいして違いはないし、そう考えると若い世代もずいぶん身近な存在に見えてきます。
今月刊の★『話せぬ若手と聞けない上司』(山本直人著)は、まさに60年代生まれの著者が、会社(博報堂)の新人育成係として「最近の若者」と向き合った奮戦記です。むろん山本氏も最初から新人たちを理解できたわけではありませんが、「育てる」という視点で見ていくうちに、世代間のミゾの正体に気がつきます。「ネコ型イヌ型」「自分ストーカー」といった腑に落ちるキーワードに納得しつつ、「そういう新人、そういう上司がいるなあ」と思わず周りの人間の顔が浮かんでくるはず。そして山本氏の誠実で暖かい筆致をたどるうちに、「どの世代も捨てたものではない」と元気が出てきます。特に中間管理職世代の30代、40代に読んでいただきたい一冊です。
他の3点は次のとおり――。
★『阿片の中国史』(譚ろ美著)は、唐の玄宗帝から蒋介石、毛沢東に至るまで、中国の歴史において阿片がどのような役割を果たしたかを追った、阿片から見た中国通史。なぜ中国だけが「阿片漬け」になったのか、その事情がよくわかります。
★『ドクター・ショッピング―なぜ次々と医者を変えるのか―』(小野繁著)は、セカンド・オピニオン流行りの陰で、実は増えつつある「病院めぐり」「医者めぐり」症候群の実態に迫り、どうすればその悪循環から抜け出せるかの処方箋を示します。
★『コクと旨味の秘密』(伏木亨著)は、「美味しさ」のメカニズムを徹底的に解き明かした目からウロコの科学読み物。なぜすき焼きが美味いのか、なぜラーメンは毎日食べても飽きないのか。これを読めば、食事がいっそう楽しくなること請け合いです。

































