新潮新書
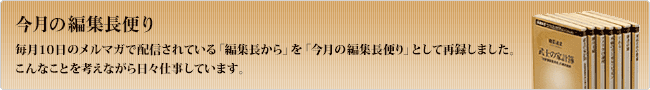
脳が壊れたの話

もう気づけば何十年も「週刊モーニング」を愛読している私は、ある時期「ギャングース」という連載を愛読していました。
恵まれない生い立ちの若者たちを描いた犯罪モノの漫画で、原作者はルポライターの鈴木大介さん。
その鈴木さんが41歳で脳梗塞で倒れたときの闘病ドキュメントが2016年に刊行した『脳が壊れた』でした。
脳梗塞からの回復の様を当事者が克明に記録した同書は、発売直後から大きな話題を呼びました。養老孟司先生には、
ゲラの段階でお渡ししたらあっという間に絶賛のコメントをいただきました。
この本の特異なところは、著者がこれまで培った手法で自らを取材対象として「ルポ」を行なっている点です。脳が壊れると、世の中はどう見えるのか。
何が苦しいのか。どうやって回復していくのか。持ち前の好奇心と取材力で描写していくのです。
2月の新刊、『脳は回復する―高次脳機能障害からの脱出―』(鈴木大介・著)は、その『脳が壊れた』の続編。
前作を読まれた方は「えっ? もう回復したのでは?」と思われるかもしれませんが、実はまだ回復の途上だったことがわかります。
著者のユーモアも健在なので、前作同様、面白く読め、しかも最後は泣ける稀有な本になっています。
他の3点もご紹介します。
『新聞社崩壊』(畑尾一知・著)は、この先新聞業界に何が起きるのか、
どうすれば破綻から逃れられるかについて、朝日新聞の販売局で部長を務めていた著者が分析した1冊です。
最近とかく新聞関連では「偏向」とか「捏造」がテーマになることが多いのですが、販売畑で実務を担ってきた著者は、
経営の観点から冷静に論を進めていきます。全国紙はもちろん、地方紙の経営状況に関する独自分析がここまで行なわれた本は珍しいのではないでしょうか。
『イスラム教の論理』(飯山陽・著)は、
新進のイスラム研究者による刺激的なイスラム入門。どこが刺激的かというと、
従来よく耳にしていた日本のイスラム学者の主張に一切忖度していないところ。IS関連の報道の際に、
よく言われた「イスラム教は平和の宗教だ」といった説を完全に否定しています。むしろISのほうが、コーランの教えに忠実だとも言える、というのです。
『団塊絶壁』(大江舜・著)は、
これから本格的に老後を迎える団塊世代のためのシミュレーションであり、エールであり、生き残りマニュアル。
堺屋太一さん、ビートたけしさん、弘兼憲史さん等々、
各界の有名人への取材も多数収録した、いわば団塊版「君たちはどう生きるか」です。
2月も新潮新書をよろしくお願いします。
- バブルの話 |
- 今月の編集長便りトップ
- | 忙しい話

































