『砂の器』『霧の旗』『けものみち』……「清張はタイトルも巧い」と言われるが実は――。総計20512ページに挑んだライターが選ぶ、清張の長編ベスト1は!?
新潮文庫で読める松本清張の長編作品は、現在二十八冊。そのうち、上下巻の作品が六作あるから作品数は二十二作だ。一日一冊読んでも一か月はかかるが、意外にも半月近くで完読してしまった。清張の文章は読みやすく、独特のリズムがあって物語に没入しやすいからだ。それに加えて、映像化された作品が多いので、そのイメージと重ね合わせて読むこともできる。
しかし、伏兵は意外なところにいた。没後三十年を機に、各社で清張作品が増刷・復刊され、関連本も刊行されている。もちろん、それらすべてを読む必要はないのだが、面白そうなのでつい手が伸びてしまう。清張のわんこそば状態だ。
その中の一冊に、『松本清張推理評論集1957-1988』(中央公論新社、以下『推理評論集』)がある。
清張は小説、ノンフィクション、古代史論など多くの分野で活動したが、エッセイは数少ない。同書には『随筆黒い手帖』(中公文庫)や『松本清張全集』(文藝春秋、以下全集)にも未収録の推理小説についての文章が網羅されている。
社会派推理の誕生
1953年、松本清張は「或る「小倉日記」伝」で芥川賞を受賞する。当初は直木賞候補だったが、「芥川賞候補作として扱うべき」という永井龍男(直木賞選考委員)の意見により、芥川賞に回されて受賞した(永井『回想の芥川・直木賞』文春文庫)。その後数年は歴史を題材にすることが多かったが、1955年の「張込み」、翌年の「顔」あたりから推理小説を書くようになる。この二編を含む短編集『顔』で日本探偵作家クラブ賞を受賞している。
そして、1957年に『点と線』と『眼の壁』の連載が始まり、翌年刊行されると、ベストセラーになった。
清張は十代の頃から江戸川乱歩を愛読したが、推理小説の現状には不満があった。「謎解きやトリックなどに凝っている一部の「鬼」と称する読者相手のパズル的遊戯になり下ってしまった」からだ(「日本の推理小説」、『随筆黒い手帖』)。「鬼」と呼ばれる一部のマニアが満足するような作品ばかりが生まれ、一般の読者が推理小説から離れていったのだと主張する。
清張は、自分が読みたい作品を自給自足的に書きはじめる。
「私は自分のこの試作品のなかで、物理的トリックを心理的な作業に置き替えること、特異な環境でなく、日常生活に設定を求めること、人物も特別な性格者でなく、われわれと同じような平凡人であること、描写も「背筋に氷を当てられたようなぞっとする恐怖」の類いではなく、誰でもが日常の生活から経験しそうな、または予感しそうなサスペンスを求めた。これを手っ取り早くいえば、探偵小説を「お化屋敷」の掛小屋からリアリズムの外に出したかったのである」(同)
清張は推理小説において、トリックよりも動機を重視すべきだと繰り返し述べた。そうすることによって、人間を描くことができるからだ。
「殊に、現代のように、人間関係が複雑となり、(略)人間は或る意味において個として孤立している状態では、推理小説の手法は最も活用されてよい。その場合には、リアリティの附与が益々必要だと思うのである」(「ブームの眼の中で」、『推理評論集』)
そのため、清張は絵空事を排して、日常の中に潜んでいる犯罪や、誰の身にも起こりうる危機を描いた。登場人物には政治家や官僚など社会的地位が高い者も多いが、彼らが犯罪を起こす動機はたいてい卑近であり、その点ではわれらの隣人なのだ。
「清張以後」という言葉があるように、清張に影響を受けた作家がリアリティを重視する作品を発表するようになり、それらは「社会派推理」と呼ばれた。しかし、水上勉『飢餓海峡』など数作を除けば、いまはあまり読まれていない。清張は社会派推理の創始者にして、孤独な頂点であったと云える。
限界に挑戦する
動機を重視すべきと云いながら、清張はトリックや意外性を軽視したわけではなかった。推理小説では着想が大事で、それをどう発展させていくかに苦心するという。「だから、推理小説は、依頼を受けてから着想を考えるべきものではない!」と述べる(「推理小説のヒント」、『推理評論集』)。
実際、清張は「創作ノート」を付けており、そのメモをヒントにいくつもの作品を生み出している(「創作ノート(一)」、『随筆黒い手帖』)。
しかしその一方で、四十代で作家デビューした清張はつねに、「自分には時間がない」という思いを抱いていた。そのため、依頼された仕事はほとんど引き受けた。1959年には「執筆量の限界をためそうと、積極的に仕事をしたが、その結果書痙にかかり、やむなく速記に頼ることとなった」(『新潮日本文学アルバム 49 松本清張』新潮社)。
このときから九年間、清張の速記役を務めた福岡隆は、月産千枚という超人的な仕事ぶりに驚嘆している。連載に加えて、講演や海外への取材旅行も行なった(福岡隆『人間・松本清張 専属速記者九年間の記録』大光社)。作家の平林たい子は清張を「秘書に資料を集めさせて書く、人間タイプライター」だと発言しているが、実際にはほとんど自分で調べていた。
自ら望んだこととはいえ、このような仕事量をコンスタントに、かつハイクオリティでこなすのは不可能だ。
『点と線』は「旅」に連載されたが、清張の原稿は他の記事が校了したあとも入らず、「清張待ち」という言葉が生まれた。雲隠れされたこともあるが、発行元が日本交通公社だけにネットワークを駆使して、羽田空港で離陸寸前の清張を捕まえたというからすごい(戸塚文子「『点と線』の頃」、文藝春秋編『松本清張の世界』文春文庫)。
また、『ゼロの焦点』は1958年に「太陽」で連載開始するが、休刊のため中断。江戸川乱歩が編集に携わった「宝石」で再開するが、数回で休載する。同誌は窮余の策として、清張と乱歩の対談を載せた。清張は「できるだけ本格の読者にも満足してもらいたい」と苦心しているため遅れたと言い訳し、大先輩の乱歩に「編集者にも同情していただきたい」と釘を刺されている(「対談・これからの探偵小説」、『推理評論集』)。
清張は謎解きやトリックが中心となる短編を晩年まで書いたが、長編に関しては1965年連載開始の『Dの複合』を境に、推理小説というよりはサスペンスや風俗小説の色が濃くなっていく。視野が広がったこともあるだろうが、大量の仕事の中で、自らが満足するようなアイデアを考える時間がなくなったからではないか。
新潮社の清張担当の編集者は座談会で、「書き出しのうまさは定評があったんだけど、編集者同士では、「終わり方がちょっとね」と(笑)」「次に書きたいことの方に関心が移っていくんですよ」と発言している(「私だけが知っている清張先生」、「小説新潮」2009年5月号)。そのため、単行本にまとめる際につじつまの合わない点が多く出た。
清張の作品はタイトルがいいと云われるが、これも多作と関係している。
「こういう抽象的な題名をつけるのは、実は締切りと関係があるのです。(略)ことに連載ものとなりますと、締切り前に予告というものが出ますので、題名を一応作らなければいけない。しかし筋はまだできておりませんので、どんな小説になってもいいような題名をつけておく。中身がないのだから、題名はつい抽象的になってしまう。それがすばらしいと褒めてくれるのであります」(「推理小説の題材」、『推理評論集』)
講演でのリップサービスとはいえ、ぶっちゃけすぎじゃないでしょうか、清張先生! 『砂の器』も『霧の旗』も『けものみち』も締め切りから生まれたものだったとは……。もっとも、そんなつけ方でも読者にはこれしかないと思わせるのがすごいのだが。
以下、長編二十二作を私なりに七つに分類して見ていく(カッコ内は初刊年。ゴシックの作品は新潮文庫収録)。
(1)人間を描く推理小説
新潮文庫に収録された清張作品を、売上げ部数から順位をつけると、1『砂の器』、2『点と線』、3『ゼロの焦点』、4『わるいやつら』、5『張込み』となる(上下巻の場合はその合計)。いずれも映像化が多く、知名度も高いので、納得の順位だろう。
上巻と下巻を別に数えて、一冊あたりの売上げ部数を出すと、一位は『点と線』(1958年)で百四十刷、三百二十二万部となる。同作はそれだけ多くの人に長く読まれてきたのだ。
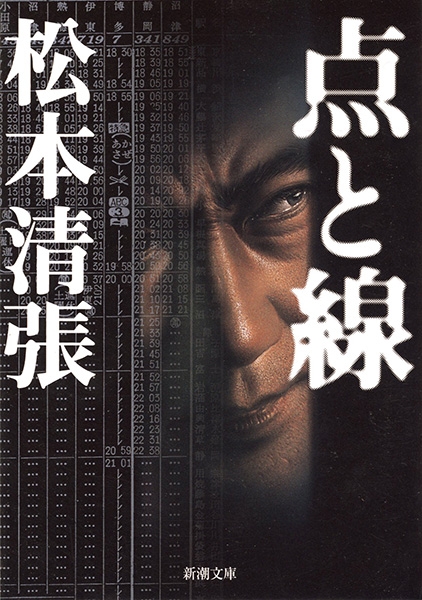
ストーリーも有名だ。福岡県の香椎の海岸で、男女が寄り添った死体が発見される。男は某省の課長補佐で、女は料亭の仲居だった。心中と判断され捜査は打ち切られるが、疑問を抱いた香椎署の鳥飼刑事は、警視庁の三原警部補と組んで事件を解明する。
心中説の根拠となったのが、その男女が東京駅から一緒に乗車するところを目撃されていることだ。十三番線のホームから十五番線のホームに停車している列車を見通せる時間は、わずか四分しかない。その目撃はあらかじめ仕組まれていたのではないか……。東京、福岡、札幌と移動が多く、容疑者のアリバイ崩しが主眼となる。
冒頭に出てくる香椎には国鉄(現JR)と西鉄の駅があり、両者の間は五百メートルほどしか離れていない。その間の通りを夜に歩いていた男女が目撃される。女が漏らした「ずいぶん、寂しい所ね」という言葉に惹かれて、私も香椎を訪れて同じ通りを歩いてみたが、そんな風情はなかった。ちなみに、2021年に香椎で開業した個人書店の店名は〈テントセンブックス〉。店内には『点と線』ほか清張作品が並んでいた。
容疑者である安田の妻は、肺結核で病床にある。彼女が同人誌に書いた「数字のある風景」という随筆には、時刻表を開くと未知の地を旅した気分になるとある。これは清張自身の感慨でもあった。
「いろいろな事情で旅が不可能な場合、どうしてその要求を満たすべきか。そういう時、私はよく図上作戦をやる。地図を拡げて、その上をたどりながら、自分が実際にその土地に旅行したような空想にふけるのである」(「楽屋裏の話」、『随筆黒い手帖』)
安田の妻は「汽車の交差は時間的に必然だが、乗っている人びとの空間の行動の交差は偶然である。私は、今の瞬間に、展がっているさまざまな土地の、行きずりの人生をはてしなく空想することができる」と書くが、これも清張自身が考えたことだと認めている。
推理小説において日常性を重視した清張は、いわゆる「名探偵」を出さなかった。探偵役となるのは、刑事か新聞記者、カメラマン、作家、編集者などが多い。いずれも調べることを仕事とする職業だ。同じ主人公が登場する作品もない。その例外が『時間の習俗』(1962年)で、『点と線』と同じ三原・鳥飼コンビが事件を捜査する。
これについて清張は、『点と線』と同じ「旅」で連載することから、「やはりなじみの人物が登場した方がいいんじゃないか」と考えたという(「一人の芭蕉」、『推理評論集』)。

相模湖畔で起こった殺人事件の容疑者・峰岡は、その日、門司市で行なわれた和布刈神事を見学したというアリバイを持っている。峰岡は神事の様子をカメラで撮影しており、その後入った旅館の女中も撮っている。三原はここにトリックがあるのではと考える。
清張は昭和12、3年から写真を撮っており、取材にはいつもカメラを持参した。『松本清張カメラ紀行』という著書があるほどだ。本作でも、神事の夜間撮影やカラーフィルムの現像のことなど詳しく描かれている。
『ゼロの焦点』(1959年)でも、写真が印象的に使われる。禎子は十歳上の夫と結婚するが、新婚旅行から戻って十日後に夫は赴任していた金沢で姿を消す。北陸に向った禎子が手掛かりとしたのが、二枚の写真だった。

禎子は変死体発見の知らせを受け、能登半島の漁村へ向かうが、夫とは別人だった。彼女が断崖に立つ場面は印象的だ。
「なぜここに自分が立っているか、禎子には合理的な説明ができない。とにかく、海が鳴っているという断崖の上に立ってみたかったのだ。北陸の暗鬱な雲とくろい海とは、前から持っていた彼女の憧憬であった。(略)陽は沈みきった。鈍重な雲は、いよいよ暗くなり、海原は急速に黒さを増した。潮騒が高まり、その上を風の音が渡った」
本作に限らず、明るい風景よりも暗く、陰鬱な風景を描くときに清張の筆は冴える。
禎子のあとに金沢にやってきた夫の兄が何者かに殺され、夫の会社の社員も東京で殺される。禎子は夫がかつて警官として勤めていた東京の立川に行き、ある女性の過去を知る。一連の事件はそのために起こったのだ。
「いわば、これは、敗戦によって日本の女性が受けた被害が、十三年たった今日、少しもその傷痕が消えず、ふと、ある衝撃をうけて、ふたたび、その古い疵から、いまわしい血が新しく噴きだしたとは言えないだろうか」
同作は1961年に野村芳太郎監督で映画化。禎子と過去を持つ二人の女を、久我美子、高千穂ひづる、有馬稲子が好演した。犯人が崖の上で告白するクライマックスは、のちにテレビのサスペンスものの定番となった。2009年には犬童一心監督で再映画化されたが、こちらは広末涼子、中谷美紀、木村多江が演技の火花を散らした。同作は現在のところ、最新の清張映画である。
一方、『眼の壁』(1958年)は、冒頭で三千万円の手形詐欺が発生する。これは検事から、捜査一課ばかりでなく、詐欺や恐喝などの知能犯を扱う二課の仕事を書いてみたらとアドバイスされたことを受けて生まれたという。詐欺の責任を取って自殺した会計課長の部下の萩崎が、友人の新聞記者・田村の協力を得て、犯人の跡を追ううちに、殺人事件が起こる。

政界のフィクサーである舟坂の存在、宗教的な集団の関与などが、不気味な雰囲気を高める。萩崎は怪しい荷物を追って木曾路を動き回るし、ラストには清張には珍しく、直截的でショッキングな描写がある。他の作品と比べて、非常にテンポの速い作品だ。
なお、本作は今年六月にWOWOWでドラマ化された。小泉孝太郎演じる萩崎が事件に巻き込まれていく様がリアルに描かれていたが、後半はかなり改変されていた。私としては、1958年の映画版(大庭秀雄監督)がチープさも含めて好きだ。
(2)旅情を味わう
清張の作品は、日本全国、ときには海外の土地が舞台となっている。
新潮文庫ではないが、恋愛小説の『波の塔』(1960年)の舞台となった深大寺には、若いカップルが急増したという。また、同作のラストに倣って青木ヶ原樹海で自殺した女性も出た。『ゼロの焦点』でも、能登の断崖から飛び降りる女性が増えたため、清張の短歌を刻んだ碑を建てて自殺を防ごうとした。それだけ強い印象を残すのだろう。
清張は一度訪れたことのある土地を小説に出すことが多かったが、「いわゆる実地取材」には行かなかった。
「後で実際に小説を書く場合、地形などは地図によってたしかめるが、その際、五万分の一の地図は最も有益である。だが、再度の実地調査をしないために細部で多少のズレが起る。しかし、それでも、私は最初のイメージを大切にするため二度目の取材訪問はしないようにしている」(「推理小説と旅」、『推理評論集』)
『眼の壁』でも読者の指摘を受けて、風景の描写を直している。
『Dの複合』(1968年)は、旅と清張の得意とする古代史や民俗学を組み合わせた長編だ。あまり売れていない作家の伊瀬は、新しい雑誌から「僻地に伝説をさぐる旅」という連載を依頼される。伊瀬は担当となった浜中の案内で、浦島伝説の残る丹後半島に取材に出かける。浜中はなんらかの意図を持って、取材地を決めているようだ。その後向かった明石の神社で会った坂口みま子は一種の数字狂で、伊瀬の旅の距離が三百五十キロであることに意味があると述べる。そして、殺人事件が発生する。
読者は伊瀬や浜中とともに、丹後、紀州、静岡、鳥取、成田などを旅し、その土地の伝説や風習に触れることができる。旅行ガイドのように読んだ読者も多かったのではないか。
主人公が古来の伝説や神話の謎を探ろうとする物語は、小説では半村良の伝奇SFや高橋克彦らの歴史ミステリ、漫画では諸星大二郎の「妖怪ハンター」シリーズ、星野之宣の『宗像教授伝奇考』などの源流と云ってもいいだろう。

作中では「三五」「一三五」という数字が意味を持つ。長編『数の風景』(1987年)にも、本作のみま子とそっくりな数字狂の女性が出てくる。また、短編「東経一三九度線」(『巨人の磯』)も、古代の神社と経度を結び付けている。ホントかなと疑いつつ、次第に引き込まれてしまう。
もっとも、北緯三五度と東経一三五度を英語で書くと、四つのDが重なるから「Dの複合」だとする説明はさすがに苦しい(頭文字じゃないDもあるし)。この解釈も後付けだったのだろうか?
それと、犯人のある行為の意味について、「いわば、それはこの事件の雰囲気づくりのようなものです」と説明したのには笑った。そう云ってしまったら、何でもアリなんじゃないか。
作家が編集者に引っ張りまわされる同作に対して、編集者が作家に翻弄されるのが『蒼い描点』(1959年)だ。

雑誌編集者の椎原典子は、作家の村谷阿沙子の原稿をもらうため、箱根に出向く。そこで出会ったライターの田倉が不審な死を遂げ、阿沙子の夫も姿を消す。阿沙子は著名な学者の娘で、懸賞小説でデビューして売れっ子になったが、最近はあまり作品を発表しないでいる。彼女は小説を書いている姿を絶対に人に見せない。典子は、同僚の崎野とともに阿沙子の秘密を探ろうとする。
阿沙子は原稿が書けないまま、「坊ヶ島」温泉に移る。そこは谷底にあり、二軒の旅館がそれぞれケーブルカーを持っている。このケーブルカーが鳴らすリン、リンという音が、夜に響く描写が美しく、旅情を感じさせる。
このモデルは堂ヶ島温泉である。清張は「書くことがなくて困って、とにかく箱根にいってね、(略)偶然に入ったところがケーブルカーでおりる旅館でしてね」と述べている(「一人の芭蕉」)。いまでも旅館はあるが、ケーブルカーは現在運行されていないようだ。
村谷阿沙子は実力もないまま、自分を偽って世に出ている。彼女はヒステリックで傍若無人な女として描かれている。「肥えた顔」「小さい目と低い鼻とをのんびりと持った」「鼻翼に脂をうかせて闘志に満ちた表情だけれど、次の作品もかならず流れる」など、情け容赦がない。
つくられた「天才」という点で共通するのが、『天才画の女』(1979年)だ。銀座の画廊に売り込みに来た降田良子の絵がコレクターに評価され、一気に個展を開くまでに至る。『蒼い描点』の阿沙子と同じく、良子もアトリエで絵を描く姿を絶対に見せない。良子を推す画廊のライバルである小池は、良子の故郷・福島を訪れる。ここでも町のカメラ店が重要な役割を担っている。
なお、郷原宏は阿沙子と良子の関連性を指摘し、こう書く。
「清張作品にあって「――の女」と名指される女たちは、なぜかいつも三十歳前後で、よくいえば個性的、ありていにいえばあまり美しくないという共通点を持っている」(「〈赤い鰊〉の群れる海」、「松本清張研究」第四号、2003年3月)
また、贋物の才能という点では、『渡された場面』(1976年)も同様だ。下坂が九州の同人誌に発表した作品が文芸誌で激賞されるが、その描写はある作家の原稿を写したものだった。その作家は、清張が敬遠したタイプの私小説作家として描かれている。下坂がある場所に近づきたくないと思いながらも、偶然によって引き寄せられていく様は、いかにも清張的だ。
(3)組織と個人
会社や官庁などの組織と一個人の関係は、多くの読者にとって他人事ではない問題だろう。清張の長編にはこのテーマを扱う作品が多い。
『渦』(1977年)は、タブーとされてきたテレビの視聴率調査に真っ向から挑んだもの。

劇団主宰者の古沢の元にある女性からの手紙が届く。彼女の兄はテレビ局のプロデューサーだが、視聴率が悪いため現場から外されたというのだ。しかし、その視聴率を算出するためのモニターはどうやって決められているのか? 疑問を抱いた古沢は、友人のプロダクションの社員らにサンプル世帯の実態調査を依頼する。
本作のきっかけは、作中と同じような手紙が清張に届いたことだった。
「テレビ局を一喜一憂させ、プロデューサーのクビにもかかわるという視聴率もモンスターなら、サンプル家庭の存在もまた幽霊の如きものである」(「着想ばなし」第二回、全集第四十巻月報)
同作は「日本経済新聞」に連載中から話題となり、「ある週刊誌は本編をヒントに、視聴率調査会社のテープ回収員を尾行することによって“視聴率調査の徹底全調査”なる特集記事を企画したりもした」という(佐藤精「解説」、『渦』)。
『蒼ざめた礼服』(1966年)は、ある経済研究所に入社した主人公が、好奇心が赴くままに謎を探る。その過程で所長の柿坂が特殊潜水艦の建造計画に関わっていることが判り、殺人事件も絡む。
それにしても、古本屋で買った雑誌を百数十ページ複写するのに、専門の業者に頼むと一晩かかって、代金が一万二千円というのは、時代を感じる。
『歪んだ複写―税務署殺人事件―』(1961年)は、東京の郊外で発見された身元不明の死体をめぐり、新聞記者の田原が調査を行なう。その男は元税務署員で、脱税に絡む収賄事件で退職したのだ。田原が男の上司たちを追ううち、新たな殺人事件に遭遇する。
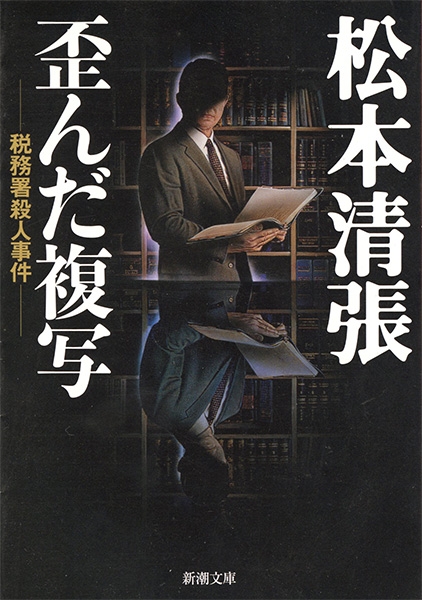
何度も文壇長者番付一位になった清張は高額納税者であり、「税金のとりやすいところは締めつけてしぼる。とりにくいところは知らぬ顔」という国税庁のやり方に不満を抱いていた(「現代のヒズミ――税金」、全集第三十四巻)。そのため、本作に登場する税務署員は署長から末端に至るまで全員が悪党だ。
なお、最初に死体が発見されるのは、中央線・武蔵境駅から北に二キロの、「武蔵野の林と畑のひろがっている場所」だ。中央線、小田急線、西武新宿線など東京の西に向って走る鉄道の沿線は、清張が犯罪の舞台に多く利用した地域だ。『影の地帯』では国立の雑木林から、「礼遇の資格」(『巨人の磯』)では武蔵境の廃車から死体が発見される。清張作品で武蔵野は出てくれば人が殺される「お約束の場所」なのである(『松本清張 黒の地図帖』平凡社)。
このほか、『状況曲線』上・下(1988年)は建築業界の談合による官庁との癒着を、『喪失の儀礼』(1972年)は製薬業界と癒着した医学界を暴き出している。
(4)社会の暗部
清張の作品には、表面からは見えない社会の暗部を描くものが多い。『昭和史発掘』などのノンフィクションで、実際に起こった事件を描いた清張だけに、小説であってもその描写にはリアリティがある。
『影の地帯』(1961年)は、カメラマンの田代が飛行機の中で若い女性と、その連れの男に出会ったことから、奇妙な事件に巻き込まれていく。田代が友人のカメラマンや新聞記者の協力を求めることや死体の処理方法など、いくつかの点で『眼の壁』と似ている。しかし、展開の早い『眼の壁』に比べて、闇の力がじわじわと迫ってくるような怖さがある。
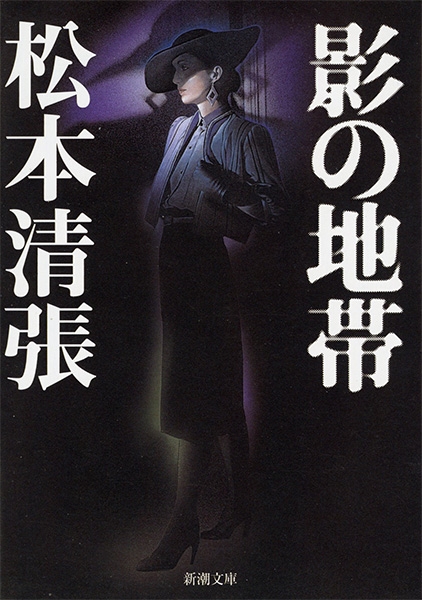
「あたりの景色はおだやかだった。/だが、この平和の奥に、まだまだ見えない黒い影が傲慢に存在し、それが目に見えないところから、現代を動かしているのだ」
あったはずの建物がいつの間にか消えているというパターンが繰り返されるのも、恐怖心を増す。
『黒い福音』(1961年)は、1959年に起きたスチュワーデス殺人事件を題材にしている。この事件ではカトリック教会のベルギー人神父が容疑者とされたが、教会側は出頭に応じず、その神父を帰国させてしまった。

清張はこの事件に関心を抱き、「スチュワーデス殺し事件」というルポを発表(『随筆黒い手帖』)したあと、「週刊コウロン」で『黒い福音』を連載した。事件から八カ月というスピードだ。犯罪が発生するまでを第一部とし、推理編にあたる第二部は『燃える水』という題名で連載された。
作中のグリエルモ教会は、下井草教会にあったドン・ボスコ社がモデル。教会の神父が聖書を翻訳するのを手伝うと称する女や、寄贈品を横流しする男、そして教会の権威を借りて麻薬を輸入する外国人貿易商など、怪しい連中ばかり出てくる。
『影の地帯』と同じように、本作でもクライマックスである建物が消滅する。よほど好きなパターンだったのだろう。
(5)サスペンスとメロドラマ
『霧の旗』(1961年)の主人公・柳田桐子は、殺人容疑で死刑判決を受けた兄を救うために、著名な弁護士の大塚に依頼したが断られる。兄は獄死し、桐子は上京してバーの女給となる。九州から上京した桐子は、「東京全体がくすんだ灰色で、紙の模型でも見ているようだった」と感じるが、再度上京したときにはその一員になっている。
そして、ある事件をきっかけに、桐子と大塚の力関係が逆転する。純粋で強情な桐子が大塚を追い詰めていく描写は、本人が確信犯だけに怖ろしい。本作は完璧な復讐譚であり、清張作品でも最高のサスペンスだ。
本作は二度映画化されており、1965年版(山田洋次監督)では倍賞千恵子が、1977年版(西河克己監督)では山口百恵が、美しくて怖い主人公を演じている。

『砂漠の塩』(1967年)は、清張がはじめて海外を舞台にした作品だ。主人公の野木泰子は、パリで団体旅行のメンバーと別れ、カイロで幼友達の谷口と会う。二人は愛し合っているが、どちらにも伴侶がいた。ベイルートからダマスカスへと旅した二人は、砂漠に姿を消す。
本作の取材で中近東に向かった清張は、たまたま映画祭に出席する女優の新珠三千代と同じ飛行機に乗り合わせている。清張は編集者から「好きな女性は?」と訊かれると、必ず新珠を挙げていた。「編集者たちも心得たもので、多忙な松本さんを対談に引っぱり出すときは、その相手に新珠さんを選んでいた」という(『人間・松本清張』)。清張の映画化では「寒流」「風の視線」「霧の旗」などに出演している。福岡隆は、本作で清張が新珠をイメージしながら、ヒロインの泰子を描いたのではないかと推測している。しかし、同作が「愛と死の砂漠」として連続ドラマ化された際、ヒロインを演じたのは小川眞由美だった。
(6)弱い男と強い女たち
『わるいやつら』、『けものみち』、『黒革の手帖』、『夜光の階段』は、主人公の男や女が自己の欲望を実現するために、悪に手を染めていく点で共通している。この四作はいずれも上下巻と長いが、展開が早いので一気に読めてしまう。
『わるいやつら』(1961年)は、清張が初めて「週刊新潮」に連載したもの。父から病院を継いだ戸谷は、経営を放り出して、その地位を利用して女を漁る。戸谷は洋装店を営む槙村隆子と結婚するために、他の女から金を取ろうとする。女たちを操っているつもりの戸谷が、彼女たちから逆襲される展開は痛快だ。映画版(野村芳太郎監督)は、主演の片岡孝夫(現・十五代片岡仁左衛門)が松坂慶子ら女性陣に翻弄されまくる、コミカルな味があった。
『夜光の階段』(1981年)も同様で、美容師の佐山は複数の女から金を出させ、一等地に美容院を出す。有名美容師になった佐山が、出張先にやってきた二人の女の間でうろうろする場面が笑える。
『黒革の手帖』(1980年)は、銀行員の原口元子が横領した金をもとに、銀座にクラブを出す。元子は架空名義口座を記録した手帖を武器に、客の男たちを騙し、さらにのし上がろうとするが……。本作は映画化されなかったが、何度もテレビドラマ化されており、浅野ゆう子、米倉涼子、武井咲らが元子を演じた。
一連のピカレスク作品で、突出して読みごたえがあるのが、『けものみち』(1964年)だ。割烹旅館で働く成沢民子が、ホテルの支配人・小滝にそそのかされ、寝たきりの夫を焼き殺す。民子は政界のフィクサー鬼頭の家に入り、体をもてあそばれながら、鬼頭の死後の財産を狙う。そこに小滝や、鬼頭の番頭とも云える秦野、警視庁の久恒らの思惑が入り混じる。彼らのいる世界は、ずっと黒い霧に覆われているようで、どの場面も緊迫している。クライマックスの描写は特にすさまじい。連載中に「週刊新潮」が増刷したというのも納得だ。

(7)清張のすべてがある
長編二十二作の最後に紹介したいのが、『砂の器』上・下(1961年)だ。ここには、清張作品のすべての要素が入っている。
同作のストーリーは有名すぎるので省略するが、後半の映像詩で知られる映画版(野村芳太郎監督)やそれを踏襲したテレビドラマ版とはかなり違いがある。和賀英良は映画と異なり前衛的な電子音楽の作曲家であり、既成の権威を否定する若手芸術家が集まる「ヌーボー・グループ」に属している。この集まりの中心である評論家・関川重雄は徹底したエゴイストで、温和な和賀に比べて強い印象を残す。殺人の方法も映画と異なる。

事件を追う警視庁の刑事・今西は、蒲田の操車場から始まり、秋田、出雲、塩山、伊勢、石川、大阪と手がかりをつかむたびに現地に足を運ぶ。それぞれの土地が丹念に描かれる。
また、秋田でヌーボー・グループに出会う、今西の妹のアパートに重要人物がいた、などの清張的な暗合が満載だ。中央線の車窓から何かを撒く女について週刊誌のコラムで知ったり、映画館が重要な役目を果たしたりというように、メディアの使い方もうまい。
本作はまた、島根県出雲地方で使われる「出雲弁」にスポットを当てた点でも重要だ。私は小学生の時にドラマ版を観て、出雲生まれであることを誇らしく思った。舞台である亀嵩に、『砂の器』記念碑を見に行ったこともある。この作品に出会わなければ、清張を読むのはもっと遅かったかもしれない。『砂の器』は私にとっての清張の出発点であるとともに、何度も立ち戻る故郷でもあるのだ。
新潮文庫の清張作品全四十五冊を全部読んで、改めて感じるのは、清張の同時代性と普遍性だ。
いつの頃からか、エンターテインメントの作品が分厚くなった。戦前や戦時中、終戦後などさまざまな時代や状況を描く作家が増えた。資料を読み込み、取材を重ねたうえで、緻密に描かれた作品も多い。
しかし、清張の場合、ひとつひとつの場面の描写はあまり長くなく、登場人物にくどくどと説明させることもしない。それでいて、読者にきちんとその状況が伝わるのは、時代の肌感覚とでも云うべきものを備えていたからではないか。
それとともに、清張は時代を超えても変わらない、人間の本質を描いてきた。だから、登場するモノが時代遅れになっても、物語そのものは古びないのだ。
私はこれからも繰り返し、清張の作品を読み直すだろう。年齢を重ねるほどに、その味わいが深くなるのだと期待して。
(なんだろう・あやしげ ライター/編集者)
【参考文献】
志村有弘ほか編『松本清張事典 増補版』勉誠出版
北九州市立松本清張記念館編『いつもカメラを携えて――松本清張が愛したカメラとその時代』(松本清張没後20年記念特別企画展図録)北九州市立松本清張記念館

































