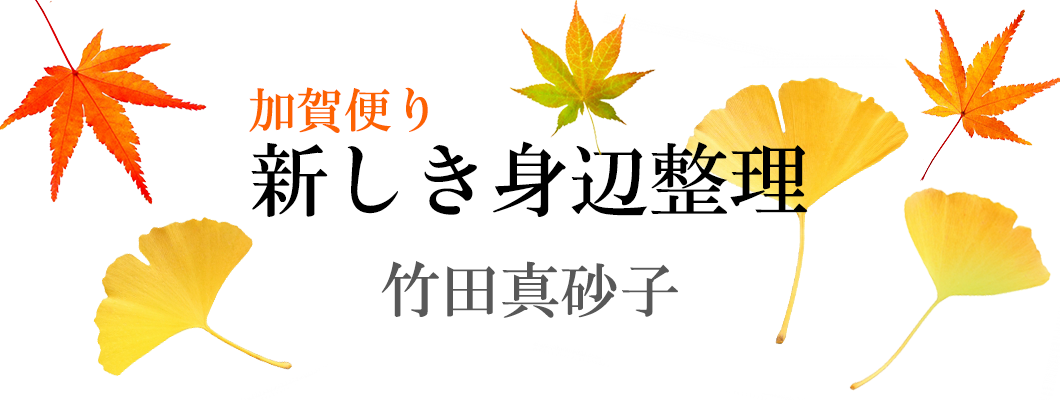今は医薬分業で、ほとんどの病院、医院が医師の指示する処方箋に従って、薬局で調剤した薬を患者に渡しますが、以前は大病院でも院内で薬の調剤をし、接続している窓口で患者に渡すのが普通でした。
そして我が家では、父の友人でありホームドクターでもあったI先生が処方し、調剤してくださるお薬を服用するのが幼いころからの習慣でしたので、よほどの大病でもない限り病院のお世話になることはありませんでした。
I先生のお世話になったのは当時住み込みでお手伝いをしてくれていた人達も含めた家族全員で、私も10代の頃、お腹が痛くなったり、熱が出たりして家中を大騒ぎさせることが何回かありました。それも大抵夜中なのです。それでもI先生は、たとえ一日の診療を終え、ご家族と食卓を囲んで団欒のひとときであっても、宴会帰りの上機嫌で床に就き、ぐっすり寝込んでいる真夜中であっても、電話一つですぐ駆けつけてくださいました。
駆けつけるといっても深夜のこと、しかもI先生はすでにかなりのお年でいらっしゃいましたし、お宅からの距離が2キロ近くありましたので徒歩というわけにはまいりません。昭和20年代から30年代初頭の頃、自家用車など所有している家庭は数えるほどしかなく、もちろん我が家もご同様でしたから、ハイヤーを差し向けることになります。そこで懇意のハイヤー会社に連絡いたしますと、こちらも真夜中にも拘らず、すぐさま出動してくれました。この頃の大人はみんな一生懸命働いていたのですね。
ところが、それまで七転八倒していた私の病状は、先生の顔を見た途端に治まってしまうのです。すると先生は一通りの診察をなさってから、ふむふむといった表情で母が差し出す銅製の手水盥(ちょうずだらい)で手を洗い、朝になったら薬を取りに来るようにとおっしゃって立ち上がります。そのあと父の部屋に移ってちょっと一杯吞み、またハイヤーでお帰りになるのが通例になっていたようでした。
お薬は基本的に一日に3回。食前に飲む水薬と食後に服用する散薬で3日分くらいだったと思います。水薬の瓶には目盛りがついていて1回分ずつコップに移して飲みます。散薬は折り紙のようにたたまれた白い紙で包まれていますが、解熱剤などの頓服は赤い紙で包んでありました。
結局、私の度重なる腹痛は虫垂炎の前兆のようなもので、妙に神経過敏な臓腑たちが些細な刺激にも反応してしまっていたらしいのです。そんなことが何回か続いた後、I先生から少し盲腸が腫れているとの診断があり、そう危険な状態ではないが、手術をしてしまうかね、と両親と私にお訊ねになりました。昔、I先生のご不在中、姉が誤診による手遅れで大変苦しんだ経験がありましたので家内全員賛成。すぐさま近くに出来たばかりの大病院で手術いたしました。至って簡単な手術でして、私のお腹の、あるかなきかの傷跡を見た姉が「えっ、こんなに小さいの!?」と仰天しておりました。あのとき、I先生さえいてくださったら、と姉は思ったに違いありません。
空襲が激しくなった戦争中も姉は肋膜炎で闘病中でした。忘れもしません昭和20年4月3日のことです。やせ細ってはおりましたがすでに14歳になっていた姉を父が背負って東京駅から東海道線に乗り、三島経由で伊豆修善寺まで私たち家族は疎開いたしました。
この移動に、ご自分にも守るべきご家族がおありですのに、しかも、いつ、どこで敵機の襲来があるかも知れないなか、I先生は同行してくださったのです。そして現地に落ち着くとすぐに病人(姉)を診察なさり、父や母が引き留めるのも聞かず、近くに知り合いがあるからと立ち去られ、翌朝再び診察に寄ってから帰京なさったのです。ただでさえ不安な家族を思いやっての行き届いた配慮であったことを、その後、我が家では語り草にしておりました。
二人の幼い姉妹を抱えている母子家庭では、往診帰りのI先生が姉妹を見舞い、母親が帰ってくるまで姉妹と共に留守番を引き受けていらっしゃったこともあったとか、往診料未払いのお家が何軒もあったとか、戦災で住む家を失い、故郷の徳島に帰るというI先生を、ご近所の方たちが手分けして住居を手配して引き留めたとか、阿波ご出身だけに殊のほか文楽がお好きだとか、逸話に事欠かない方でした。
井伏鱒二著で映画にもなった「本日休診」の三雲八春先生やTVドラマ「Dr.コトー診療所」の五島建助先生に共通する、今の医療制度および社会通念では生きにくいキャラクターでいらしたかもしれません。でも近年、病院、医院経由の処方で受け取る薬の副作用欄に目を通しますと、薬を飲まないほうが無事に生きられるような気がしてしまい、しきりにI先生のことを思い出すようになりました。
医学の進歩と人間の感情とは、逢いたいのに逢えないメロドラマの恋人たちのようなものかもしれません。

350年経過している家を移築してから50年。つまり400年前の家ですが、もちろん現役。
美術館の館長ご夫妻が守っていらっしゃいます。
本物の茅葺古民家。まるで芝居の大道具みたいです。