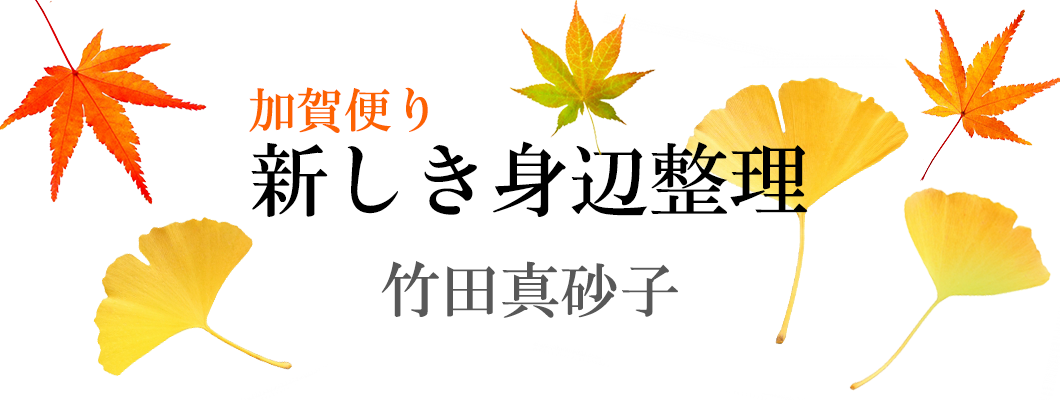1964年10月10日の東京は、前日の土砂降りの雨で大気がすっかり洗われて雲一つない青空が広がっておりました。アジアで初めて開催された東京オリンピックは、劇的な快晴に恵まれてその第一日目を迎えたのです。
とはいえ、私自身はあまりオリンピック開催について熱心ではありませんでした。大変な争奪戦が繰り広げられているという観戦チケットも、芝居のチケットほどには興味が湧きませんでしたし、競技そのものにも詳しい知識を持ち合わせておりませんでした。それでもテレビ中継くらいは見ます。なにしろオリンピックを機に家庭用のテレビのほとんどが白黒からカラーに移行いたしましたから青空もきれいに映りますし、航空自衛隊所属のアクロバット飛行チームブルーインパルスが大空に描いた五輪もひときわ鮮やかに見えました。でも私、この飛行をテレビ画面ではなく、直(じか)に見ております。自宅が国立競技場から5キロほどの所にありましたので、外へ出て空を見上げましたら澄み切った青空に五輪マークがくっきりと描かれておりました。57年前は東京都心の空も、今より広かったのですね。残念ながら今回の飛行では肝心の時に雲が出てきて、ブルーインパルスが描く五色の五輪がテレビ画面ではよく分かりませんでした。
時節柄、賛否両論あったオリンピックの開催。もちろん選手の活躍には無条件で拍手を送りますが、正直なところ私も積極的に賛成はしておりませんでした。なぜなら関係者の言動には、かなりの違和感を覚えましたし、パフォーマンスについても疑問だらけで、実際に繰り広げられたものを見ても、記憶に残るようなものが一つもありませんでした。これは当日の出演者の問題ではなく、明らかに組織委員会の人選の問題でしょう。何を基準に選んだのか、後日、反省と共にその経緯をつぶさに発表してもらいたいものです。
そこで思い出されるのが57年前のオリンピックの開会式です。年寄りの繰り言、懐古趣味と揶揄されるのを恐れずに申し上げます。
まずファンファーレが結構でした。それから選手入場時の行進曲がまた無類でしたし、五輪旗入場、掲揚時に流れる「オリンピック賛歌」も印象的でした。のちに知ったところでは、この曲は第1回近代オリンピックで演奏されたあと楽譜が消失していたそうですが、1958年にギリシャで発見され、IOC総会が東京で開かれていたために当時の都知事であった東龍太郎氏のもとに送られてきたそうです。その譜面を基に行進曲の作曲をした古関裕而氏が編曲し、それが見事な出来栄えだったので早速1960年アメリカのスコーバレーで開催された冬季オリンピックからオリンピック賛歌として復活したのだとか。今回は閉会式でソプラニスタ(男性ソプラノ歌手)の岡本知高氏が見事に歌い上げてパフォーマンス不備の印象を薄める役割を果たしてくださいました。
音楽はまだあります。格調高く力強く、この日の空のように澄み切って明るい「オリンピック東京大会賛歌」(作詞・佐藤春夫。作曲・清水脩)。「...五輪の旗やへんぽんとひるがえる...日本の秋さわやかに」
そうなのです。秋の天は高く、栄光のオリンピック旗は日本人の期待をいやが上にも搔き立ててへんぽんとひるがえったのです。「日本の秋さわやかに」この響き、57年経った今も耳に残っております。そして会場がオリンピックムードに包まれたところで天皇陛下が開会宣言をなさいました。
「第18回近代オリンピアードを祝い、ここにオリンピック東京大会の開会を宣言します」
その3か月後の正月、宮中の歌会始で翌年のお題が発表されました。お題は「声」でした。さらに次の年、歌会始に皇族の宮様方や
太平洋戦争が終結してから19年。敗戦で負った深く大きな傷跡からなんとか立ち直った日本人が、やっと日本という国の誇りを取り戻した瞬間が、この天皇陛下の開会宣言のお声だったような気がいたします。
終戦時、私は7歳でした。そして57年前は26歳でした。戦争についてもオリンピック同様、特に語れるような知識も経緯も持っておりません。しかし、この時は確かに戦禍から脱却しようとする日本を感じて、「平和」という漠然とした存在を感情的に、かつ、かなりの緊張感をもって受け止めるようになりました。
それから57年。突然襲ってきたコロナ禍の影響も、もちろんあるでしょうが、たった半世紀ほどの間に日本だけでなく、世界中が大きく変わりました。けれども世の中の趨勢がどんなに変わっても、せめてオリンピックの時だけは平和であってほしいと切に願っております。

今回の物はすべてが内面外面ともに貧弱でした。。