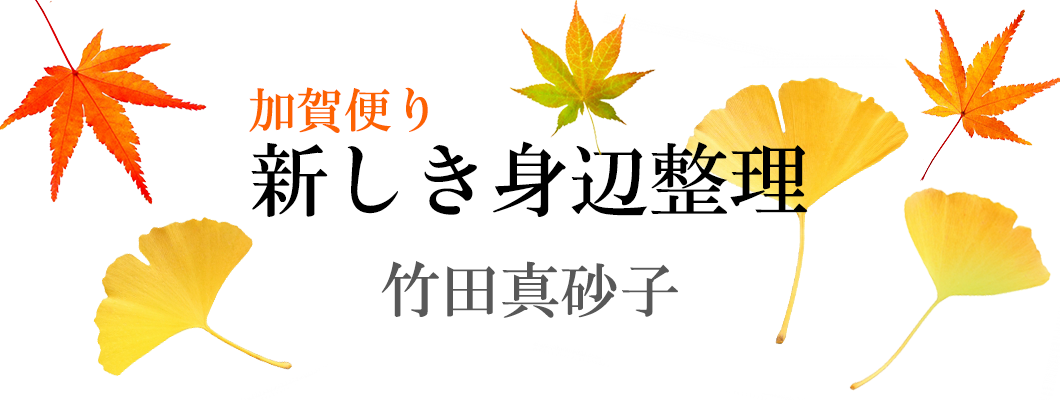オリンピックの閉会式のテレビ中継を断片的に見ました。
パフォーマンスも盛りだくさんでしたが、ソプラニスタが熱唱した「オリンピック賛歌」以外覚えておりません。ただ最後の、次回開催国フランスの映像によるパフォーマンスは圧巻でした。いろいろな楽器を使って演奏されるフランス国歌が流れるなか、パリといえばここ、とほとんどの人が知っていると思われる町並み、建造物を驚くようなアングルで映し出し、そこを全速力で自転車が縦横無尽に走り抜けてゆくという卓抜な演出に目を奪われました。国歌が宇宙空間からトランペットの演奏で流れる映像も実にさりげなくて、感激すると同時になんとなく情けない気持ちにもなってしまいました。なぜって、二国の文化に対する意識の差が歴然としていたからです。
今を去ること14年前、私たちは無謀にもパリの小劇場で自前の芝居を打つという大冒険を企画いたしました。私たちというのは前々回(加賀便り第76回)に登場したMさんとSさんに私、それにもう一人演出家のOさんで当時60代の女性ばかり4人。そのきっかけとなりましたのは、かなり前に東京のある劇場で谷崎潤一郎作『春琴抄』を不肖私の脚色によって上演された朗読劇「春琴抄」でした。スタッフ、キャスト共にかなり贅沢な舞台だったことが引き金になったのか、突然、私は自分でも思いがけないことを口にしておりました。
「この作品を邦楽でフランス語でフランス人でフランスでやりたい」
日本では映画の場合、ごく稀な例を除いては時代劇でもバックに流れる音楽はほとんど洋楽器を主体としたものですし、舞台でも伝統芸能以外は大体同様の演出が行われています。でも、西洋映画のバックミュージックに邦楽器が使われることは(特殊な例を除いて)まずありません。私は外国人による外国語の芝居にぜひ邦楽を溶け込ませたいと長年、願っておりまして、特に、フランス語なら琴、三弦との共演が可能なのではないかと思ったのです。しかも題材は大谷崎の「春琴抄」。
「やろう!」
あっさりと相槌を打ってくれたのは、この公演を見に来ていたSさんでした。彼女はご主人の転勤に同行して欧米の各地を巡りつつ二人のお子さんを育て上げ、ご自身もペーパークイリングというヨーロッパ由来の手芸を会得して多くの門下生を育て上げた経歴を持つ、自称"専業主婦"です。直ちにその場で台本の翻訳はソルボンヌ大学で演劇学を学び、すでに40年現地で暮らしているMさんに決めてしまいました。勉強家のMさんのこと、改めて谷崎潤一郎を勉強し、昔の大阪の
資金は4人の
でも面白かった。なぜなら、お陰様でゲネプロの評判がよく、日を追うごとにお客様の入りがよくなっていって、当日券売り場の窓口に行列ができましたし、劇場の支配人が「ほら、今日の売り上げですよ」と、なにやら数字が書き連ねてあるノートを見せてくれたりしたこともありました。それから劇場との正式な契約書を交わしたのはセーヌ川の畔のカフェテラスでしたが、この時は歌舞伎式の手打ちで支配人と「おめでとうございます」を言い合いました。
もう一つ、うれしくて有難かったことは、Mさんの紹介だったこともあってホテルの方々が皆さん細々と便宜を図り、気兼ねなく過ごせるようにしてくださったことです。そして代わる代わる劇場に足を運んでくださいましたし、初めて聴いたという琴、三弦の音色を、もっと聴いていたい、とうれしい感想を聞かせてくださったのです。
さらに4週間近くの滞在を終えて帰国するとき、ホテルのオーナーが放った「フランス人の知らない文化を教えてくれてありがとう」の一言。
私たちのハートはこの一言に鋭く射抜かれてしまいました。残念ながら日本人の多くは、伝統芸能というと「わからな~い」「だせェ~」だから「見たくな~い」で終わってしまうのです。
日仏の文化への認識の違いをつくづく感じたあの時のことを、改めて思い出させてくれた今回のオリンピックでした。

細い紙をくるくる巻きながらパーツを作っていきます。
写真は、さくらいたえこさん提供。