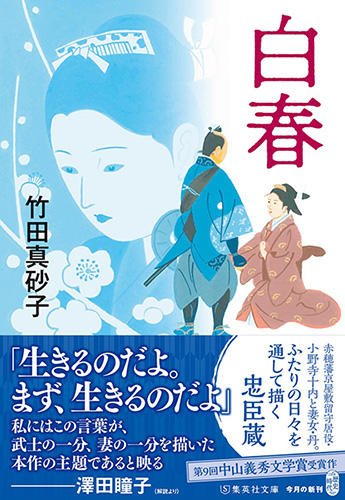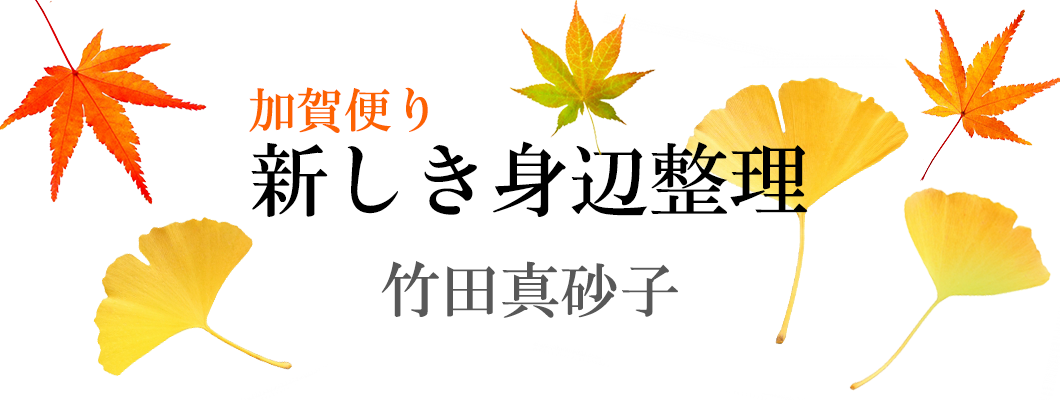今年の中秋の名月はお天気に恵まれました。空の東の端に浮かんだばかりの満月は、澄んだ夜空の所どころに漂っている叢雲を月光で染めて、見事なオブジェを描き出しておりましたし、その雲が通り過ぎると、遠い遠い、なん百光年か離れているのであろう辺りに分散するスターダストの存在を、地上から見上げる人間の目にまで届けてくれておりました。
驚いたのは、夜も更けてきた時刻、我が家の2階の窓から中天にさしかかる月を眺めたときです。近くの空き家の屋根がスポットライトを浴びたように光っていて、その源である満月から放たれている光がなんと二重の十字を描き、その縦の光線は真っ直ぐ地面にまで届いていたのです。
今まで見たこともない不思議な現象に、慌ててお隣にお住まいの宮司さんご夫妻に電話をかけました。
「早くいらしてください! 消えちゃうといけませんから」
私、虹を見たときのような急いた気分におりました。
すぐに駆けつけてくださった宮司さんは、シャッターを2、3回きってから、なにかに気がおつきになったとみえ、窓の網戸を
外国でも月を愛でる行事があるそうですが、概ね派手にお祭り騒ぎをすることが多いようです。日本のように
元来、農業国である日本の1年は田植えに始まり、稲刈りで終わる農作業を中心に営まれてまいりました。旧暦8月15日は現行の太陽暦になおすと9月中旬から10月初めの頃にあたります。丁度、1年に1度の大仕事を終えてほっとする時期ですね。気候的にも暑からず寒からず、空気は澄んでいるし、木々はたくさん実をつけているし、束の間訪れる穏やかな憩いの時間です。この貴重な時間の主役に日本人はお月様を選んだのですね。そして、自分たちの宴にお月様を招くことを思いついたのです。
おもてなしのお膳には、まずお月様が立ち寄りやすいように
この
太陽暦は4年に1度閏年があって、2月が1日増えますが、旧暦は大体3年ごとにひと月まるごと増える閏月があります。元禄15(1702)年は8月が閏月でしたから中秋の名月が2度ありましたし、享保14(1729)年には閏月が9月でしたので、栗の形に似ているところから栗名月ともいわれる13日の後の月を、2度愛でていたと思われます。
『障子から 押あふ顔や 後の月』
あ、お月様きれい、と障子を開けて誰かが叫ぶと、どれどれ、と居合わせた何人かが顔を出した光景を、お月様から見た「加賀の千代女」の一句です。
『お月様いくつ、十三、七つ まだとしゃ若いな』
これは古くから伝わる童謡の一部ですが私は子どもの頃、勝手に13+7=20で足し算の歌だと考えておりました。正確には意味不明だそうです。
邦楽・清元節の名曲『玉兎』は満月の中でお餅をついていた兎が
〽お月様さえ嫁入りなさる 年はおいくつ十三、七つ ほんにお若いあの子を生んで 誰に抱かせましょ お萬に抱かしょ
本来の童謡は、この先、しりとり歌のようになって裾野を広げていきますので結果的に意味不明になりますが、お月見がいかに日本人の心の平安を保ってきたかという証拠ではないでしょうか。
心がささくれ立つような出来事が続く昨今ですが、満月には餅つきをする兎がいると見た昔の日本人の豊かな感性に、少しばかり誇りが取り戻せるような気がしてくるのです。

【お知らせ】
竹田真砂子さんの新刊『白春』が、集英社文庫より刊行されました。
2003年に第9回中山義秀文学賞を受賞した名作です。
主人公は、捨て子で身寄りもなく、耳が聞こえない娘・ろく。
赤穂藩の京都屋敷留守居役、小野寺十内夫妻に仕える、下働きの女性です。
日々、ご主人夫妻と赤穂藩のため、真摯に仕えています。
しかし、二十歳になったとき、はるか遠い江戸城内で発生した刃傷事件のため、「御家断絶」という未曽有の事態に......。
このとき、彼女が抱いた思いとは。
障がいを持つ下働きの女性の視点で描かれる赤穂事件。
うつくしい日本語と静かな筆致のなかから、「何か」がこみ上げてくる、著者渾身の歴史小説です。
ぜひ、お読みください。
解説は、先ごろ『星落ちて、なお』で直木賞を受賞した、澤田瞳子さんです。
(新潮講座事務局:RM)