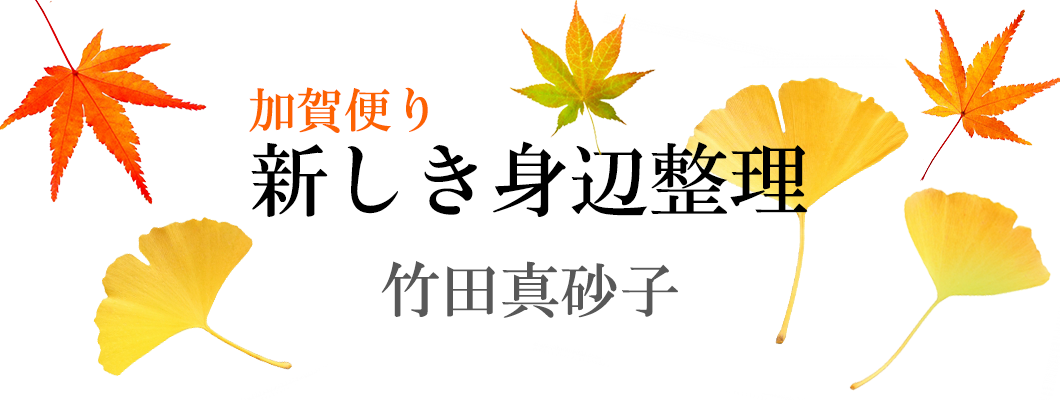古来、日本人の主食は「米」とされてまいりましたが、近年はその地位をパンにとって代わられたと何かの記事で読みました。かくいう私も朝食は何十年も前からパン食でございますが、一日三食の内1回はお米のご飯を食べます。炊き立てのご飯の魅力は、どんな美味、珍味にも勝りますもの。
そのお米の成長を、日々目の当たりに出来る環境に移り住みまして、この10月で満4年が経ちました。その直後から始めた「加賀便り」も4年が過ぎ、5年目に入ったわけでございます。月日が経つのは早いと申しますが、新型コロナウイルスの侵入を受けてからの月日の経過は特に早かったように思われます。昔も今も一日は24時間のはずですのに。
メーテルリンクの『青い鳥』に、来年こそクリスマスのおじいさんが贈り物を届けてくれるだろうと期待するチルチルとミチルが、でも「来年は遠い」と思う
そんな戸惑いが日常茶飯事になっている10月のある一日、コロナ禍発生以来途絶えていた東京行きを1年7か月ぶりに再開いたしました。大事をとって移動範囲を極力狭めた一泊旅行です。一番の目的は米寿を迎えた女性舞踊家、尾上菊保さん、尾上菊見さんお二人が主催なさる「菊壽 二人会」でした。
当日のプログラムの「ごあいさつ」によれば、お二人は『幼少より日本舞踊のお稽古を始め、戦時下でありながらも踊っておりました』という幼少時を過ごし、『一世を風靡なさった初代尾上菊之丞師に憧れ』て入門なさって以来のお付き合いとか。数えきれないほど舞台を踏み、華やかな舞踊人生を過ごしていらっしゃったお二人ですが、数え年八十八になった今年『精一杯の舞台をつとめ』たいと、この会を企画なさったそうです。お二人はそれぞれ大作と小品と二番ずつ選んで当日の出し物となさいました。
日本舞踊についてあまり詳しくない方は、ゆったりとした動きをご覧になると「簡単だ」と、お思いになるかもしれませんが、意外なことに日本の踊りは、体中の筋肉を隈なく激しく使うものなのです。因みに足をそろえて立ってから、膝を曲げながら姿勢を崩さずに静かに体を沈めて座ってみてください。次にその姿勢から手を使わずに立ち上がってください。お出来になりましたか?
83歳の私はストレッチや柔軟体操で、日常生活に不自由しない程度の体力を維持しているつもりですが、姿勢を正したまま座って立つだけの基本動作が出来ません。ところが米寿のお二人はやすやすとやってのけてしまうのです。お小さい時から
菊保さんが選んだのは日本舞踊の永遠のテーマ「道成寺もの」を現代人の感覚でまったく印象の違うものに作り上げた『道成寺昔語り』。せり出しの効果を最大限に活用するという舞台機構の整った大劇場でしか上演できない演目ですが、激しく燃える恋への執念から蛇体に変じた少女の菊保さんは、この大きな演出と真っ向勝負に出る勢いを最後まで崩しませんでした。
一方の菊見さんが挑戦したのは四世鶴屋南北作『
この舞台も大掛かりで、人里離れた
この複雑な内容の踊りが生半可な体力でし
「これが踊り納め」と固い決意で臨んだお二人の潔さに、その場に居合わせたすべての人々が心の底から米寿を
加賀では来年のお正月用の

(右)「菊壽 二人会」当日のプログラム。