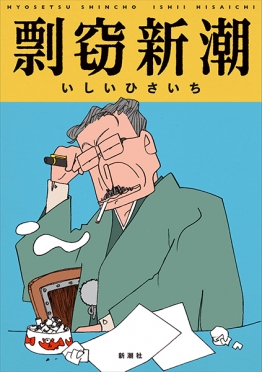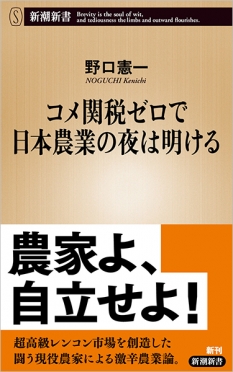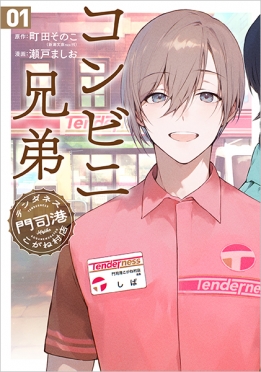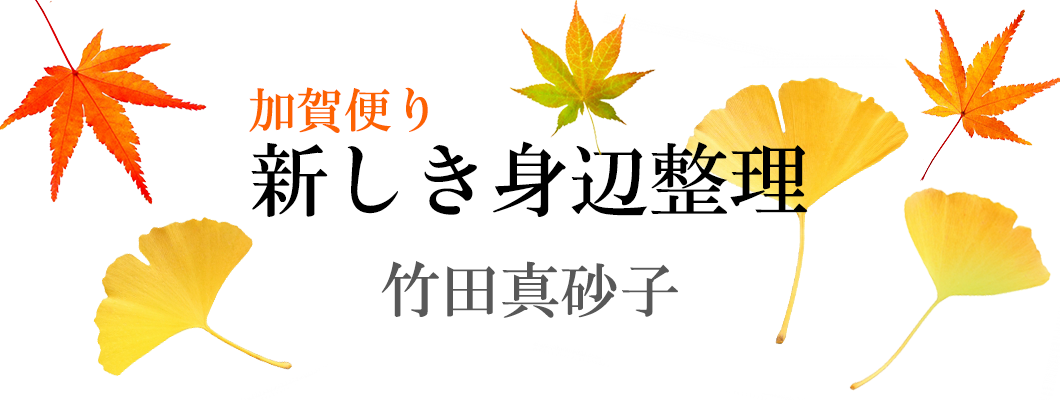令和2年7月25日19時を少々廻った刻限でした。偶々(たまたま)傍らに置いてあったスマホに「凄い虹が出ています」と知人からのメールが表示されているのに気がつき、急いで表に出て、まず西の空を見ましたら鮮やかなオレンジ色の夕焼けでした。なんてきれいな色と見とれかけましたが、いや、これは虹ではないと東の空に目を転じましたところ、ありました。宵闇が迫りつつある広い空いっぱいに七色の光が大きな弧を描いております。
神社の裏山から続くこぢんまりした森以外には視界を遮るもののない広い空に浮かぶ虹の、端から端までの大きさを、どういう単位で、どう測ればいいのか見当もつかないまま、その大きさと鮮やかな色彩に圧倒されてただ「うわー凄い!」と素っ頓狂な声をあげるばかりでした。
一番上が赤、一番下が紫。その間に橙、黄色、緑、青。七色のうち、6色まで肉眼で識別できました。「初めてです。こんなに大きくて、色鮮やかな虹を見たのは」と、叫びましたら「わたしも初めてです」と、当地の古老のS氏も同意してくださり、続いてS夫人が「きれいだけれど、不気味」と呟きました。同感です。本当に、不気味なくらい美しい虹で、そこに居合わせた4、5人は、あまり言葉を交わすこともなく、ひたすら空を見上げておりました。
7、8分も経った頃でしたか、虹は突然形を崩し始め、あれよあれよという間に宵闇に紛れて消えてしまいました。同様に西の空の夕焼けも夜の中に吸い込まれていき、あとには弓のような形をした四日の月が残っておりました。
翌日の新聞には、同じ日の朝7時頃、東京の上空では白雲が七色の光に染まるという珍しい現象が見られたという記事と写真が載っていました。その七色の光が12時間後、西に移動して大空に弧を描いたのでしょうか。虹は昼間だけでなく月の光でも見られることがあるといいますから、西の空の残光で宵の空に出現することもないわけではないのでしょうが、各地に大きな傷跡を残しながら日本列島を何度も通過していった未曽有の大雨のあとだっただけに、あまりに鮮やかな虹の出現に格別の意味を感じてしまったかもしれません。何故って、最近の気候の変動は激しさを増しているようにお思いになりませんか?
天候だけではありません、断続的に起こる地震もありますし、衰えを見せない新型コロナウイルスの跋扈(ばっこ)も並行しております。まったく思いもよらない災難が列を作って号令をかけながら前進して来るようです。その結果、私たちは、ごくありきたりの日常生活さえ有形無形に拘束されてしまう状況に陥り、先行きの見通しも立たずに不安ばかりが募っていきます。この夜の虹は、そんな私たちの心を鎮め、慰めるために、大自然が束の間見せてくれた天体ショーだったのかもしれません。
そういえば、コロナ禍の影響が大きくなり始めた3月中旬の新聞紙上に面白い記事が載っていたことを思い出しました。飛鳥時代に日本でオーロラが見られたというものです。
「キジが尾羽を広げたような扇形の赤いオーロラを聖徳太子が見たかも―。国立極地研究所、国文学研究資料館などのチームが16日までに、飛鳥時代に現れたオーロラを歴史書『日本書紀』が記録していたとする分析を発表した」(日本経済新聞2020年3月16日)
昔は地磁気の環境も違っていて日本で観測されても不思議ではなく、巨大で明るい扇形のオーロラは真夜中に現れることが多い、という説明と共に明和7(1770)年7月28日に京都から見えたというオーロラを描いた絵も添えられていました。その根拠になった『日本書紀』推古28年の条(くだり)には次のように書かれております。
「十二月の庚寅の朔(ついたちのひ)に、天に赤き気(しるし)有り。長さ一丈餘。形雉尾(きぎすお)に似たり」
この現象を見ていたかもしれない聖徳太子は、この頃、各種の公文書の基礎を作成する作業に多忙を極めていたと思われます。同時に疫病の流行も続いており、翌年12月には生母、穴穂部間人大后(あなほべのはしひとのおおきさき)を失い、さらにその翌年2月には妃の一人、膳部大郎女(かしわべのおおいらつめ)の死も見送ることになってしまいました。そして聖徳太子自身も1月に発病し、膳部大郎女が亡くなった翌日、逝去なさいます。48歳でした。
太子の死は高位高官ばかりでなく、老若男女すべての人に大きな衝撃を与え、「日月輝(ひかり)を失いて天地既に崩れぬ。今より以後、誰をか恃(たの)まむ」と嘆き悲しんだと『日本書紀』は伝えます。医学も科学も未成熟であったこの時代、政治の中枢を担える者は、疾病対策を円滑に行える者であったと言われております。治療とそれに関わる場所、人材などの確保や組織の確立に努めた聖徳太子は、まさにそれに該当する逸材だったのでしょう。
その死から来年は1400年とか。私たちは今、誰を「恃」んだらいいのでしょうか?

(写真提供/AKIHIRO)