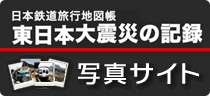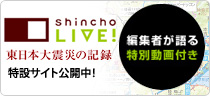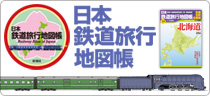この土日は3つの予定を立てていましたが、うち2つ、高崎線の撮影と鉄道模型ショーには酷暑に恐れをなして出かけず、昨日の晩にお台場の「東京カルチャーカルチャー」(外部サイトへリンク)で行われた「地図ナイト6」に行ってきました。お題は「住宅地図」。正直、このお題で人を呼べるのかと思っていました。
 開始30分前の17時半に行ってみると、ほぼ満席に近い人々がすでに座っていました。日曜日の18時開始、お台場、安くない入場料に、入場後も飲食費がかかる、といった「悪条件」をものともせず、ほぼ満員。実はここのイベントには何度も来ていますが、いつも満員、または満員に近いお客さんが集まっています。この集客力は見事です。
開始30分前の17時半に行ってみると、ほぼ満席に近い人々がすでに座っていました。日曜日の18時開始、お台場、安くない入場料に、入場後も飲食費がかかる、といった「悪条件」をものともせず、ほぼ満員。実はここのイベントには何度も来ていますが、いつも満員、または満員に近いお客さんが集まっています。この集客力は見事です。
さて住宅地図の存在を知っている人は、さほど多くないような気がします。むしろこの地図の存在を知っている人は、特別な業界に属しているとも言えそうです。例えば弊社の週刊誌の編集部にはもちろんあります。事件事故の取材には欠かせません。マスメディア以外では、警察や消防といった役所関連でしょうか。そのほか私には想像もつかない使われ方をしている可能性はあるにせよ、それほどの部数が出ているとは思えません。一番分厚い住宅地図は福井市のものだそうですが、1万9000円だそうです。だれもが簡単に買える値段ではありませんね。
イベントは住宅地図の市場をほぼ独占しているゼンリン(外部サイトへリンク)の調査員3人がゲストとして登壇して始まりました。冒頭、烏口で等高線を描く職人の動画が披露され、いとも簡単に地図の世界に引きずり込まれました。話には聞いていましたが、烏口で等高線を引くところを見たのは初めてでした。
地図を見ながら、他人の家の表札やマンションの入居者の名前を確認していくという話は、聞く前からドキドキしました。犬に吠えられるなどは苦労のうちに入らないようですが、雑居ビルが密集する繁華街や坂道・階段だらけの住宅街を調査していく話は、このところの酷暑のこともあり、目眩がしそうでした。
また昼食は神社、トイレはガソリンスタンドを借りることが多いという話など、調査員の方々が見ている町の姿と私が見ている町の姿は明らかに違うということがわかります。
ゼンリンといえば、今ではグーグルマップの右隅に「ZENRIN」の文字があるように、電子媒体に地図データを提供する会社として知られていますが、実はそのもとになっているのが、私の目の前で苦労話をされている調査員の方々の地道な調査なのです。
登壇したのはいずれもベテランの調査員の方々で、みなさん笑顔がいいのが印象的でした。おそらく調査中に怪しまれない技法のひとつとして身につけたのではないか思います。
彼らが見てきた20年、30年の日本の変化を是非とも聞いてみたいと思いますし、他にもいろいろ突っ込みたいところがたくさんあります。真夏の夜、刺激的なひとときでした。
編集部 田中比呂之(ひろし)