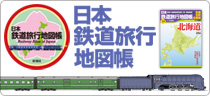鉄道と文学を題材にしたエッセイの類は、これまでにもたくさん刊行されています。最近も原口隆行さんが鉄道ジャーナル誌の連載をまとめて『文学の中の鉄道』(交通新聞新書)を出されています。
夏目漱石『三四郎』の一節にずっと気になってたところがありました。三四郎が九州から上京する列車の中の描写です。列車は京都を出て米原方面へ向かっているところだと思います。引用してみます。
--爺さんに続いて下りたものが四人程あったが、入れ易って、乗ったのはたった一人しかいない。固から込み合った客車でもなかったのが、急に淋しくなった。日の暮れた所為かも知れない。駅夫が屋根をどしどし踏んで、上から灯の点いた洋燈を挿し込んで行く。三四郎は思い出した様に前の停車場で買った弁当を食い出した。(夏目漱石『三四郎』新潮文庫より)
この引用部分は関川夏央さんも『汽車旅放浪記』(新潮文庫)で取り上げています。関川さんはここに出てくる駅がどの駅かを、当時の時刻表を駆使して推理をされています。私が気になっていた一節は、駅夫が屋根をどしどし歩いているところです。屋根から洋燈(ランプ)を挿し込むということはどういうことだろう、と思ったのです。
時代は日露戦争後の明治末期です。この頃の客車には現在のような電灯がついていませんでした。それで夕方になると停車駅で、火の点いたランプを屋根から差し入れていたというのです。漱石が何気なく書いている一節も、それから100年以上年月が経過し、当時は日常として行われていたことも、説明がないとわからなくなっているのですね。
すでにこの頃から客車に車軸発電機が取り付けられ、車室に電灯が備わり、次第に洋燈は使わなくなったようです。「なるほど、そういうことか」と思ったのですが、実はこの洋燈を収納していた小屋を、21世紀の現在でも見ることができます。
当サイトにもアップしましたが、ご覧ください。


▲奥羽本線鷹ノ巣駅(明治32年)

 ▲東北本線片岡駅(明治30年)
▲東北本線片岡駅(明治30年)
ホームにあるので目にすることもあるかもしれませんが、注目されることもなく、しかし100年以上の歳月を過ごしているランプ小屋。明治期には重要な役割を担っていたということを、見かけたときに思い出してみてください。
編集部 田中比呂之(ひろし)