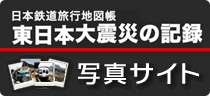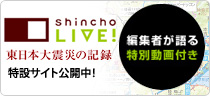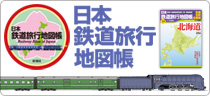ようやく津軽海峡を渡る日が来ました。昨年末、試運転を始めて以来、半年近く北海道にとどまっていましたが、ついに青函トンネルをくぐります。地図は東北地方全域、路線・駅は東北本線仙台以北の60路線、665駅を公開します。
駅スタンプの嚆矢は、昭和6年の福井駅とこのブログで書きました。福井駅長考案のものだということです。では鉄道スタンプの起源となると、いったいいつのことになるのでしょうか。6月2日に「日光牛車鉄道」さんが青函航路のスタンプを投稿されています。これは昭和4年の「北海道樺太視察旅行」なるツアーの栞に押印された津軽丸のスタンプです。旅の記念にスタンプを押すという行為は、昭和6年以前からあったという証明ですね。
駅名に関する書籍は、これまで数え切れないほど出版されています。地名や姓名などとともに、いつの時代でも売れ筋であることがわかります。北海道の路線と駅について、簡潔にわかりやすく編集された書籍を最近手にしました。『北海道の駅878ものがたり 駅名のルーツ探求』(富士コンテム)というB5判の書籍です。平成16年の発行なので、10年近く前の刊行です。
『百駅停車』を編集してから、駅をめぐる旅に嵌まっています。著者の杉﨑行恭さんに誘われて、この週末、静岡鉄道の駅をめぐってきました。清水と静岡の市街地を結ぶ鉄道だけあって、杉﨑さんお好みの狭小駅が連なっていました。この鉄道はもともと静岡茶を運ぶために建設されたそうですが、今は沿線の足として日中6分間隔で電車が走っています。
昨日は「いい駅、見つけました」で津軽線の大川平(おおかわだい)駅をご紹介しました。今日はその余談です。前にこのブログで「似たもの駅舎」として千歳線の植苗駅と美々駅の写真を並べてみました。今日はその津軽線編。大川平駅から2つ青森寄りに大平(おおだい)駅、さらに新中小国信号場を挟んで中小国駅があります。大川平、大平、中小国の3駅が似たもの駅舎です。
津軽線も田植えの季節を迎えていました。木々の緑は濃く、畦道の草も鮮やかな緑です。田んぼの水が風でわずかに波立ち、風が止むと駅舎がそこに映ります。5月も末になるというのに、駅前の桜の木に葉桜が残っていて、この地でも春の訪れが遅かったことがわかります。
『日本鉄道旅行地図帳』を企画したとき、サブタイトルとして「全線全駅」という文字を入れることは、最初から決めていました。悩みに悩んだのが、「全廃線」という文字を入れるかどうかでした。語呂もいいし、納まりもいい。鉄道をよく知る人たちに、強くアピールができる文字です。反面、編集する側の責任は重大です。最終的に、自分に「覚悟」を促す意味で、入れることにしました。
このブログのタイトルを決めました。「悠悠自鉄」。ありがちな「もじり」ですが、よろしくお願いします。人生の半ばはとっくに過ぎていますが、悠悠自適などとは縁遠い生活をまだまだ続けなくてはなりません。悠悠自鉄には、のんびりと鉄道を楽しみたいという願いを込めております。なお「鉄」の字はJR各社のロゴをまねて、金編に「矢」という字を使いました。誰だって金を失いたくありません。